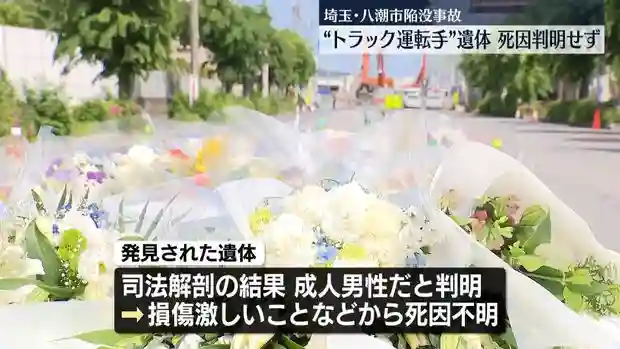「大卒の就職率30%台」の試算 デフレ・不動産不況に加え、トランプの米国との経済戦争が直撃する中国で、その影響が社会不安に直結するかもしれないことを予想させる、ある試算が発表された。 3月10日、香港科学技術大学教授・経済学者の丁学良氏は香港紙の「信報」で「内地大卒失業大軍は3000万人に達しているかもしれない」とする論評を発表した。 香港人の言う「内地」とはすなわち中国大陸、香港以外の中国全域を指している。論評の中で丁学良氏はまず、自らの調査と試算に基づいて、「昨年度の内地の大卒の就職率は30〜35%程度である」との結論を出した。 こうした上で丁教授はさらに、2020年から2024年までの毎年の「内地大卒数」を基数にして、この5年間で「卒業はすなわち失業」とまでいわれる大卒の失業者数を割り出したところ、「約3000万人程度ではないか」との衝撃的な推測数字を出した。 おそらくそれは、実態に近い数字であると思うが、今後の状況はさらに悪化する一方であろう。3月20日に中国国家統計局が発表した2月の16〜24歳(学生を除く)の都市部若年失業率は16.9%と、1月の16.1%から上昇した。上昇は2カ月連続となった。25〜29歳の失業率も6.9%から7.3%へと上昇。30〜59歳の失業率も4.0%から4.3%に上昇したと言う。 実際の失業率は統計局の公式発表よりも倍以上に高いのは中国国内の常識でもあるが、いずれの数字も「上昇」していることには、さらに注目すべきである。今後の雇用情勢がさらに厳しくなること示唆している可能性があるからだ。 その一方、今年の大卒数は史上最高の1220万人以上であるから、今年の大卒失業率はさらに上がることとなる。数千万人単位の大卒の若者たちが職もなく行き場を失うような事態は、いずれ、国内の大動乱の発生に繋がりかねない性質のものである。 デフレ・不動産不況が続く経済情勢 事態が悪化すると考える背景には、いうまでもなく現状の経済状況の悪化が続いているという現実がある。3月になってから各方面が公表した一連の経済関連数字をみると、2025年に入ってからの中国経済は依然として深刻な不況にあることが分かる。 まずは3月2日、中国指数研究院が公表したところでは、今年1〜2月、全国で企業規模100位以内の不動産開発大手(百強房企)の売上総額は4479.9億元、前年同期比では5.9%減であるという。減少幅は以前より小さくなっているものの、不動産市場衰退の流れは依然として継続していることが分かる。 3月7日、中国税関総署が公表した数字によると、今年1〜2月、中国の対外輸出総額は5399.4億ドルで前年同期比では3.4%増である。それに対し、輸入総額は3694.3億ドル、前年同期比では8.4%減であるという。輸出が3.4%増となっているのは、トランプ政権の20%新関税実施の前に、米国の商社などが急いで中国からの輸入を集中的に増やしたことが要因の一つだと思われるが、「輸入8.4%減」は逆に、中国の国内需要が大幅に萎縮していることを示している。 また、3月9日、国家統計局が2月の生産者物価指数(PPI)を公表した。それは前年同月比2.2%下落、2022年10月以来の連続29ヶ月の下落となっている。連続29ヶ月のPPI下落は、完全に大不況級のデフレ、その背後にあるのは企業の業績悪化、倒産と失業の大量発生である。2025年も、中国経済は「地獄の一年」となろうとしているのである。 北京・上海「消費急落」の衝撃 それを裏付ける数字も出ている。 昨年2024年4月27日公開の「中国の実態は大経済都市『魔都』上海の凋落にすべてが表れている」で解説したように、中国の消費を代表する指標が、上海・北京の2大都市の動向である。その2市の数字が「続落」どころか「急落」を示しているのである。 4月22日、北京市統計局は今年第一四半期(1〜3月)の市内の消費事情を示す一連の数字を公表した。1〜3月の北京市社会消費品小売総額は約3456億元、前年同期比では3.3%減、中でも3月は1049億元、前年同月比9.9%減となっている。つまり「消費1割減」、それはまさに「消費の急落」ともいうべき事態の発生である。 さらに、北京の3月の前年同月比消費減のうちわけを見てみると、外食の小売総額は3.1%減、化粧品類の小売総額は10.9%減、日用品類の小売増額は13%減、スポーツ・娯楽用品類は17.6%減、「文化・オフィス用品類」は22.6%減、自動車は20.6%減、そして通信機器類は38.2%減である。それに対して、食糧・食品の小売上総額は1%増、「金銀珠宝」のそれは28.5%増となっている。 以上の数字からも分かるように3月において北京市民は、外食や娯楽を控えめにして、化粧品や日用品の消費を大幅に減らし、車や通信機器に対する需要を急速に萎縮させていることはわかる。また、「文化・オフィス用品類」の小売総額の22.6%減は、北京市におけるビジネス活動の縮小を意味している。 その一方、「金銀珠宝」の小売総額は28.5%も増えている理由は、北京市民が日常の消費を徹底的に削る一方、将来への大いなる不安に備えて、そして金融に対する不信感のために「究極の貯蓄手段」に走っていることを示している。 4月23日、上海市当局も第一四半期の消費に関する一連の数字を公表しているが、そこからは、上海市の3月の社会消費品小売総額は14.1%減となっていることは分かる。そのうち、外食のそれは6.2%減、家庭用電器は4.7%減、自動車は19.4%減など、北京と同様の消費急落が起きている。 中国の消費をリードする2大都会、北京と上海で起きている深刻な消費急落はこれから、全国に広がっていくはずである。米国との貿易戦争によって今後、中国の対外輸出も大幅に減ることは予想される。こうした中で内需としての消費が冷え込んでいくと、中国経済を襲っている大不況はさらに深刻化していくことは容易に予想できる。 そしてこのことは、間違いなく、すでに高水準である大卒失業率、若年失業率のさらなる悪化を招く。「完全雇用」を約束する共産主義国であるはずの中国には、失業率のとめどない上昇による社会不安の未来が待ち受けている可能性が高いのである。 中国の実態は大経済都市「魔都」上海の凋落にすべてが表れている