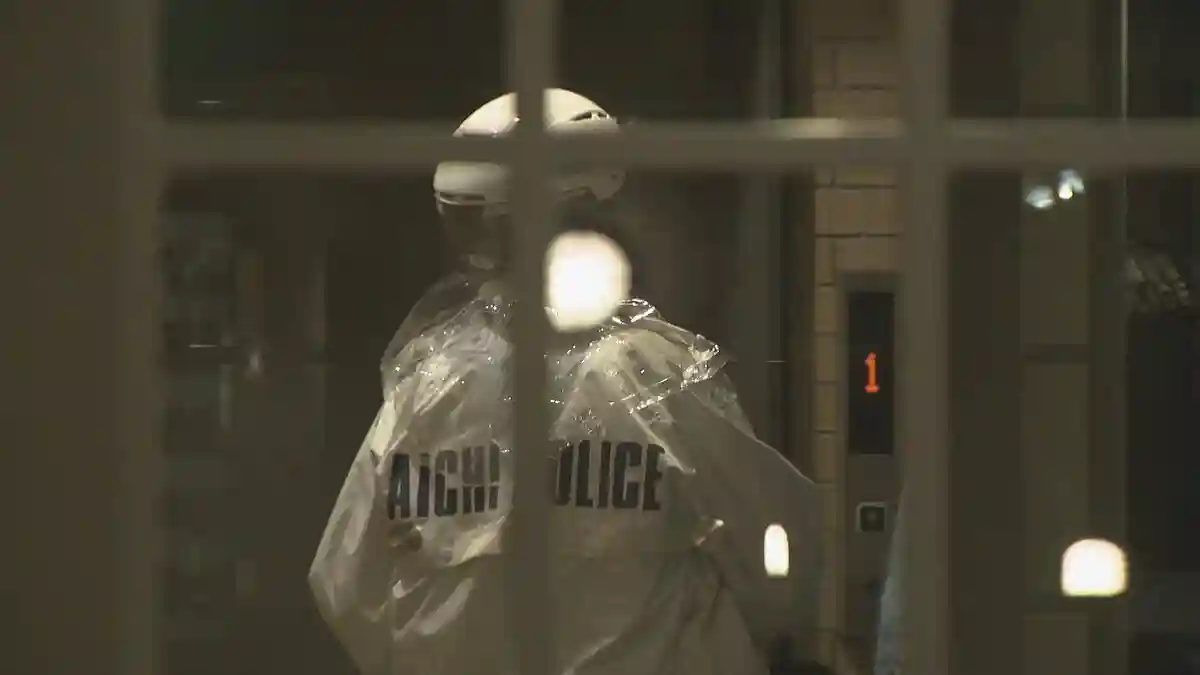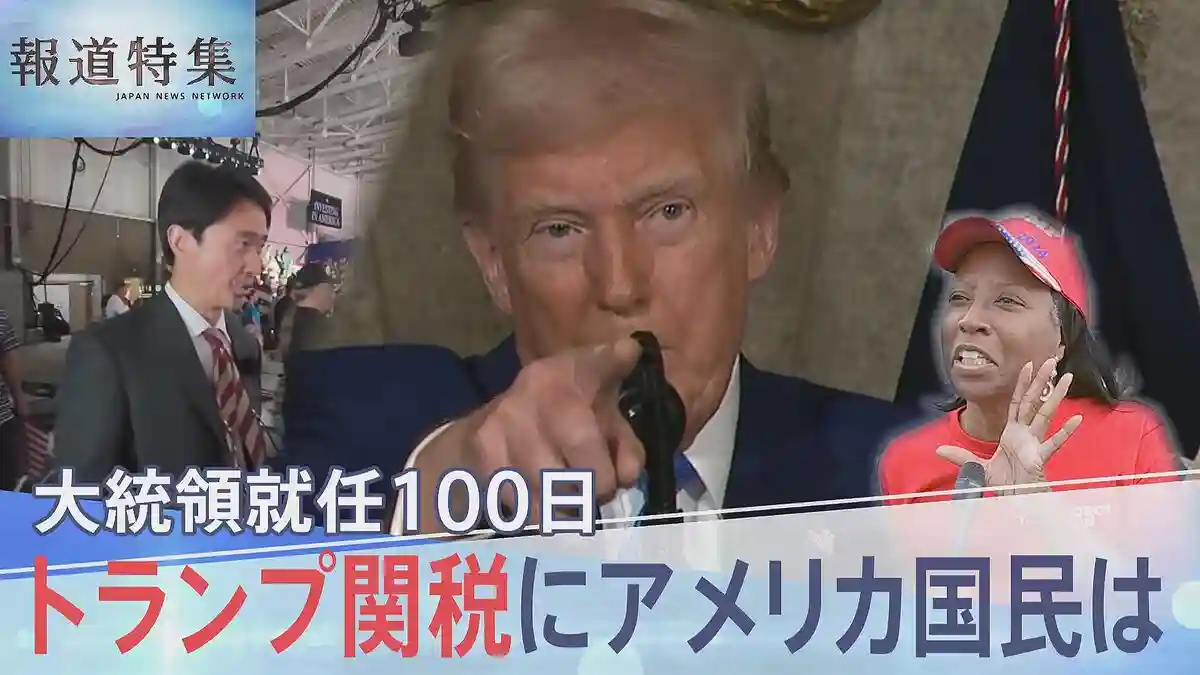山口有紗医師は、虐待などの逆境的な体験をしたこどもや、死にたい気持ちを持つこどもたちの相談などにあたってきました。こどもたちができるだけ安心して日々を暮らしていくために、大人ができることを聞きました。 ——トラウマについてうかがいます。こどもの頃の虐待やいじめ、家庭の不和など、つらい体験をどう考えればいいのでしょうか? 逆境体験を虐待やネグレクトなどの限定的な定義でとらえても、こどもの頃に何らかの逆境体験がある人は、アメリカだと7割ぐらい、日本でも3、4割ということが研究の中で明らかになってきました。つまり特別な人のことではなくて、一般的に起こりうる、すべての人のこととして扱わないといけないということで、「トラウマインフォームドケア」といって、すべての人がトラウマのことを知っている文化を作る必要性が認識されてきたんですね。 トラウマインフォームドケアというのは、特別な専門家だけでなく、わたしたちみなが「逆境体験が人生に与える影響」を知って、その影響に気がつき、二次的な傷つきをうむような言葉や状況を避けるなど、こどもの傷つきに応じて、権利を尊重した対応を心がけ、それぞれができることをしていくことです。 もちろん、何よりも逆境自体の予防が大切で、例えば、(こどもの逆境体験につながるような)養育者の経済状況や働き方を支援するとか、こども・若者の居場所を作るとか、暴力、体罰に対する認識を変えていく法律を定める…など、逆境体験を予防するための方策に取り組む必要があります。 逆境体験が起きてしまった時、その影響の程度によっては、同時に専門のケアが必要な場合もあるので、医療などケアの体制を整え、アクセスできる人とできない人といった格差がないようにするなども必要です。逆境体験の予防とケアの両輪で進めていくことが大切かなと思います。 ■こども時代の逆境体験は決して「一巻の終わり」ではない ——逆境体験がある人は、その後の人生が難しいものになってしまうのでしょうか? 人生を生き抜くのにレジリエンス(弾性、しなやかさ)が重要だといわれますが。 例えば、「逆境体験は人生の悪い結果につながる」という考え方があるとすると、逆境体験がある人はとても不安になるかもしれません。自分の人生は駄目なんだなって。でも研究が進む中で、逆境体験は決して「一巻の終わり」ではないこともわかってきました。 こども時代に苦しい体験がある場合でも、いろいろなポジティブな体験や関係性や環境が、逆境の影響を和らげる可能性があることが知られています。そして、こどもたちやわたしたちは、すでに(人生を生きる)力を持っている。まさに、こどもをただの逆境の「犠牲者」ととらえるのではなくて、力のある生きる主体としてとらえることの重要性が強調されています。 人の回復力を考える概念にレジリエンスというのがあります。レジリエンスとは何かというと、とてもつらいことがあっても、自分の内外の力や智慧を周囲と協力しながら動員して、自分のちょうどいい状態を保つ力だとされています。昔は「折れない心」のように、個人の楽観性とか、認知能力、非認知能力などに焦点が当たっていた時期もありました。でも最近の研究では、個人の資質はもちろん大事ですが、周りのあり方や環境もレジリエンスの一部だという考え方に変わってきているんです。その人がどれだけ打ちのめされた状態でも、周りの人がその人とどう関われるか、回復してウェルでいられるための環境をどう整えられるかが鍵になってくるんです。つまり、わたしたち一人一人が、誰かのレジリエンスになっているかもしれないということかなと思います。 わたしは(診療の中や児童相談所などで)、虐待やネグレクトなどのつらい体験をされた方たちと日々関わる中で、こどもが一言も発しないまま面談を終えたり、関わったお子さんが、またまったく同じ状況で保護されたりするなど、自分たちがやっていることは本当に意味があるのかなと無力感を持つこともあるし、他の職員さんたちの葛藤や無力感に触れることもあります。いますぐできることはきちんと行った上で、それでもいますぐ変わらなかったとしても、学びながら大切なことを真摯に続けていけば、実はその関係性が20年後、30年後にその子たちにじわーっと効いてくることもあるのかも、と信じています。 ■こどもには「安全感」と「見通し」が大事 こどもたちは、もともと力のある存在です。こどもたちの力を支えるものはいくつかあるのですが、「安全感」と「見通し」が大事だといわれています。自分は今ここにいて大丈夫だと感じて、明日も3日後も2週間後も多分大丈夫だという見通し。今ここが大丈夫な感じが、今後も続いていくんだろうなという見通しを作るのが大事だといわれています。 いわゆるトラウマ体験の逆ともいえるかもしれません。トラウマというのは、きょう、殴られるかもしれないし、ご飯がもらえるかどうかわからない、そしてそれを自分ではコントロールできない、自分は何もできない、独りぼっちで誰も助けてくれないみたいな感覚になることも多く、この安全感とその見通しが持ちにくい、しかも孤独の中でその状態を強いられてしまうということでもあります。 では、その「安全感」「見通し」を持つにはどうすればいいのかということで、ここでは、3つくらいのことをご紹介したいと思います。 まず、例えば予測できるようなルーティーンを作ること。それは「朝は6時半に起きなきゃ」ということではなくて、例えば起きた時に、家にあるサボテンに挨拶をするとか、道を歩く時に、いつもいる猫を探すとか、だいたい同じ時間に、何か飲んでほっと息をつくとか、そういう自分にとって今日も明日もこれは変わらない、その子が安心してコントロールできるルーティーンを作ることですね。 ほかには、そのこどもが何か選べる、意見を言える状態を作ることです。例えば、医療処置もトラウマになることがありますが、病院で注射をする時に、右腕にするか左腕にするか選べるとか、シールはアンパンマンかポケモンがいいかとか、こどもが選べるようにする。日々の暮らしの中に選択肢がある、それをこどもが実感できることが大切です。 そして最後が「つながりを感じる」です。まさにその子にとって安心できる人とつながれるような仕組みを作っていく、それは日々の暮らしの中でもできるかなと思います。 わたしが関わってきたこどもたちから教えてもらったことは、「大人って何かアドバイスしたがる」と。「こうした方がいいよ」みたいな。でもこどもたちは、すでに自分たちの力で工夫していることもいっぱいあるので、大人は「こうしたら?」と言う前に、「そういう時ってどうしてる?」とこどもに尋ねてみるのもいいですね。 ■アタッチメント(愛着)…「くっつく」を繰り返し、自分は助けてもらえる存在なんだと感じる ——子育てで大切といわれるアタッチメント、愛着形成についてもお願いします。 それは動物としての基本なんですね。人間だけではなくて動物が、嫌だな、つらいなという状況の時、1人で何とかするんじゃなくて、関係性の中で調節して「不快」を「心地よい」「楽な状態」にしていく仕組みのことです。「愛着」というと、深い愛情みたいな風に強調されることもありますが、実は「着く」=くっつくというのが大事な概念です。 「くっつく」ことを繰り返していくことで、こどもたちは、しんどい時に助けてもらえると感じ、自分は助けてもらえる存在なんだ、この世界は自分が困ったら助けてくれるんだ、という自分に対する信頼感と、社会に対する絶対的な信頼感を持つことができる。そして、そういう環境が「安全基地」になる、自分がすごくつらい時、そこに戻って来られる、とっても強力なガソリンスタンドがいつもオープンしてます、みたいな感じですね。100%、いつも対応じゃなくてもいいんです。毎回だとちょっと不自然で、9割ぐらいは営業しているガソリンスタンド、つらい時はそこに戻って来られるとなると、こどもたちは安心して外の世界を探求できる。 あとはメンタライジングっていうんですけど、アタッチメント関係が築かれていく間柄で、例えばお腹が痛い子に大人が「お腹痛いね」ってつらそうな顔や声で言うと、こどもは「ああ痛いってこういう顔なんだな」「つらいってこういう声なんだ」とわかり、感情に名前がついていく。それが自分の心の理解や他者の心の理解、共感にもつながっていく。 そしてアタッチメントというと、母子関係、家族のものだととらえがちですが、この世界が安心な状態でないとアタッチメントは形成されにくいですよね。家庭の外の要因もアタッチメントの形成に関わっているという視点をわたしたちはもっと持てると思います。 アタッチメントは1人の人との関係だけではなくて、例えば保育園の先生とか、いつも行く子育て広場のおばちゃんとかもこどもの「安全基地」になりうる。つまりわたしたち、すべての人たちもアタッチメントの担い手であるということです。また、アタッチメントで大切なのは、こどもたちが求めていない時に、過度にそのこどもの世界に入り込まないことだといわれています。 ——それから、先生がお子さんを育てる中で感じられたこととして、こどもが言葉を話せるようになると、大人たちはこどもに言葉で表現することばかりを求めてしまうが、こどもはそれを苦痛に感じることもある、言葉以外の表現も大切にしようと思われたんですね。 そうなんです。実は先日あるイベント後、参加者に感想を書いてもらうのに、文字でなくてもいいですと伝えたところ、8割ぐらいの人は絵など言葉以外の方法で表現されました。わたしたちが「感想は言葉で表すべき」といった考えにいかに縛られているか、いつでもそこから自由になれるんだなと。まさに書籍の中でも書いている、すべての人の中にある「子ども性」みたいなものにすごく感動しました。 あとは、言葉にすると、本質と違ってしまうこともあると思います。例えば、一時保護で児童相談所に来たお子さんが「家に帰りたい」と言ったにしても、いろいろな質問の仕方によって、そのこどもが「帰りたい」と言わざるを得なくなったのかもしれない。言葉に頼りすぎるのではなく、わたしは「聴けていない声」があるんだと考えるようにしています。わたしたちは、言語以外の豊かなものを本当はいっぱい持っていることに、気づいていたいなと思います。 言語以外の表現では、まさにこどもたちは豊かなバリエーションを持っている先生なんですよね。大人はこどもの言葉だけでなく、それを言った時の表情や声色、ためらった間があるとか、身体の様子や雰囲気も含めて感度高く受けとることが必要かと思います。 ——ウェルビーイングについて一番知ってほしいことは。 わたしは「死にたい」という子と関わることも多くて、そうした子にかなえたい願いを聞くんですけど、ある子が「ないね。だってさ。なんか大人見てるとみんな闇じゃね?」と。そうだなあと思いました。 自殺の原因は何かなどと考える時に、そのこどもと彼らを取り巻く事柄だけに要因を求めがちだけれども、社会が、わたしたち一人一人のきょうが、この瞬間が心地よい状態であること、そこをもっと大事にしてもいいし、こどもたちはそういった社会全体の一部であることを、こどもの日だからこそ、とらえ直していけたらいいなと思います。 大人たちも楽でいていいし、ホッコリする時間も大事。つらさの中で生きのびている人を「勇者」というなら、この現代社会に生きている人はある意味みんな「勇者」だと思うんです。自分の「ウェル」にちゃんと耳を傾けるということが、世界をちょっとずつ変えていくのかなと思います。 そしてそれは何か壮大なことではなくて、道で人とすれ違ったらニコッとするとか、バスを降りる時に運転手さんにありがとうございましたと言うとか、日常の小さい、地味なウェルをわたしたちは増やしていけるんじゃないか。誰でもそれはできるし、1億2000万人が1日ひとつでもやったら、とっても大きい力になるし、それはこどもたちにも絶対に伝わるんじゃないかなと思うんです。すべての人の権利と尊厳が保障されている世界は、わたしたち一人一人の、きょうのふるまいによって作っていけるものだと信じています。 山口有紗:小児科専門医・子どものこころ専門医、公衆衛生学修士。高校中退後、イギリスでの単身生活や国際関係学部での学びを経て医師となる。現在は子どもの虐待防止センターに所属し、地域の児童相談所などで相談業務に従事。国立成育医療研究センター臨床研究員、こども家庭庁アドバイザー。近著は「子どものウェルビーイングとひびきあう——権利、声、「象徴」としての子ども」(明石書店)、「きょうの診察室:子どもたちが教えてくれたこと」(南山堂)。