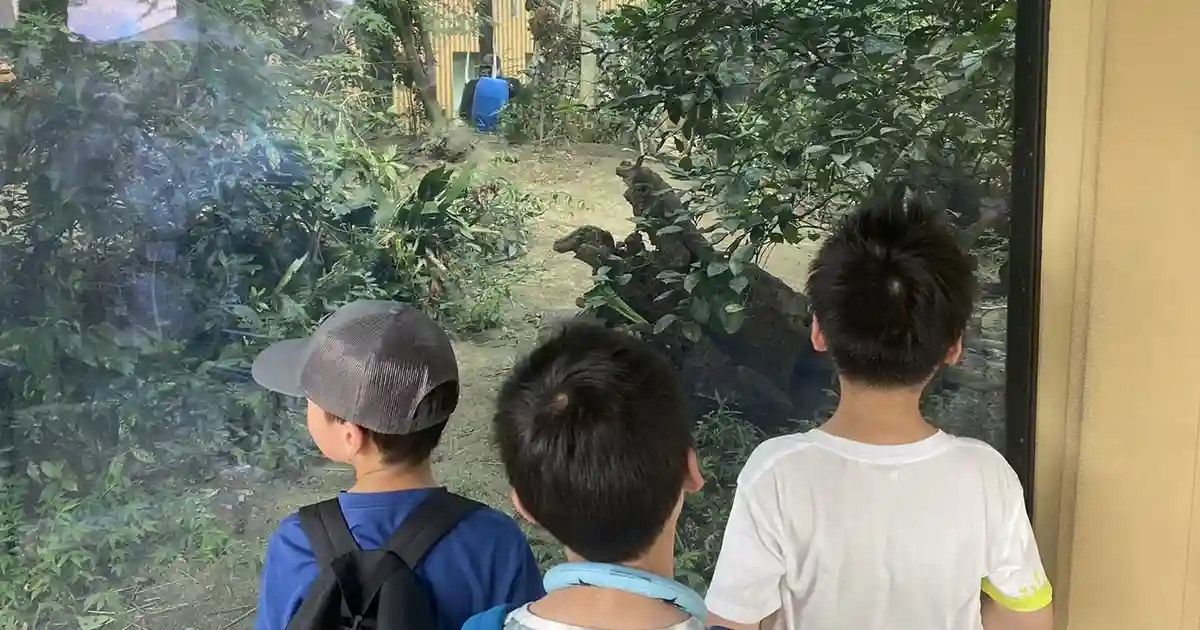
NPO法人『福祉広場』代表の池添素さんは、不登校や発達障害の子どもと親にかかわり続けて40年、子どもの不登校に悩み苦しむ親たちを支えている。 その池添さんと出会った家族と池添さんに、ジャーナリストの島沢優子さんが取材する連載「不登校と向き合うあなたへ〜待つ時間は親子がわかり合う刻〜」第15回では、池添さんと出会い、その考え方に衝撃を受けたという一般社団法人「こどもの応援団TEIEN」の代表・伊ケ崎大樹さんについてお伝えしている。 24歳の伊ケ崎さんは、不登校の子どもへの支援活動を通して池添さんと出会った。池添さんの考え方や行動に衝撃を受け、自らの支援のあり方にも変化が生まれていく。前編 【「してあげなきゃと思っていた」24歳相談員が反省した、不登校の子との向き合い方】 では、池添さんから学んだ「子どもを理解し、認めること」の本質についてお伝えした。 後編では、不登校の子どもや親と日々向き合う伊ケ崎さんの活動や考え方について。また、なぜ不登校支援をするようになったのか、その原点をジャーナリストの島沢優子さんがレポートする。 子どもの「学校に行く」は“免罪符” 例えば「明日は学校に行く」と言ったのに、翌朝になると「やっぱり行かない」と布団から出てこない。よくあることだ。期待しては夢破れてへたり込む親たちに、伊ケ崎大樹さんは「それは子どもにとっての免罪符なんですよ」と語りかける。 子どもたちは、こころのどこかで「自分は学校に行かないといけないのに……」と罪悪感を抱いている。親に「行く気はあるよ」というサインを出すことで、少しでも安心させたい。罪を逃れたいのだ。 「子どもは許しを求めてるんです。行かなかったときに、しょんぼりしないでください」と話す。免罪符を使えなくなってしまったら、子どもは余計につらくなる。よって「行こうとしただけでも進歩だよねと言ってあげませんか。お子さんは行かなきゃって思ってるんです」と伝える。 一方で、親が「行かなくてもいい」と言ったことに対して苦しむ子どももいるという。自分は頑張ってるのに、できないと思われていると感じる。親から見放されていると失望してしまう。微妙な気持ちを受容しなくてはならない。 「今日は休もうか」 この「今日は」が大切だと伊ケ崎さんは考える。気をつけていないと「今日も休もうか」「もう行かなくていいよ」と言ってしまいそうなときに「今日はとりあえず休もうか」と伝えるのだ。伊ケ崎さんは「子どもは、学校に行く気があるんです。その思いを自分の中でギリギリ保っている。行きたいけど行けないっていう苦しみを抱えているので、そこを理解してもらえたら」と話す。 子どもが「学校に行く」と言い出すことを伊ケ崎さんは「免罪符」と表現したが、池添さんは「それは子どものリップサービスや」と話していた。学校に行きたいという気持ちに嘘はない。それくらい親から自分を承認してほしいのだ。 肯定し、認めることで起きる変化 昨今、「不登校の子どもを学校に行かせるにはこうすればいい」といったノウハウを説明する言説がメディアにもあふれている。しかし、池添さんや伊ケ崎さんはひたすら目の前の子どもに向き合うことにこころを砕く。 支援するなかに中学生からかかわってきた高校生がいる。中学時代はずっとオンラインによる対応だった。当然ながら伊ケ崎さんは顔を出す。しかし、その子の画面はずっと真っ黒のまま。黒い四角形から声だけが漏れ聞こえてくる。そんなコミュニケーションだった。 とはいえ、伊ケ崎さんが勉強のコツなどを伝え課題を与えると毎日きちんとやってくれるので「本当にすごいなと感心していました」。こつこつ真面目に頑張れることは一見当たり前のように見えて難しいことなので、そのプロセスをいつもほめた。ほかにも、早寝早起きができた。宅配業者が訪れた際に玄関に出て対応した。簡単な家事を手伝った。そんな些細な行動を、黒い画面に向かって聞き出してはほめて、認めた。 「今日は何もできませんでした」 ぼそっと聞こえてくる後悔に対しては、「できなかったっていうことで落ち込めるぐらい習慣化できてるじゃん。いいじゃん、いいじゃん」と答えた。寝る時間が遅くなったなど、うまくいかなかったことを本人がどう見ているのか。そこを観察していると、日々後悔していることが伝わってきた。その後悔する気持ちの発露を、伊ケ崎さんは称えた。 ポジティブな結果ではなく、ネガティブな結果も温かく認めたのだ。何かができなかったとしても「でも、これはできるようになってるよ。焦らなくてもいいじゃん」と伝えた。ほかにも、無理しすぎないことを徹底させた。体が疲れてしまうと、メンタルヘルスに影響が出る。 「無理しなかった自分をほめてあげよう」と声掛けし、「今日は疲れて自習できません」と言われれば「疲れてできないって正直に言えるのはいいことだよ」と告げた。徹底して肯定し、認めた。 「いいじゃん! いいじゃん! めっちゃいいじゃん」 そう声をかけると、「ふふん」と鼻を鳴らすような音がイヤホンからかすかに聴こえた。黒い四角形の向こうに、照れくさそうな笑顔が見えた気がした。 子どもの自己決定を尊重する そこまで見守られた子どもが成長しないわけがない。一歩も外に出られなかった中学生は、通学型の通信制高校に入学した。久しぶりの学校に、苦戦しながらも通い続けている。 このケース、伊ケ崎さんは必ず許される「何か」を中学生だったこの子に用意している。例えば「休むときは休むって言ってくれていいからね」と伝えておいて「休みます」と報告してくれたことに対し、「言いづらかっただろうに、よく言ってくれたね」とほめる。伊ケ崎さんのこの対応によって、子どもには「自分で決めた結果、それをやらなかった」と自己決定した感覚が残る。 そこが「できなかったことも認める」ことの利なのだ。 こういった彼の対応は、臨床心理の学びから具現化されている。ひとつ挙げられるのは「ロジャースの受容と共感」や「ロジャースの3原則」と言われるものだ。米国の心理学者であるカール・ロジャースが提唱した「傾聴」の3つの構成要素で、「共感的理解」「無条件の肯定的関心」「自己一致」から構成される。 1,相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとするのが「共感的理解」。 2,相手の話を善悪や好き嫌いの評価をせずに聴き、相手の話を否定せず、なぜそのように考えるようになったかという背景を“肯定的な関心”を持って聴く。そうすることで相手は安心して話ができる。それが「無条件の肯定的関心」。 3,最後の「自己一致」は、相手に対しても、自分に対しても真摯な態度を貫き、話がわかりにくい場合はそのことを正直に伝える。わからないことをそのままにしておくことは自己一致に反するというわけだ。 このように臨床心理学のベースが支援行動を豊かなものにしている。そして、実はその豊かさは伊ケ崎さんの家族によってもたらされたものだ。 不登校の弟と優秀な兄の間で葛藤 弟が不登校だった。 うろ覚えだが、行き渋りが始まったのは弟が中学1年生のころだった。3つ上で高校生の伊ケ崎さんは、不登校の弟に対し憤りを感じていた。同じ部屋で寝起きしていたため、学校から疲れて帰ってきた兄はYouTubeを見てけらけら笑っている弟の姿に腹が立った。 「おまえばっかさぼってて。こっちは勉強してんだよ」 学校に行けるといいのにと心配したり、かかわろうとは思わなかった。その後、大学受験で第一志望の国立大学に落ちた。毎日10時間以上勉強したのにもかかわらず失敗したことは大ショックだった。それでも名門私立の理工学部に合格。物理学を専攻した。 大学に入り、塾講師のアルバイトをした。合格、不合格の明暗を目にするなかで、受験体験をつらいものにして欲しくないという思いが芽生えた。受験を失敗した自身の姿を投影したのかもしれない。オンラインで学習支援を始めた。 不登校になっている中学生、高校生の多さに驚かされた。接するなかで、自分の弟に対する当時の感情と、子どもたちに向けた感情の違いを肌で感じた。自らは不登校の当事者ではなかったものの「不登校家族」の経験がある。学校に行けない子どもを抱える親たちの気持ちに寄り添えるような気がした。2年生で公認臨床心理士の資格を取得できる大学への編入を決めた。 臨床心理を学び、子ども支援の仕事をするなかで、優秀な兄へのコンプレックスにあらためて気づいた。不合格になった第一志望は兄が現役合格し通っていた大学だった。三男として生まれた末弟の気持ちがわずかではあるがわかるような気がした。 「もがいて苦しんで、コンプレックスも味わった。アイデンティティの確立と崩壊を繰り返して思春期を送ってきました。いろいろ模索しながらここまで来た気がします」(伊ケ崎)。 そのような「物語」があるからこそ、豊かな支援ができるのではないか。不登校だった弟への嫌悪。兄へのコンプレックス。すべてが子ども支援という仕事の糧になっているようだ。そこに池添さんという師匠の存在もある。 「いやいや。まだまだ青いというか、自分はまだまだだなっていうのを池添先生と話すといつも痛感させられます」 実家で暮らす弟が最近保育園でバイトを始めたと聞いた。黒い四角形の背後にあるものを、これからも追い続ける。 【前編を読む】「してあげなきゃと思っていた」24歳相談員が反省した、不登校の子との向き合い方









