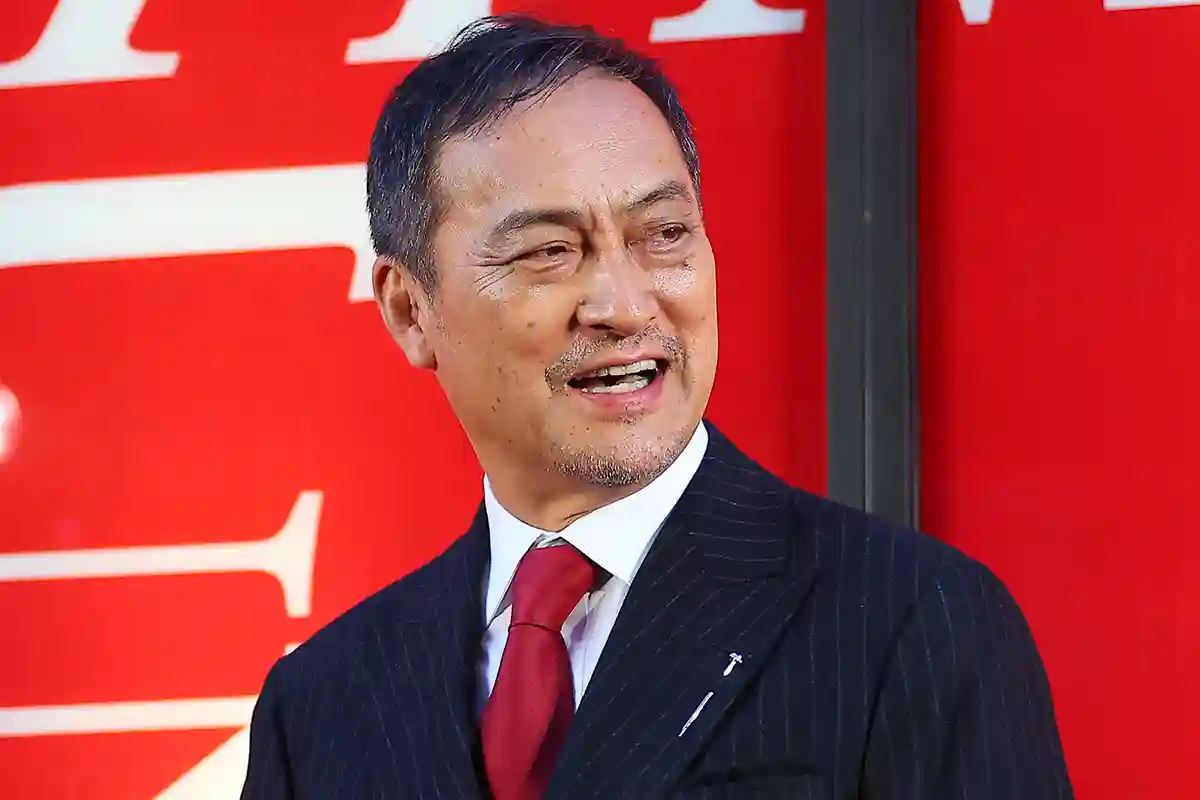すでに高かった前年より16%上昇 ゴールデンウィーク(GW)が終わって、ホテルの宿泊費の高騰にため息をついている人が多いのではないだろうか。とりわけ都市部はひどい。宿泊した人は、支払いを終えてそれを痛感しただろうし、ホテル代が高すぎるあまり旅行に行くことを躊躇した人もいるだろう。むろん、以前からGWはホテルの宿泊費が高かった。しかし、昨今はいわゆる閑散期でも十分に高い。 【衝撃写真!】浅草寺の境内で“水浴び”する中国人観光客 ほか 東京商工リサーチの調査によると、ビジネスホテル12ブランドの2024年10〜12月期の客室単価は平均1万6,289円で、対前年同月期で17・8%上昇した。コロナ禍で最安値だった2021年の平均8,171円にくらべると、99・3%と2倍近くも高くなっている。 ビジネスチャンスを逃せとはいわないが… こうして高騰した価格を基準にGWの特別料金が設定されるのだから、高額になる。日本経済新聞社が全国5都市の100ホテルを対象に行った聞き取り調査によれば、GW初日だった4月26日の平均客室単価は1万9,269円で、前年を16%上回った。 私の最近の経験を記せば、GW前の平日に名古屋に宿泊したが、駅に直結して便利なホテルAは1泊7万円弱。同様に駅に直結するホテルBは3万円強。結局、ビジネスホテルに宿泊したが、1泊1万9,000円だった。名古屋在住の知人と話すと、「ホテルAにはかつて1万5,000円くらいで泊ったし、ホテルBも1万円少々で泊れた」とのこと。それは10年近く前の話にせよ、物価上昇率にくらべれば恐ろしい高騰ぶりだ。 また、以前はこうしたホテルチェーンの運営会社に知人がいると、特別料金で宿泊させてもらえることも少なくなかったが、昨今はそんな話はとんと聞かれない。名古屋のホテルBについて、知人に聞いてみたことがあるが、いまはそのような特別あつかいはしないという。理由を尋ねると、「高値でも外国人が泊ってくれるので、割引する必要はないから」という話だった。 外国人にとっては3〜4割のディスカウント同様 観光庁が2024年の宿泊旅行統計をもとに、のべ宿泊者数に占める外国人の比率を集計したところ、東京都が51・5%、京都府が50・1%、大阪府が44・9%で、日本全国では25・2%だった。日本政府観光局(JNTO)の発表では、2025年1〜3月の訪日外客数は1,053万7,300人で、昨年の同時期より200万人近く、すなわち2割以上増えているので、宿泊者数に占める比率もさらに高まっているはずだ。 そして外国人観光客に尋ねると、概ね日本のホテル価格は「安い」という答えが返ってくる。当然である。現在、日本人に空前の外国人旅行者が訪れているのは、日本の魅力が向上したからではない。過度の円安によって日本に値ごろ感が生じたため、押し寄せるようになったにすぎない。 購買力平価という言葉がある。これは各国の物価水準から為替レートを求める考え方で、たとえば、アメリカで1ドルのハンバーガーが日本では100円だという場合、1ドルと100円の購買力は等しいので、1ドル=100円が妥当だ、ということになる。第一生命経済研究所の首席エコノミストである熊野英生氏の試算によれば、2024年1〜3月の購買力平価は93・7円だという。 現在、トランプ関税の影響で「円高」に触れたことになっているが、「円高」とされる1ドル142円として購買力平価と比較しても、ドルと円の相対比率は93・7円÷142円×100=66%。つまり、円は34%も割安だということになる。これは日本人の購買力が34%も低くなっているということで、そうである以上は物価高が避けられないということであり、一方、外国人にとって日本旅行はきわめて割安だということである。 ホテル価格に即していえば、日本人にはとんでもない高騰でも、外国人にとっては30%や40%のディスカウント料金で宿泊できるということになる。 兆を超える税金で救済されたホテル業界 要するに、外国人にとってはホテルだけでなく日本のすべてが割安で、お得感がある。だから、すでに大幅ディスカウントも同様だったホテル価格が多少上昇したところで、彼らには大きな影響はない。その結果、宿泊費を値上げしても、外国人を中心に高い稼働率が維持されるとなれば、ホテル側は料金を上げ続ける。外国人一人当たりの宿泊費も平均泊数も増加し続けている以上、ホテル側が強気の料金設定をするのは、ある意味では、当然だといえる。 しかし、私たち日本人は、ここで立ち止まって考えてみる必要がある。 2020年にはじまった新型コロナウイルスの感染拡大で、ホテル業界が苦境に陥ったのは記憶にあたらしい。増え続けていた外国人の宿泊者はほぼゼロになり、緊急事態宣言が発出されて国内の出張や旅行の需要も激減。観光庁のデータによれば、2020年5月の国内のホテル宿泊者数は、前年同月期にくらべて84・9%も減少。先行きがまったく見えない状況に、ホテル業界からは人材が次々と流出し、人手不足も深刻になった。 そこで政府が、観光などの需要を喚起し、ひいては経済の再興につなげようとして実施したのが「Go Toキャンペーン」だった。なかでも、宿泊や運輸などの観光関連産業の打撃が多きかったことから、それらの需要を掘り起こすための「Go Toトラベル」にはとくに力が入れられた。 ホテルに関していえば、1人1泊あたり2万円を上限に旅行代金の2分の1を支援するという制度だった。なにしろ、2020年度第1次補正予算に計上されたGo Toキャンペーンの総事業費1兆6,794億円のうち、1兆3,542億円がGo Toトラベルに割り振られたのである。 いうまでもないが、Go Toトラベルの事業費は国民の税金だった。それが兆を超える規模で充てられた。すなわち、いま外国人が次から次へと宿泊するのをいいことに、日本人にとってはべらぼうな高値を押しつけるホテル業界は、わずか4、5年前の苦境時にわれわれの税金で救済されていた、ということだ。ところが、ひとたび外国人が押し寄せると、手のひらを返して日本人に高値を押しつける。こうした姿勢が許されていいものか。 せめて「日本人割引」を 外国人が高値で泊ってくれるというビジネスチャンスを逃せとはいわない。しかし、外国人を当てにして強気の値段設定をし、結果として日本人が宿泊できなくなるのは、本末転倒だというほかない。日本人の税金を注ぎ込んでもらった過去がある以上、なおさらだ。 外国人向けの二重価格をためらうのであれば、日本人にかぎって宿泊費を割り引けばいい。「日本人割引」の適用で、せめてコロナ禍前の価格にすべきだろう。税金が投じられた以上、それは合理的な策であるはずである。 それとも、宿泊費用が安い日本人客が増え、高額でも泊ってくれる外国人宿泊客の比率が下がるのがイヤなのだろうか。しかし、いつまたパンデミックが起こらないともかぎらない。この先、円高が急激に進んで、外国人観光客が激減することもあるかもしれない。なんらかの災害を機に、外国人観光客が日本を避けるようになるかもしれない。それを考えれば、大事にすべきなのは日本人の宿泊客だと思うのだが。 いまのホテル業界を見ていると、バブル期の地上げが思い出される。目の前の収益に目がくらんだ不動産業者が、地道に暮らしている人を追い出して土地を買い取り、地価を吊り上げ、そこに銀行が際限なく融資した。結果はご存じのとおりである。 どんな状況下でもホテル業界を地道に支えてきて、これからも支えるのはだれなのか。再考を促したい。 香原斗志(かはら・とし) 音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。 デイリー新潮編集部