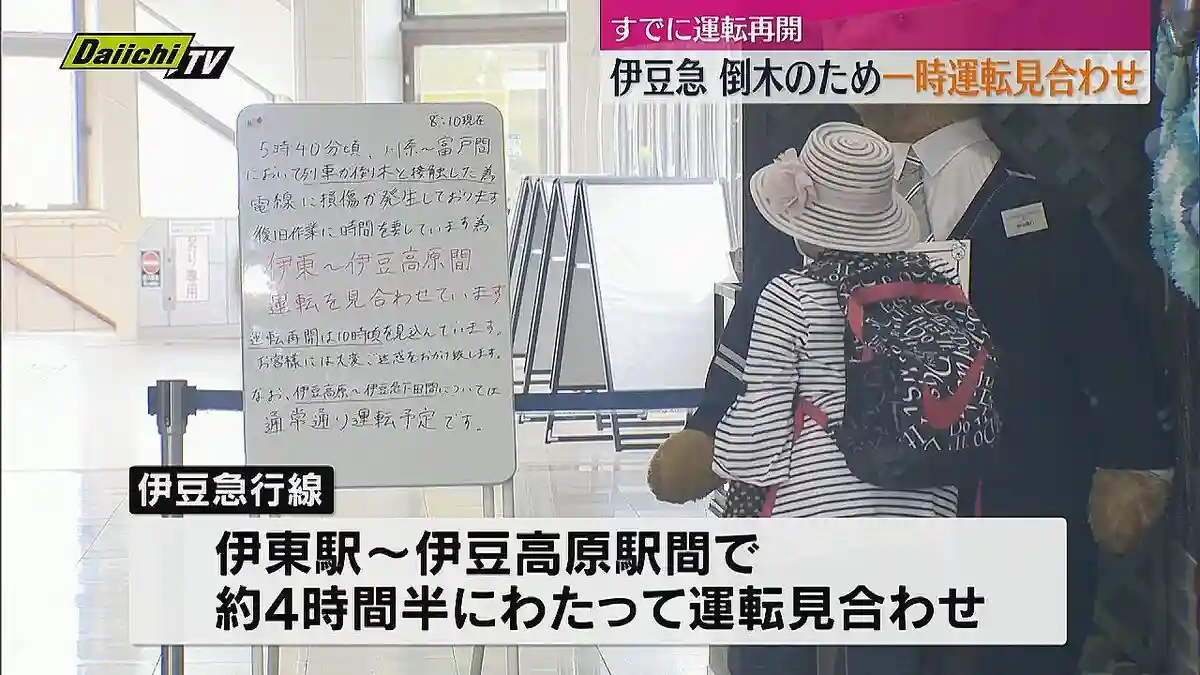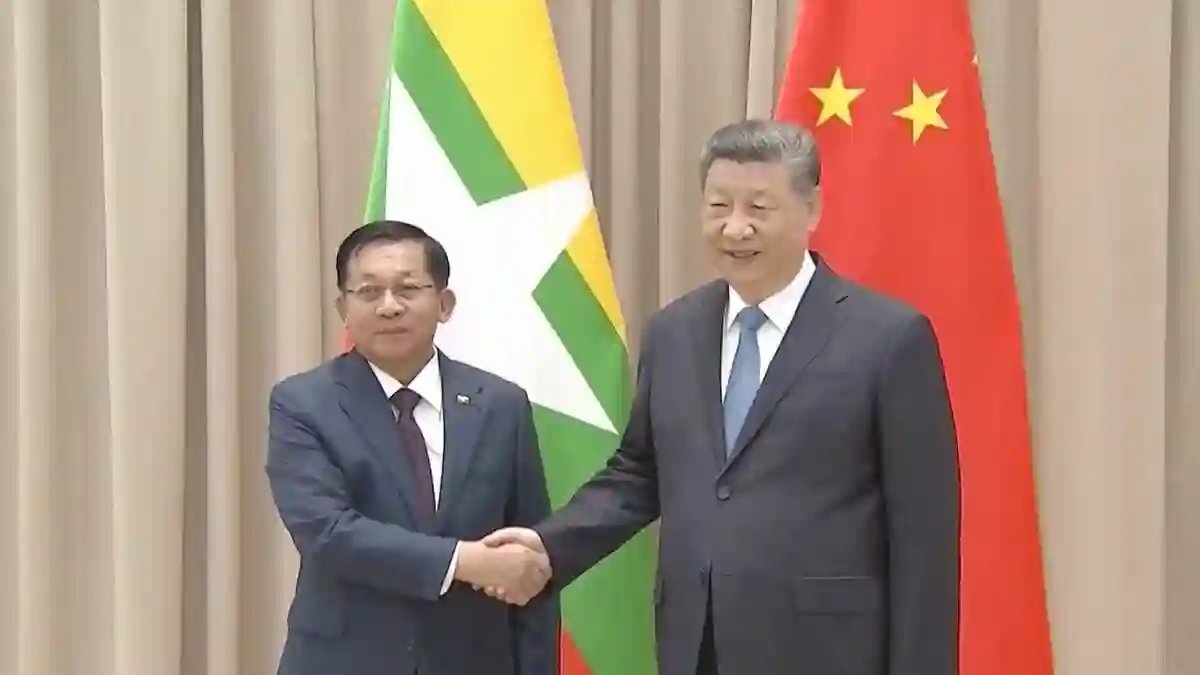暴力団は暴利を貪る犯罪組織の代表格と言われて久しい。そんな暴力団であっても、ヤクザ渡世に起源を持つことから、組には一定の規律や綱領のようなものがある。それに反した者は重ければ絶縁、一般的には破門といった追放処分が科されることが習わしとなっている。【藤原良/作家・ノンフィクションライター】 *** 【写真11枚】露出度の高い“挑発的なドレス”をまとうマニラの「美人ホステス」 トクリュウ犯罪を世に知らしめた「ルフィ」が豪遊したパブでの実際の写真をみる それらしく言えば「掟に背く者は追放されるのがしきたり」なのだ。 処分される者に立場は関係なく、直系組長や幹部、ベテランであっても掟に背けば例外なく処分される。だが実のところ、処分を決定する掟、つまり“判断基準”は曖昧だ。 破門覚悟で詐欺に手を染める者も(写真はイメージです) 法律や判例に基づいて判決を下す裁判とは異なり、暴力団は問題視された事案に関する事情や原因などを「組長個人の裁量」で勘案して処分を決定するからだ。(一部の役職者は執行部会で処分を決定する)。そのため同じ事案であっても同じ処分となるわけではない。 規約や破門の条項を会則のような形で紙に明記し、あらかじめ組員に周知する組もないではない。だが、ほとんどの組では口頭で何となく言い伝えているというケースが一般的だろう。 要するに「その時々の組長の判断によって、あちらの組では破門にされても、こちらの組では許される」という感じだ。これで組員が組を移籍する原因につながることも珍しくない。 例えば、ある組では組員が覚醒剤を扱えば破門と定めている。だが別の組では覚醒剤はお咎めナシだったりもする。どの暴力団にも共通する“ヤクザの掟”は存在しないと言ってもいい。 とはいえ、どんな業界にも「業界の常識」、「業界のイロハ」、「業界共通の筋道」といった慣例や習慣があるものだ。それと同様、“暴力団業界”にもヤクザ渡世に端を発する古いルールのようなものが存在する。 「詐欺は破門」の伝統 有名なものに「ヤクザは盗人の上で、乞食の下」がある。ヤクザは乞食より格下だが、絶対に盗みには関与しないという信条を示した口伝だ。だからこそ窃盗に手を出した組員は破門処分にされても仕方がない、ということになる。 「詐欺は破門」という口伝もある。昔からヤクザは、「カタギさんには迷惑をかけてはいけない」という信条を持つ。自分たちが詐欺の罪を犯さないだけでなく、口伝を拡大解釈して法律では裁けない悪質で巧妙な詐欺師を“退治”することも行われてきた。 詐欺罪に対するヤクザの厳しい姿勢は、多少なりとも暴力団にも引き継がれている面がある。ならば詐欺に関わった組員は破門になると解釈できるはずだ。 では昨今、社会問題化している特殊詐欺やトクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)に関与した組員の処分はどうなっているのか。 某組長は「うちでは詐欺全般、理由の如何を問わず破門」と言う。 2008年5月に施行された改正暴対法による「指定暴力団の代表者等の損害賠償責任」の拡大強化により、組員による特殊詐欺事件の損害賠償責任は団体トップにも及ぶようになった。 このため特殊詐欺の被害者は提訴などの法的手段で、暴力団の組長や会長に対して使用者責任を問い、被害請求を行えるようになったのだ。 “チェック機能”は存在しない 2021年には最高裁が指定暴力団のトップに賠償金の支払いを命令。さらに2023年には東京地裁で数千万円の賠償金を命じる判決が確定している。 「うちは判決が確定する前から、詐欺はダメにしている。昔からあったからね。詐欺の被害者から相談されたら、はっきり言って法律は関係なく、こっちのやり方で詐欺師を懲らしめた。それが俺たちの伝統的な役割なのに、俺たちが詐欺師と関わってしまったら、格好付かないどころか本末転倒でしょ」(同・某組長) しかし組員に対するチェック機能は存在しない。この組長は「組に秘密で個人プレーでやられたら、若衆(組員)が特殊詐欺やトクリュウに関わっていることが露見するまでは、処分のしようがない」と明かす。 別の組長も同様に「うちも破門ですけど、組員ひとりひとりがどんなシノギをやっているのか、全てを把握することは難しいですよ」と言う。 「みんなで集まった時に、『詐欺は破門だからな』と口頭で注意するぐらいしかないです。その上で、あとは若衆のことを信じるしかないですよ」 とは言え、特殊詐欺やトクリュウは秘密裏に行うことが肝だ。関与する組員が自分の正体を世の中に公開することは絶対にないだろう。詐欺が破門要件になっている組なら、わざわざ幹部に報告することもあり得ない。 特殊詐欺の犯人に同情する声も よって関与を秘密にしている組員は「組への裏切り」を自覚しているだろう。裏切りに対する組の処分や制裁も充分覚悟した上でのことなのだろう。そこまでしても一時の暴利を貪りたいのだ。 警察庁によると、2023年の特殊詐欺検挙人数は2455人。このうち暴力団構成員などは439人で全体の5分の1から6分の1程度となっている。統計からは非暴力団員による犯行が圧倒的に多いことが浮かび上がる。 しかし、ある組幹部は「やっぱり、やる奴はやるでしょう。破門覚悟で。今はもう、こういうのしかないって思って、組に内緒にして勝手に特殊詐欺をやっちゃうんでしょう」と、ため息交じりで言う。 「一般の人たちも今はどの業界でも大変でしょう。働いても働いても稼ぎにならない。特に若い人なんかは社会に夢を持てないんじゃないですか。カネが全てとは言いませんが、稼げない世の中で借金でも抱えたら嫌気がさしてきて、『もう闇バイトや特殊詐欺をやるしかない』ってなっちゃうんじゃないですかね。他に稼ぎ口がないですから。それで捕まって懲役に行って、数年後に刑務所から出て来たら、ブランクが足かせになって行く所がなくて、俺たちのところに入って来る。けど、こっちでも稼げないからまた特殊詐欺をやって、破門になって弾き出されたら、そういう人はどこに行けばいいんですかね?」 詐欺を許す組も 別の組幹部は「ヤクザってのは社会最下層の住人です。けど、最近の社会はヤクザの下というか、ヤクザも務まらないような感覚を持った若者を作り出してるような気がしますよ」と嘆く。 国としては特殊詐欺やトクリュウに対する取り締まりを強化するだけではなく、行き場を失ったり、貧困にあえいだりする若者に対して何らかの救済措置を講じる必要があるのかもしれない。 そして特殊詐欺やトクリュウは、“暴力団業界”の中でも注目度が高まっている。ある組の幹部は「確かに詐欺に関連する行為は昔なら破門でした。それが当代(現在の組長)になってからは変わりましたよ」と言う。 この組では現在、破門要件に詐欺は入っていないという。先述した通り、処分の判断は組長の裁量が大きい。昨今、暴力団の活動に対する締め付けが厳しいことから、この組では組織維持のため、いわゆる“シノギの枠”を広げたそうである。つまり、詐欺OK。 組長が「やれ」と指示まではしないが、「見て見ぬ振りをする」というサジ加減のようだ。ただし、「あまりに詐欺の内容が問題だと、場合によっては破門になる可能性もゼロではない」と組の幹部は付け加えた。 掟を再考する必要性 組織維持のため詐欺を許すようなやり方を選ぶからこそ、いつまでも「暴力団は犯罪者集団」、「反社会的組織」と批判されるのかもしれない。 一方の暴力団は詐欺を許容することで、“行き場がなくなった人々”の新たな受け皿となる可能性なきにしもあらず、と自分たちを弁護するのだろうか。 いずれにしても時代の変化が、暴力団の性格に大きな影響を与えるようになってきた。破門ですら時代の影響を受けている。 しかし、仮にも暴力団がヤクザ渡世に起源を持ち、破門というものが“掟”と表裏一体であるならば、社会潮流に左右されることなく伝統を貫いてほしい。 よく組長の命令は絶対だと言われるが、それは自由の存在しない主従関係や奴隷制度のような絶対的支配を意味しているのではない。 組長の命令は“掟”から発せられているから絶対なのだ。暴力団は今一度、「破門とは何か?」、「掟とは何か?」と自問自答すべきではないだろうか。 藤原良(ふじわら・りょう) 作家・ノンフィクションライター。週刊誌や月刊誌等で、マンガ原作やアウトロー記事を多数執筆。万物斉同の精神で取材や執筆にあたり、主にアウトロー分野のライターとして定評がある。著書に『山口組対山口組』、『M資金 欲望の地下資産』、『山口組東京進出第一号 「西」からひとりで来た男』(以上、太田出版)など。 デイリー新潮編集部