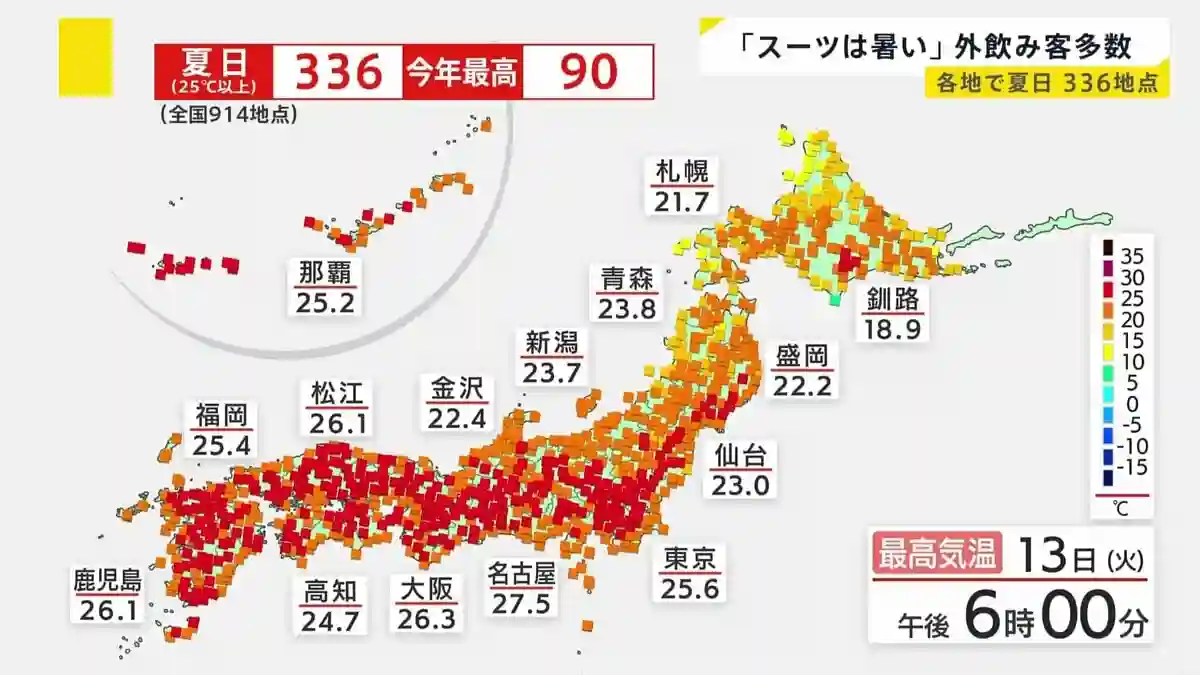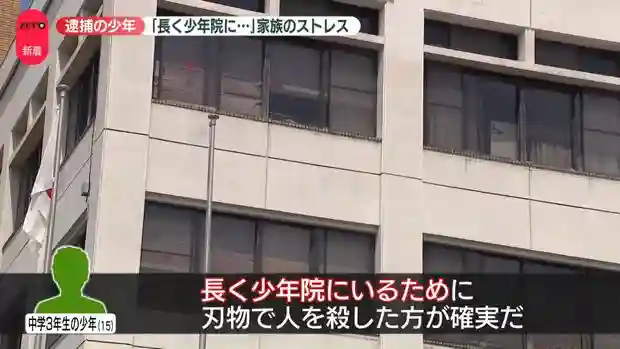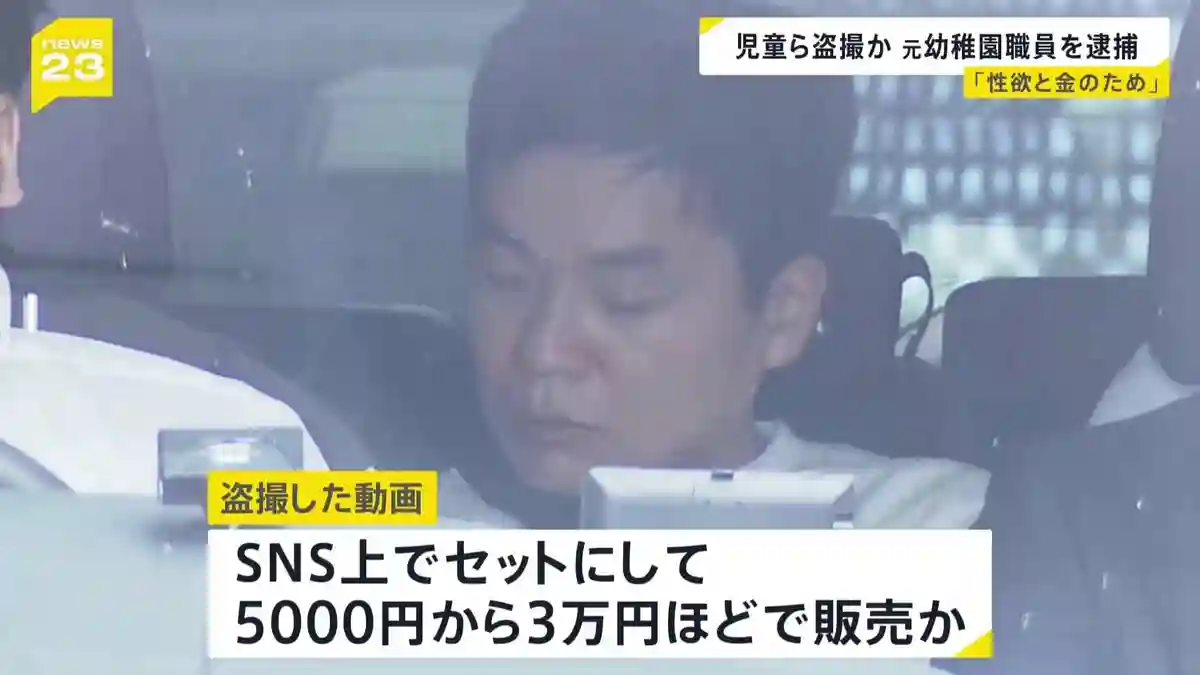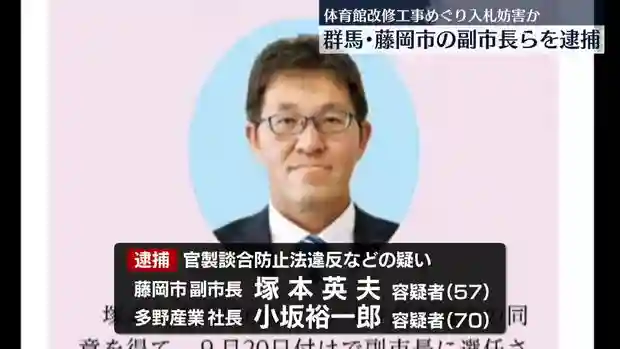週刊新潮の1990年10月11日号に「特集『住友銀行』『伊藤萬』心中未遂の後始末」との記事が掲載されると、たちまち大きな反響が巻き起こった。約3000億円が裏社会に流れたとされ、今でも「戦後最大の経済事件」と呼ばれるイトマン事件──この問題に関する、かなり早い段階での詳報だったからだ。(全2回の第1回) *** 【写真】ともに住友銀行(現・(現・三井住友銀行)の頭取として、イトマン事件で闇勢力と対峙した、巽外夫氏(1923年〜2021年)と西川善文氏(1938年〜2020年) 特集記事のリードは短い字数にもかかわらず、見事に事件の本質を伝えている。ご紹介しよう。 《『伊藤萬』と『住友銀行』が揺れている。ご存じ関西の老舗商社とその主力銀行にして業界トップの利益を誇る名門都銀である。ここ数年、過大な不動産投資を繰り返してきた伊藤萬は、昨年来の高金利と不動産融資規制で経営悪化が表面化。グループ全体で実に一兆円に及ぶ債務を抱えているという。内部からは大蔵省宛に告発文書が飛び出したり、同社の筆頭常務をめぐる手形騒動が持ち上がるなどテンヤワンヤ。その再建をめぐっては住銀上層部の意見対立も噂され始めた。伊藤萬は住銀にとって“第二の安宅”となるのか》 リードの《手形騒動》に注目していただきたいのだが、その話を進める前に、結びの《第二の安宅》の意味が分からないという人も最近は増えてきたのではないか。 バブル時代を象徴する事件だった(写真はイメージです) これはカナダにおける石油精製プロジェクトの失敗により、名門商社だった安宅産業が1975年に経営破綻したことを指す。安宅のメインバンクも住友銀行であり、イトマン事件に匹敵する大きな経済ニュースだった。 話をイトマン事件に戻すと、この未曾有の経済事件に関する報道では「手形」という単語が頻出した。 異常な680億円の絵画取引 大阪で起きた“手形騒動”に関する《関西のある金融筋》の生々しい証言を、週刊新潮の特集記事から引用する。 《「大阪の裏金融では、今、伊藤萬が振り出した手形の話題で持切りですよ。五億円、六億円、十億円の三種類の手形で、都合、百四十億円もの手形が伊藤萬から振り出されているんですが、不思議なことに、それの受取り先が、関西新聞というこちらのちっぽけな夕刊新聞でしてね」》 《「伊藤萬ほどの一流企業ならもちろん一枚百億円の額面であろうと(手形を)振り出す資格はありますが、問題は受け取る側の能力でね。もし、それが一流企業なら、普通の銀行で割り引いて現金にするなり、取引先に回したりして何の問題もなく手形は流れていく。が、今回は振り出し早早、この信用ある手形の一部が“街金融”に割引きに出されたり、その手形のコピーが、裏金融に一斉に流出したり、一体どうなってんのか、って感じなんですよ。関西新聞は大手の百貨店から実際にこの手形で絵を購入しているようなんですが、全く不思議としか言いようがない」》 イトマン事件で最初に浮上したのが、総額680億円に及ぶ巨額の絵画取引だった。現在では不正に価格を釣り上げたことが明らかになっており、事件の関係者を大阪地検特捜部が特別背任容疑で逮捕する“突破口”となった。 手形不渡りで強制捜査 手形の動きが《全く不思議》という関係者の勘は当たっていた。巨額の絵画取引に使われた手形が不渡りとなり、大阪地検特捜部が強制捜査に踏み切るきっかけになったのだ。 週刊新潮は1991年4月25日号のMONEY欄で「『疑惑の絵画』不渡り騒動でイトマン事件の『終着駅』」とのタイトルで詳細を報じた。 ここで細かな話で恐縮なのだが、伊藤萬は1991年1月にイトマンに商号を変更した。そのため、これからはイトマンと表記する。 週刊新潮は《絵画に不動産にゴルフ会員権と、およそバブルそのものに巨額の疑惑融資ばかりしてきた》と、まずはイトマンの乱脈経営がどれほど悪質だったか指摘した。 記事は絵画の巨額取引を巡り、事件の中心人物が絵の購入代金をイトマンに返済する必要があると説明。分割での返済が決まり、中心人物とイトマンは覚書を交わした。 だが、その金額には驚かされる。4月10日に1回目として100億円を支払い、その後は4月20日、8月、9月の3回に100億円ずつ支払う。最後は12月に金利を含めて225億円を払う──。 こんな返済が本当に可能なのかと疑う人も多いだろう。 案の定、1回目の100億円さえ返済されることはなかった。事件の中心人物と関西新聞社など関係会社3社が保証した関西新聞の手形が不渡りになったからだ。 50億円の小切手 大阪地検特捜部が動いたことで、「イトマンの不正取引」は刑事事件となった。新聞各紙が特捜部の動きを追う中、読売新聞は大阪版に記事を掲載し、不渡りが確定した瞬間、“現場”で何が起きたのかを伝えた。 これがなかなか興味深い。そして、この記事では「小切手」が登場する(註1)。読売新聞の記事から該当部分を引用させていただこう。 《大阪市北区の関西新聞本社。同新聞振り出しの百億円の手形の決済資金が銀行の窓口が閉まる午後三時になっても、口座に入金されず、詰めかけた報道陣に、専務と営業局長(引用註:記事ではいずれも実名)は、あっさりと手形が不渡りになった事実を認め、準備していたワープロ打ちの声明文を淡々と読み上げた》 《決済前日の九日午後、弁護士が五十億円の保証小切手をイトマンに持参、一回目の返済金百億円のうち残り五十億円の支払いの猶予か代物弁済を要請。深夜までやりとりが続いたが、イトマン側に拒否され、この日朝から金策に走っていた。最近まで「二百億円程度は調達のメドがついた」と周囲に報告していたが、資産の株や不動産の売却が予定通りに進まなかったという》 昭和生まれなら、手形や小切手を巡る大騒動を体験した方もいるに違いない。だが、こんなことが起きることは、もう二度となさそうだ。 手形・小切手廃止の衝撃 全国銀行協会は3月26日、手形や小切手の決済システム「電子交換所」の運用を2026年度末で終了すると発表した。 読売新聞は終了を報じた記事で《明治以来続いてきた制度に終止符が打たれる》と報じた(註2)。確かにその通りだ。金融史における大きな転換点と指摘しても大げさではないだろう。 手形も小切手も非常に長い歴史を持つ。日本では1882(明治15)年に太政官布告「為替手形約束手形条例」が制定・公布され、近代的な手形と小切手が商取引に使われることになった。まさに文明開化の一環だったのだ。 1932(昭和7)年に手形法が、翌33(昭和8)年に小切手法が整備され、現在の制度が確立した。担当記者が言う。 「手形も小切手も共に現金の代わりとして決済に使える有価証券です。2億円の土地を購入する際、1万円札をケースに詰めて不動産業者に渡すのは重くて大変ですし、盗難も不安です。しかも長い金融の歴史を見れば、電子決済の実現は“つい昨日のこと”です。三井銀行(現・三井住友銀行)が世界初のオンライン・バンキングを稼働させたのは1965(昭和40)年のことでした。明治、大正、昭和の人々が現金ではなく手形や小切手で決済を行っていたのは非常に合理的だったのです」 第2回【ピーク時の交換高は「4797兆円」…手形・小切手の廃止に専門家は「経営者の矜持が失われないか」「手形詐欺は犯人にも高度な知識が必要だった」】では、なぜ国や金融機関は手形や小切手の実質廃止を経済界に求めたのか、なぜ専門家は廃止に懸念を示すのか、について詳しくお伝えする──。 註1:100億円不渡り 巨額の“許氏資金”どこへ イトマン絵画疑惑急展開(読売新聞大阪版朝刊:1991年4月11日) 註2:手形・小切手は26年度末で全廃、電子交換所が終了へ…手形は「下請けいじめの温床」の指摘も(読売新聞オンライン:3月23日) デイリー新潮編集部