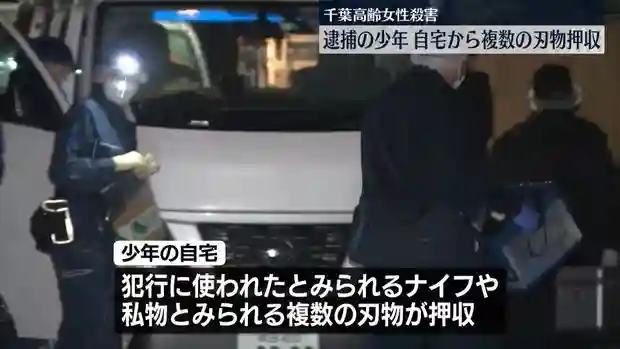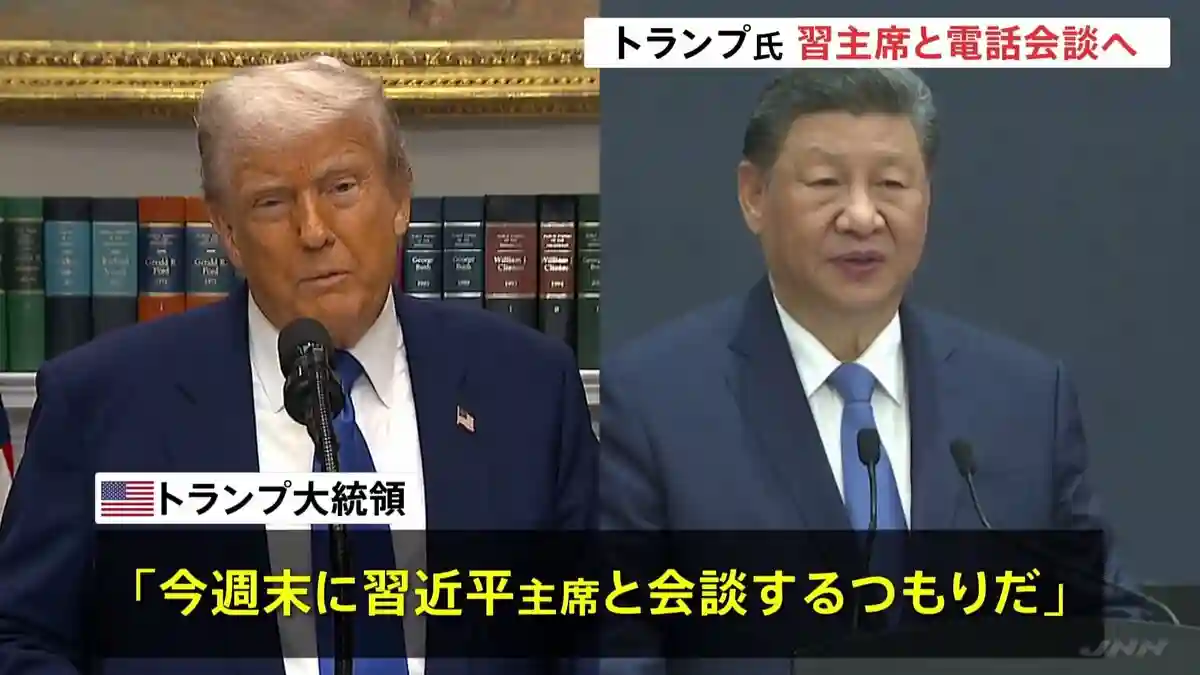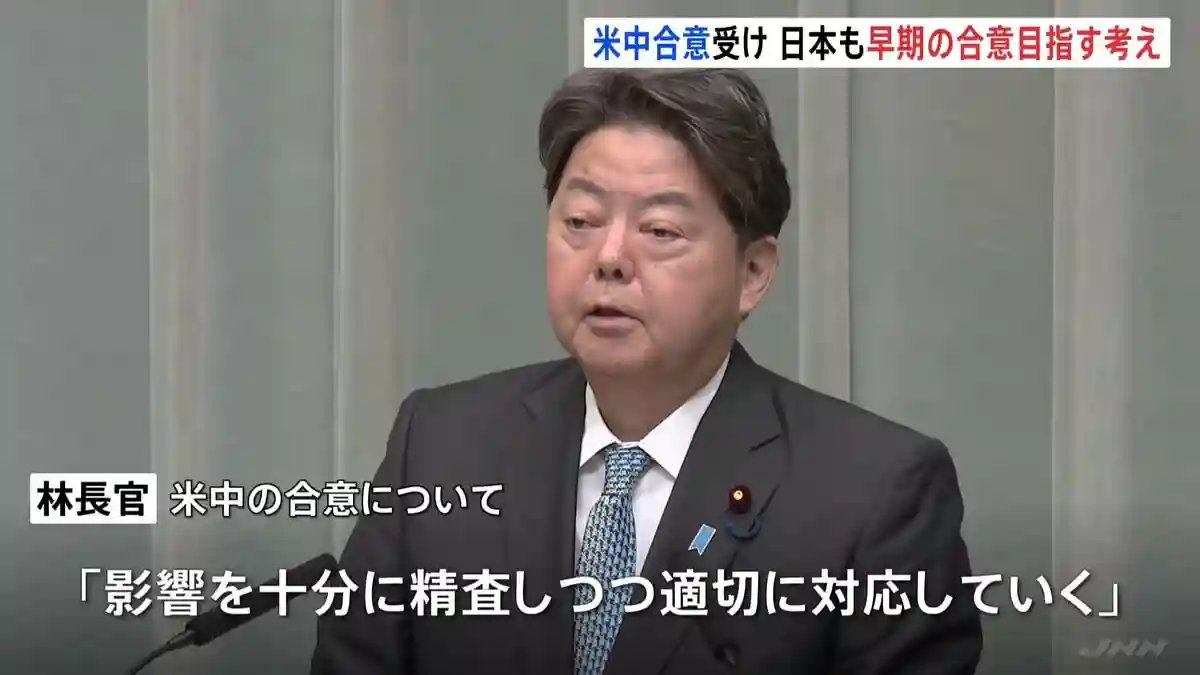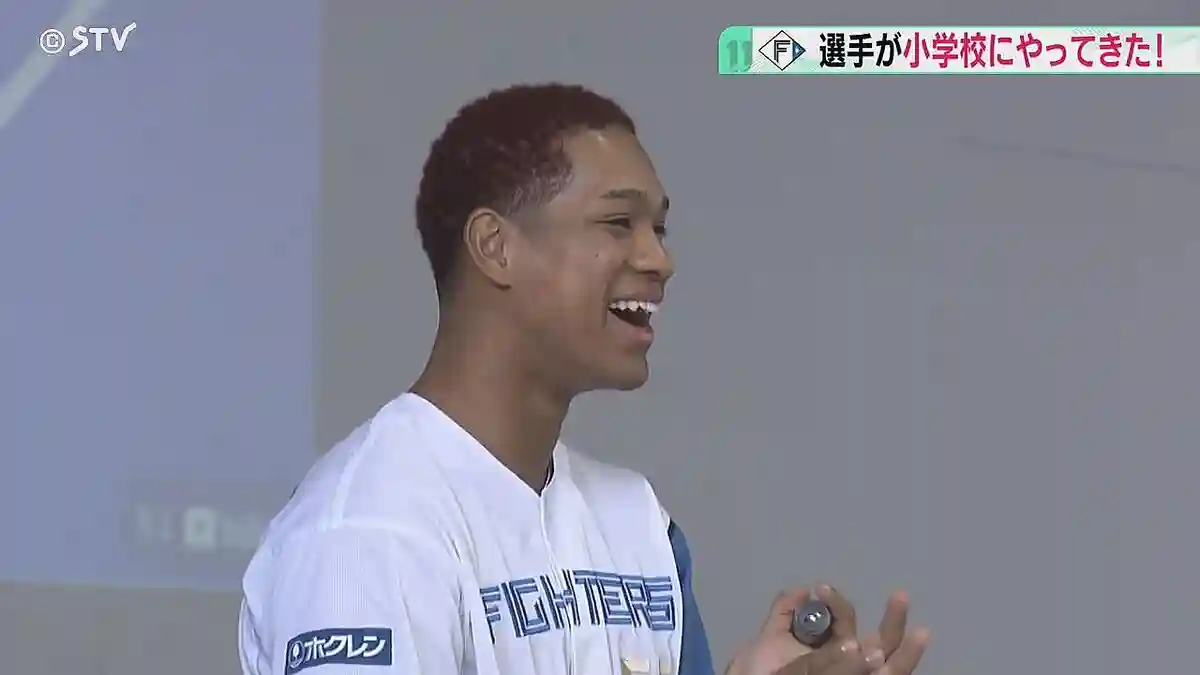遠い地域の文化がなぜ似ているのか、これは文化人類学における究極的な謎の一つである。百年以上にわたり、文化人類学者たちは諸地域の文化を記述し、それらの間にある構造的なパターンを見出してきた。筆者は、よく似た文化が生まれるのは、人間が社会を作る限りにおいていつでも成り立つ、「文化を生む仕組み」があるからだと考えている。本連載では、数理モデルのシミュレーションによって、人間文化に普遍的な構造を生む仕組みを探求する普遍人類学の試みを紹介する。 人類に普遍的な「贈与」が及ぼす力 飲みの席などで見栄を張って多めに支払う人は金銭的には損をしているが、それによって周りから尊敬を得られるのであれば、そうした振る舞いも報われる。 文化人類学では、これと似たような、一見して経済的に損な行為によって名声を得る慣習が多く知られている。これを「贈与」と呼ぶ。興味深いのは、この贈与を大規模かつ儀式的に行う慣習が、ネイティブアメリカンの社会やパプア・ニューギニアの社会など、遠く離れた地域の社会に共通して見られることだ。これらはまさに人間文化の普遍性を示している。 中でも、ネイティブアメリカンの「ポトラッチ」などのように、人前でモノを与えることで「お返しする義務」を押し付け、その義務を果たせなかった者が脱落していくような覇権争いの慣習を「競覇的な贈与」と呼ぶ(図1)。 以前の記事では、これを数理モデルで表現した。その結果、競覇的な贈与が繰り返されるにつれて、社会にまず富の格差が生まれ、その後で名声の格差が生まれることがわかった。 さらに、集団内の格差の有無を判定するためには、富の「分布の形状」を調べることが重要だと論じた。 分布とは、数量の値と頻度の関係(例えば年収がいくらの人が全体の何%であるかという関係)を示すものであり、それを図示したものが分布の形状である。分布の形状はそれが生まれるメカニズムを反映していて、ランダムなやりとりをするときには「指数分布」、「富める者ほどますます富む」という仕組みが働く場合だと格差が著しい「べき分布」が生まれるのであった。 今回の記事では、競覇的な贈与によって、社会がランダムネスに支配された状態と、「富める者ほどますます富む」という仕組みが働いた状態の間を移り変わることを、数理モデルによって示す。 最後に、人類学上の観察事実を紹介しながら、現実に贈与のやりとりが状況に応じてランダムネスをもたらしたり、格差を強めたりすることを明らかにする。 社会構造に影響する「贈与の頻度」と「利率」 以前導入した、競覇的な贈与の数理モデルの設定は以下の通りであった。 ・100人の人がいて、 ・各ステップで人々は以下の三つの行動をする。(1)から(3)までを順に行うことを「1ステップ」という。 (1)自分以外の誰かを選んで自分の富を贈与する。 (2)全員が一定量の富を生産する。 (3)最初にもらった富に一定の割合(rとおく)の利子をつけてお返しする。 ・お返しするときに十分な富を持っていなければ負債が発生する。 ・負債を抱えさせるほどの大規模な贈与をした者は名声を獲得する。 今回の分析ではこれらに加えて、プレイヤーたちが経験できるステップの数の効果を考えてみよう。人間には寿命があるので一生のうちにできる贈与の数は限られている。さらにその回数は何を交換するのか、そして交換できるものをどれだけ持っているのかにも依存する。この違いは贈与が引き起こす社会変化にどのような違いをもたらすのだろうか? そこで、贈与の頻度を表すパラメータℓを導入する。具体的には、各ステップの終了時点で確率1/ℓで人々は死に、次世代のプレイヤーに交代するとする。ここで、確率1/ℓで死ぬということは人々は平均してℓステップの間生きる、つまり一生の間に平均してℓ回の贈与をする、ということである。 さて、以前のモデルでは人々が死ぬことがないので、シミュレーションを繰り返していくにつれて、人々の富の総量は際限なく増大し、富と名声の格差はますます拡大していった。しかし、今回のモデルでは、寿命によってモデルから退場する人がいる。その結果、各ステップで新たに生み出される富や名声と、死んで失われる富や名声がつりあって、富と名声の分布は一定の形状に落ち着く。 (図2)贈与の頻度ℓとお返しに必要な利率rを変えたときの富と名声の分布の形状の変化(矢印はrやℓを大きくしたときの分布の変化の方向を表している)。 シミュレーションの結果、富と名声の分布の形状はお返し時の利率rと贈与の頻度ℓという二つのパラメータに依存して変化した(図1)。図は富と名声について、ある値(x軸)を持つ人がどれだけの頻度(y軸)で存在するかを示している。 rやℓを大きくすると、莫大な富や名声を持つ人が出現する(図の線が右側に移動する)。この変化は指数分布からべき分布への変化に対応する。ただし、名声についてはrやℓが極端に大きくなると、線は左側に戻り指数分布が現れる。 (1)まず、rやℓが小さいとき、つまり、贈与がまれにしか起こらずしかも利率も小さいときには、富も名声も指数分布に従っていた。これはつまり、富と名声の変動がランダムネスに支配されているということである。 たまたま長生きすれば多く稼いで豊かになるし、逆にたまたま多くの人から贈与されればたくさんの利子を支払う必要があるので貧しくなる。このように、今のモデルにはランダムネスが存在する。富の分布が指数分布であるとは、このようなランダムネスのみによって引き起こされる程度の富のばらつきしかないということを意味する。 そして、この場合には、ある時点で裕福な人であっても、たまたま多くの人から贈与されればすぐに貧しくなってしまう。 今回は、この程度の違いについては格差とはみなさないという立場をとる。分布が指数分布に従う限り、一時的に裕福な人や貧しい人の間の違いができたとしても、それらの違いはわずかであり、また時間が経てば失われることが多いからだ。 贈与の頻度と利率が増えると格差が生まれる (2)だんだんrやℓを大きくすると、つまり贈与が頻繁になったりお返しに求められる利率が大きくなったりすると、あるところで急に富の分布がべき分布に変わった。これはつまり、「富める者ほどますます富む」仕組みが働いたということである。 豊かな人は贈与をすることで、たくさんの利子をもらうことができ、ますます豊かになる。先ほどの(1)のように利子率rが小さいときには、多少の利子を稼げたとしても、たまたまたくさんの人から贈与されてその分多くの人に利子を支払うようなことがあればそんな稼ぎは吹き飛んでしまう。 しかし、rが十分に大きいと、豊かな人は安定して多くの稼ぎを得ることになり、たまたま支払いが増えたくらいでは貧しくならない。このとき、富裕な人ほどより多く稼げるようになり、ランダムネスよりも「富める者ほどますます富む」仕組みが優位になって、急速に富の違いが拡大してべき分布が生まれるのである。 ここで生まれた豊かさの違いは、先ほどとは違って簡単にはひっくり返らないものである。そこで、本記事では分布がべき分布に従って、平均的な人よりも何倍も豊かな人が現れ、しかもその差が固定的である場合を、「格差がある」と表現する。 (3)そこからさらにrやℓを大きくすると、名声の分布もべき分布に変わった。これは名声についても、「富める者ほどますます富む」仕組みが働いたということである。 この変化は富の格差がますます大きくなることで、経済的に豊かな人が受取人に負債を抱えさせるような贈与をできるようになったときに起きる。経済的に豊かな人ほど相手に負債を押し付けやすいので、「(経済的に)富める者ほどますます(社会的に)富む」という仕組みにより、名声のべき分布が生まれる。 ここでポイントとなるのは、贈与が富の格差を身分の格差に「埋め込む」ものだということだ。逆に言えば、(贈与以外に格差をもたらすものがない場合)身分の格差だけがあって富の格差がない状態はありえないということができる。 (4)面白いことに、そこからさらにrやℓを大きくすると、名声(身分)の分布は指数分布に戻る。これはつまり、名声の変化についてはまたランダムネスが支配するようになったということである。 実はこのとき、富の格差が著しく大きくなっていて、一番富裕な人から贈与されればほとんどの人はお返ししきれず、負債を抱えてしまう。すると、ほとんどの人にとっては「いつ一番豊かな人から贈与されるか?」だけが問題になる。ここで一番豊かな人が誰に贈与するかはランダムに決まっているので、ほとんどの人の挙動はそのランダムネスに支配され、指数分布が生まれるのである。 ただし、ここで、一番富裕な人自身は指数分布の法則に支配される謂れはない。実際のシミュレーション結果はその通りで、一番富裕な人だけは指数分布の外にいるような振る舞いを示す。これはあたかも、王様が民衆や貴族の活動を抑制しつつ、自分だけは圧倒的に豊かになったような状況に対応している。 このように一つのモデルであっても、パラメータが変わると挙動が全く違ったものになる。ここで重要なのは、同じ贈与の相互作用が「たまたま多くの人から贈与されてしまって利子の支払いが増える」というランダムネスと、「豊かな人がたくさんの利子をもらってますます豊かになる」という「富める者ほどますます富む」仕組みの両方をもたらしうるものだということである。 そして、これらの仕組みのどちらが強く働くかがお返し時の利率rと贈与の頻度ℓに依存して変わり、それによって社会レベルでの富や名声のばらつきの程度に違いが出る。 つまり、rやℓが小さい場合には、ランダムネスが優位に働いて「あるときにはAさんが豊かになり次にはBさんが豊かになる」というような流動性をもたらすのに対し、rやℓが十分に大きくなると「富める者ほどますます富む」仕組みをもたらして、豊かな者の地位を固定化させていくのである。 贈与によって形成される多様な社会構造 贈与のやり取りがランダムネスをもたらすか、格差を固定化させるか。実際の社会では、どのような状況が見られるのだろうか。 まずは狩猟採集社会に例を見てみよう。多くの狩猟採集社会において、獲物を周囲の人に分け与える慣習がある。 狩りが成功するかは(もちろん上手い下手はあるとはいえ、基本的には)運次第だ。たまたま獲物を得た人が周りに贈与する限り、一時的にもらってばかりになる人やあげてばかりになる人がいても、そうしたばらつきはいずれ解消される。 しかし、近年ではそうした狩猟採集民の社会においても格差が生まれ始めている。近代的な技術が普及し始めたからだ。近代技術を持っているかどうかによって明確に狩りの成功率が変わってしまうのだ。 イヌイット社会では古くから、犬ぞりと銛によって狩りを行っていた。それが20世紀中頃になると、近代化に伴ってモーターボートやライフル銃を用いた狩りが普及して、狩りの効率が急激に向上した。しかし、こうした高価な機材は誰にでも持てるものではない。狩り以外の収入源を持つ者のみがこうした機材を保持し、それによって狩りでも成果を上げるようになった。 イヌイット社会においては、獲物を皆に分配する平等主義的な価値観があるので、高価な機材を持たない人も狩りの恩恵に預かってはいる。しかし、一方で、「あげてばかりの人」と「もらってばかりの人」の二極化が進み、政治的な判断などの場においては、「あげてばかりの人」の発言力が大きくなるというような名声の度合いの違いが生まれ始めているようである(N. Kishigami “Contemporary Inuit Food Sharing and Hunter Support Program of Nunavik, Canada” Senri ethnological studies 53 (2000))。 すなわち、近年のイヌイット社会で起きているのは「(狩り以外で)富める者ほどますます(狩りでも)富み、狩りでの成功度合いの格差が政治的な発言力の格差に埋め込まれる」というプロセスである。 また、パプア・ニューギニア近くのトロブリアンド諸島の社会では、毎年最初に収穫されたイモを首長に贈り、残りの収穫のほとんどを姉妹や姪とその夫たちに贈るという習慣がある。これらは日頃受けている恩への返礼としての贈与である。 この場合でも、どこで雨が多く降ったかなどによって、たまたま多く収穫する人とそうでない人が出てくる。それでも、次の収穫期には別の人が多く収穫するかもしれない。そのため、親族間での贈与においては、誰が多く贈与するのかはランダムネスによるところが多い。しかし、首長は別である。皆が首長に向かって贈与するので、この贈与は富の格差を固定化している。 ところで、先ほどのモデルでは、名声が高い人とは、たくさん贈与をする人であった。これを踏まえると、首長はたくさん贈与されているのだから名声が低いのではないか?と思う人もいるかもしれない。しかし、ここで注目すべきは、首長への贈与は実は返礼であって、人々が首長に対していわば「負債」を抱えているから行われているということだ。そのため、首長がたくさんの贈り物をもらうのはむしろ、それだけの負債を抱えさせた首長の名声の大きさを示しているのである。 最後に一つ日本の例を挙げる。鎌倉時代の武士は御恩と奉公という論理で将軍のために尽くした。武士たちは、将軍によって所領を安堵(領地の支配を保障)されているので、その恩へのお返しとして、将軍のために戦ったのであった。 将軍への奉公も、首長への贈与と同じく、すでに受けている恩に対するお返しである。首長や将軍から受けている恩はとても大きいので、長期間かけてお返しされる。(今のモデルでいうところの負債に対する返礼である)。 そしてその結果、富める人ほどますます富むという仕組みが働いて、富と名声の格差が固定化されていく。 贈与をしてお返しをする。それを通じて多くの恩を着せれば名声を獲得する。このシンプルなやり取りは人間社会に一般的であるが、それが形づくる社会構造は実に多様である。 続編『社会構造は「贈与の繰り返し」で変化する…物理学が提示した「人類の歴史」の新しいシナリオ』では、格差の程度と変化の視点から、社会構造をいくつかのタイプに分類する。そして、贈与に駆動されて社会構造が変化するという新しい歴史観を提示する。 【続きを読む】社会構造は「贈与の繰り返し」で変化する…物理学が提示した「人類の歴史」の新しいシナリオ