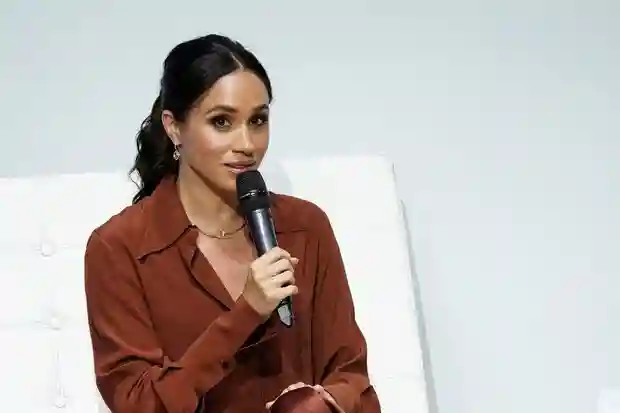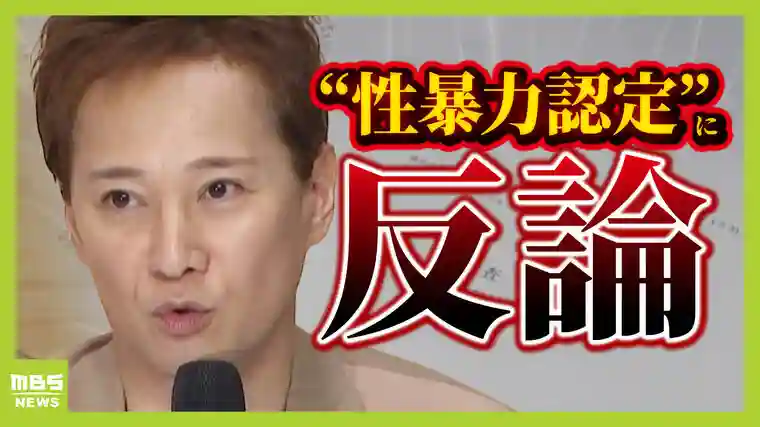人類は進化の過程で共感力を獲得し、言語を発達させてきた。そのなかで生まれたのが歌やダンス、演劇だった。そうして演劇は人と人とを繋ぐ芸術となっていった。戦争が止まらないこの時代にこそ私たちはもう一度立ち止り、人類の来し方に思いを馳せたい。群像にて連載中の『ことばと演劇』では、劇作家の平田オリザが演劇の起源に迫っている。 ※本記事は群像2025年6月号に掲載中の新連載『ことばと演劇』より抜粋したものです。前回の記事はこちらです。 「やることが毎年違う」という凄さ ここでもう一つ、人類史を考える上で重要なことがある。「対等に優劣を競う」という点が古代オリンピックの革新的な要素だったが、一方、それに加えて、ギリシャ悲劇が生み出した最大の進化は「祭りなのに、やることが毎年違う」という点だ。 こんなことは、どうやっても証明できないのだけれど、おそらくそれまで「○○祭り」と言われたもので毎年違うことを行うなどというものはなかったはずだ。祭りは神への奉納だから、取り立てて新しいことをする必要はない。巫女の踊りなどは毎年違ったのだろうが、それは意図してのものではない。盆踊りだって進化はするだろうが、その変化は目に見えにくいものだ。 しかしディオニソス大祭におけるギリシャ悲劇の上演は、それらと全く異なる。毎年、意図的に、私たちが現代で言うところの「新作」を上演するのだ。村祭りの対抗戦から発展したのだとしても、この変化は大きい。 では、この紀元前五三四年というのはどういう時期だったのだろう。 紀元前五五○年前後から、スパルタが力を持ちペロポネソス同盟を形成する。一方、アテナイは、ペイシストラトスによる僭主政治が行われ経済が飛躍的に発展していく。同時にこの時期には、タレスをはじめとする賢人らによって哲学の原型が生まれた。 そして紀元前五三四年、ギリシャ悲劇の誕生。 このころクレイステネスによる改革が行われ、アテナイの民主政の基礎が築かれる。 紀元前四九九年から、なんと五十年の長きにわたってペルシャとの戦争が始まる。 ペルシャ帝国との戦争は、まずアケメネス朝ペルシャ帝国の支配下にあったイオニア地方(現在のトルコの一部)のギリシャ系の小都市が、ペルシャの圧政に反発して反乱を起こした、いわば小競り合いから始まった。アテナイや他のいくつかの都市国家がこの反乱を支援したが、強力な軍事力を持つペルシア軍によって鎮圧される。 紀元前四九○年、ペルシャ王ダレイオス一世は、イオニアでの反乱を支援したアテナイとエレトリアへの報復としてギリシャ本土への遠征を決定した。ペルシャ軍はマラトンに上陸しアテナイ軍と衝突。当初、劣勢とみられていたアテナイ軍だが、得意の重装歩兵戦術を駆使してペルシャ軍を破った。この戦勝と、アテナイの防備をさらに固めよという知らせのための使者の逸話が、マラソン競技の由来になったことはよく知られる。 紀元前四八○年、ダレイオス一世のあとを継いだクセルクセス一世は、より大規模な遠征軍を率いてギリシャ本土への侵攻を開始した。ギリシャ諸都市はスパルタを中心とする連合軍を結成してペルシャ軍に対抗する。初期の戦いではギリシャ連合軍が敗れペルシャ軍はアテナイを占領、アクロポリスを破壊した。しかし、サラミスの海戦でギリシャ連合軍がペルシャ海軍を破り、戦況はギリシャ側に傾いていく。翌年のプラタイアの戦いでギリシャ連合軍がペルシャ陸軍を破り、ペルシャ軍は撤退した。 『ペルシャ人たち』の誕生 先のサラミスの海戦の勝利の要因は、アテナイ海軍の主力である三段櫂船の活躍だった。それまでの海戦は船を近づけて飛び移り船上で白兵戦を行うものが主流だった。しかし船首に堅い舳先を持つ三段櫂船は、高速で航行し、そのまま相手の軍船の横腹に体当たりして敵を沈没させるという画期的なものだった。 三段櫂船の漕ぎ手は、槍と盾と鎧を自前で調達できなかった下層市民、いわゆる無産階級だった。彼らは、サラミスの海戦の勝利に大きく貢献したため、凱旋後にその発言力を高めていく。 三段櫂船は有能な指揮官と、そしてその指示を伝達する指揮系統、さらには息の合った漕ぎ手の三者がいないと成立しない。これを統率したのがテミストクレス将軍だった。当時のギリシャでは、政治家と将軍は地続きで、優れた政治家が将軍に選ばれ軍隊の指揮を執った。おそらくテミストクレスは圧倒的に優れた統率力を持っていたのだろう。凱旋後、テミストクレスは無産階級の市民の支持を集めアテナイの民会を主導していく。 紀元前四七二年。サラミスの海戦の勝利から八年後、文献として残っている最古のギリシャ悲劇、アイスキュロスの『ペルシャ人たち』が生まれる。 物語の舞台はペルシャの首都スーサの王宮。報を待ちわびていた王妃や長老たちのところに伝令が到着し、サラミスの海戦でのペルシャ軍の壊滅的な敗北が伝えられる。この作品はギリシャ側の勝利を一方的に称えるものではなく、敗れたペルシャ側の視点から戦争を描いている点に特徴がある。それでもエドワード・サイード(一九三五─二〇〇三)はオリエンタリズムの端緒として、この『ペルシャ人たち』を挙げている。この点は次号に検討したいと思う。 一点、ここで書き留めておきたいことは、メディアとしての演劇の役割が、ここで完成した点だ。遠い戦場で何が起こっていたのか都市に残った市民たちは知りたがった。戦闘に自ら参加したアイスキュロスの本作は、さぞやアテナイ市民たちを熱狂させたことだろう。それはたとえば、火野葦平(一九〇七─一九六〇)の従軍小説『麦と兵隊』を、本国にいる日本兵の家族たちがむさぼり読んだように。 狩りから帰った父親が「今日、こんな大きなマンモスがいてさ」と伝えるところから始まった人類の「伝達」は、数万年の時を経て、ここまで様式化した。 なぜ人類は「近親相姦」をかたく禁じているのか…ひとりの天才学者が考えついた「納得の理由」