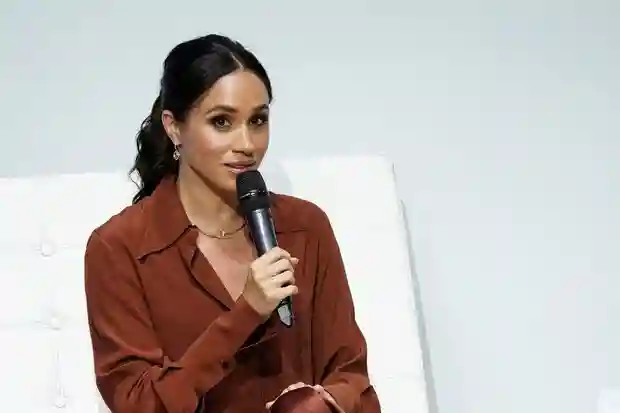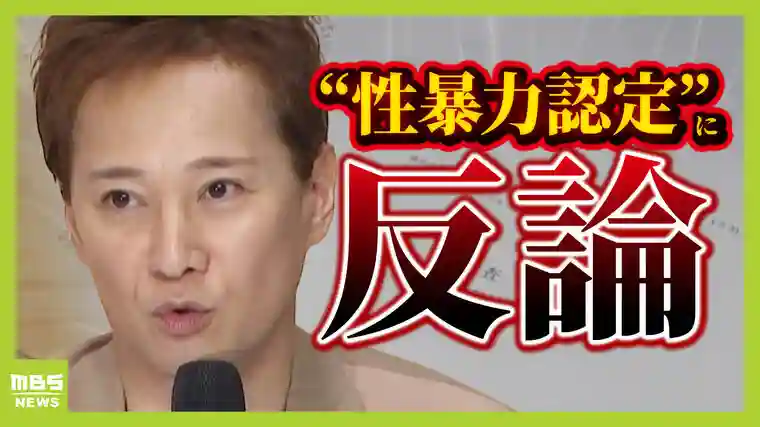追い詰められる中国 「今後90日間、中国への関税を145%から30%に引き下げる」 米国のベッセント財務長官がこう発表した5月12日、NYダウ平均は一日で1160ドルも上昇した。翌朝の日経平均も高値で推移したが、前編『米中関税戦争停戦で「オルカン」も「日本株」も爆騰へ…!でも、油断できない「中国25年前の裏切り」、そのヤバすぎる前科』でお伝えしてきたように、停戦に至ったからといって、米中関係の緊張は続くとみておくべきだろう。 中国が米国の求める市場開放に応じるとは到底思えないし、ましてや、中国には2001年にWTOに加盟した際に「自国市場を開放する」と約束したが、現在に至るまでこれを履行していない。 それでも、今回の米中協議が実現した背景には中国側の苦しい台所事情がある。中国経済が米国の高関税の重荷に耐えきれなくなっているからだ。 高学歴エリートに「農村移住」を奨励 中国の4月の対米輸出額は前年に比べて21%減少。4月の製造業担当者景気指数(PMI)は前月に比べて1.5ポイント低下し、3ヵ月ぶりに好不況の境目である50を下回っている。海外からの新規受注を示す指数は大幅に低下して44.7である。この水準は、新型コロナウイルスの感染が広がり経済活動が停滞した2022年12月と同じ低さだ。 中国の雇用環境がさらに悪化することも確実だ。 今年の大卒・大学院卒予定者は約1220万人に上ると言われており、若年層の失業率が下がることはありえないだろう。 未曾有の雇用難に際し、習近平国家主席は4日の青年節のメッセージで「若者は農村に行くべきだ」と訴えかけた。 中国では若者が故郷に戻って起業することを奨励する報道がさかんになっている。国営新華社通信は「故郷に帰るか農村に移住して起業した都市部の大卒者らの数は1200万人を超えた」と成果をアピールしているが、専門家は「眉唾だ」と切り捨てている。 「独裁に反対せよ!」 習氏の呼びかけで想起されるのは、1968年から約10年間続いた「下放(若者の農村での従事)」運動だ。当時も都市部の就職難を改善する目的で実施され、その規模は数千万人に及んだと言われている。習氏も20代前半に陝西省の貧しい農村に送られ、崖の岩肌に掘られた洞穴で生活した経験があるという。 だが、現在の中国は当時と比べられないほど豊かになっている。時代錯誤の政策を打ち出すようでは、共産党政府も焼きが回ったのではないかと思わざるを得ない。 そのせいだろうか、権威主義体制にもかかわらず、民主化を要求する垂れ幕が掲げられたり、女性教授2人が実名で習氏を批判する声明をインターネットに掲載するなど、異例の事態となっている。 二人の女性教授は声明で「自由のため、独裁に反対せよ! 民主のため、奮起し戦え!」と学生に呼びかけたという。 最悪の事態は「金融危機」 中国経済の苦境が米国の金融市場に波及するリスクにも警戒すべきだ。 ロイターは1日、「中国の政府系ファンドが約10億ドル(約1450億円)規模の米国の流動性の低い金融資産の売却に着手した」と報じた。 米国ではヘッジファンドが直接融資するプライベートクレジットを証券化した金融商品の取引が不調となっている。利回りの高さから、市場規模は2兆ドル(約290兆円)を超えているが、流動性が低いという欠点を有している。 関係者が動揺する中、資金繰りに窮した中国勢が投げ売り攻勢を強めれば、流動性に問題を抱える米国のクレジット市場全体でパニックが起きてしまうのではないかとの不安が頭をよぎる。 予断を許さない「米中関係」 思い起こせば、2008年のリーマンショックは流動性の低い市場でのパニックが世界の金融市場全体に広がったことで起きた。 いずれにせよ、米中経済の今後の動向について最大限の関心をもって注視すべきだろう。 さらに、連載記事『中国「寝そべり族」がさらに劣化していた…!トランプvs.習近平の熱い米中交渉のウラで蔓延!努力を拒む若者たちの《絶望の日々》』でも、窮地に陥る中国経済の実情を解説しているのでぜひ、参考にしてほしい。 【つづきを読む】中国「寝そべり族」がさらに劣化していた…!トランプvs.習近平の熱い米中交渉のウラで蔓延!努力を拒む若者たちの《絶望の日々》