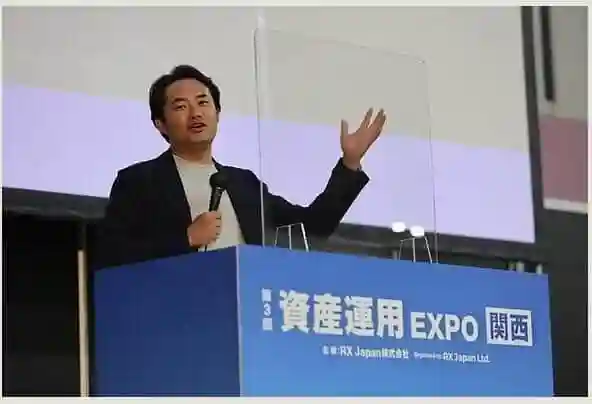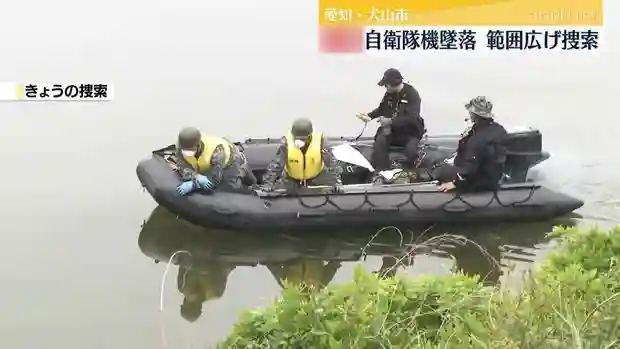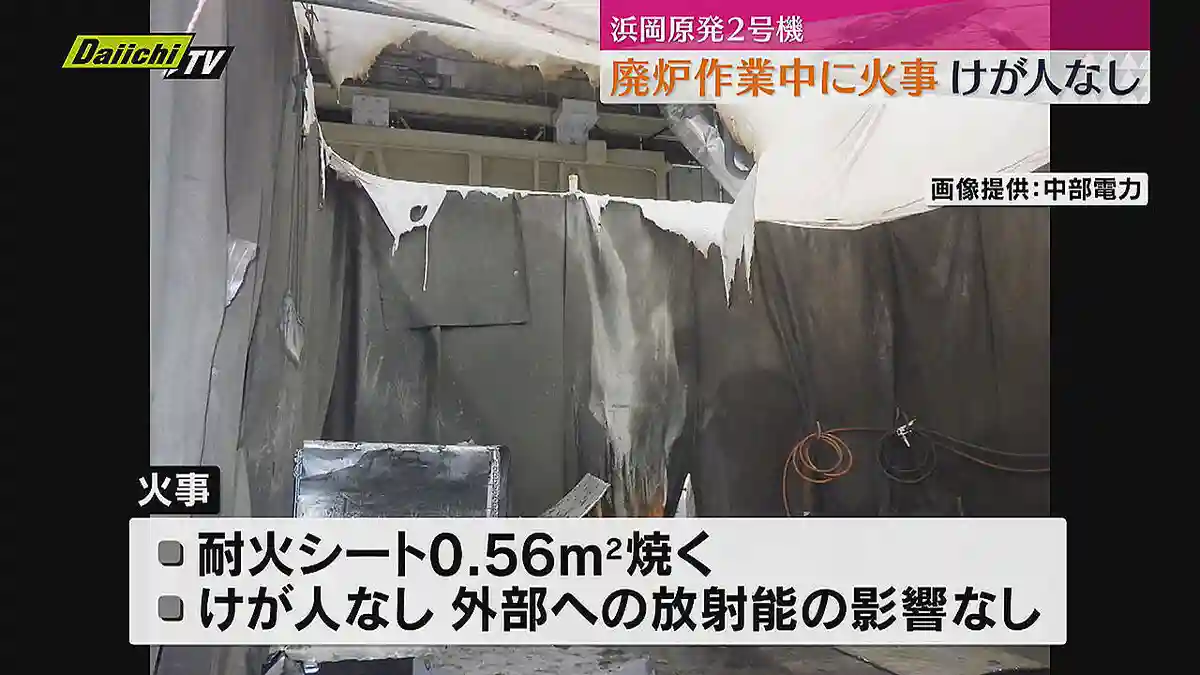小学生の1年間の学校生活1200時間に対し、放課後の時間は1600時間。この未来の貴重な「資産」となる時間を、塾や習い事だけで埋めていませんか? なんてもったいない!! 1600時間を「未来への投資をする時間」と考えると、小学生のうちにまず優先してやるべきことは、学校や塾の勉強での認知能力の向上ではなく、社会につながるための人間力=非認知能力をいかに育むか。 民間保育園・学童を広く展開する著者・島根太郎が、多くの子どもたちと接し、キッズコーチと子どもたちのかかわりを通じて学んできたヒントを明かした書籍『子供の人生が変わる放課後時間の使い方』より、抜粋してご紹介します。 学校教育1200時間に対して学童保育は最大1600時間 そもそも学童保育と聞いたとき、あなたはどのような場所をイメージしますか? 今まさに小学生のお子さんを通わせている保護者の方は、毎日足を運ぶ身近な施設がパッと思い浮かぶでしょうし、小さなお子さんを子育て中の保護者の方は、「そういえば、小学校のそばにあったかも……」と学校の敷地にある建物に小学生たちが集まっている場所を思い起こすかもしれません。 もともと学童保育は、働く女性の数が増加し、いわゆる「鍵っ子」が社会問題化した高度経済成長期に、保護者の自主運営や市町村の事業として広がっていった仕組みです。ですから、地域によって運営のあり方が違い、隣接している東京都と神奈川県の人でも学童保育という言葉からイメージする姿が異なります。 現在、学童保育の運営は3つの形式で行われています。 1つ目は、行政が施設の設立と運営業務を行う「公立公営」。 2つ目は、行政が施設の設立を行い、運営業務に関しては民間企業などに複数年にわたり包括的に委託する「公立民営」。 3つ目が、民間企業などが施設の設立、運営業務を行う「民立民営」のいわゆる民間学童(KBCは3つ目の民間学童としてスタートし、現在は港区、新宿区、大田区、目黒区などから運営業務を受託して公立民営の学童保育事業も行っています)。 昭和30年代に学童保育事業が始まった頃と比べ、近年は子どもたちが自由に遊ぶことのできる場、機会は減っていて、習い事や塾が増え、保護者の働き方も大きく変わりました。こうした変化によって、子どもたちの放課後の過ごし方も多様化。保護者のニーズは、遅い時間までの預かりや教育プログラムによる学習機会があること、インストラクターによるスポーツの指導など、公的な事業だけでは対応しきれない範囲に広がっています。 そこに私たちのような民間事業者が参入したことで、大きな括りの学童保育という名称の中で提供される支援、サービスの質、内容ともに多様化しています。 放課後、学校敷地内の建物にランドセルを置いた後、子どもたちが校庭に走り出て遊ぶ、昔ながらの公立学童もあれば、児童館や公民館の一角に子どもたちが集まってくつろいで過ごす公立民営の学童もあれば、各小学校まで送迎の車両が向かい、習い事への移動も担ってくれる今どきの民間学童もあります。 いずれにしろ共通しているのは、そこにいる大人たちが子どもたちを「おかえり」と迎え入れ、放課後時間をともに過ごしていくこと。小学生が学校にいる時間は年間1200時間。それに対して、家庭での食事や就寝などを除いた放課後の時間は1600時間です。 生活や成長における放課後時間の役割は大きく、さらにその多くの時間を子どもたちは学童で過ごします。学びの場、成長の場として、学童保育は大きな意味を持ち、可能性を秘めているのです。 学童保育の可能性 「水は方円の器に随う」という言葉があります。 8〜9世紀の中国の詩人である白居易の詩の一節で、その意味は「水は容器の形によって、どんな形にでも順応する」というもの。そこから転じて、人は交友関係や環境によって、善にも悪にも染まりやすいことの例えとして使われています。 この言葉のとおり、子どもたちの成長には出会う人と、日頃から接しているコミュニティが大きな影響を与えます。学童保育は学校も学年も異なる子どもたちが集まり、交流しながら放課後時間を過ごす場所。学校はさまざまな機会や経験を通して、子どもたちの成長を促してくれますが、基本的には教科教育が中心となります。 学校よりも長い時間通うことになる学童は、学校と違う役割を担うことができるのです。学校の宿題をしたり、習い事の教材を進めたり、読書をしたり、民間学童オリジナルのプログラムを受講したりと、何かを学ぶ時間も取れますし、友達や大人たちと一緒に活動することがコミュニケーション能力を伸ばす機会にもなります。 でも、私はそれ以上に学童での放課後時間において重要だと考えているのが、余白の時間です。誤解を招く表現かもしれませんが、子どもたちが安心してぼーっと過ごせる時間があること。そこに学童保育の可能性を感じています。 学校の授業、塾のカリキュラムは基本的に大人の決めたタイムスケジュール通りに子どもたちが行動するようにできています。そこで学べることはもちろんたくさんありますが、大きく欠けてしまっている要素があります。 それは子どもたちが自分で選択したり、決定したりする機会です。 人は自己決定を繰り返すことで、成長していきます。そして何かを選んだり、決めたりするまでには、ぼんやりと自分と向き合う時間が欠かせません。あなたもカフェでコーヒーを飲んだり、公園のベンチで一息ついたり、歩きながらその日の出来事を思い返したり、ぼーっとする時間の中で、考えをまとめたり、自分の行動を振り返ったり、明日以降に何をするかを決めたりしていませんか? 日々試行錯誤を繰り返しながら成長している子どもたちには、大人以上にぼんやり過ごす時間が必要です。本来、放課後は子どもたちにとって解放されている自由な時間のはずだったのに、そこまで大人が設計したカリキュラムの連続にしてしまうと、子どもたちから自分で考える機会を奪うことになってしまうのではないでしょうか。 学童で過ごす放課後時間には、保護者からも学校や塾の先生からもあれこれ言われない、自由な時間があります。 【オススメ】「遊びより勉強に価値がある」というのは大人の偏見! 自由な遊び時間を子どもに与えることで身につく驚異的能力