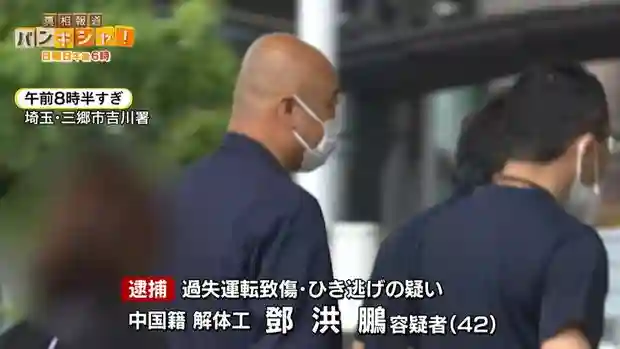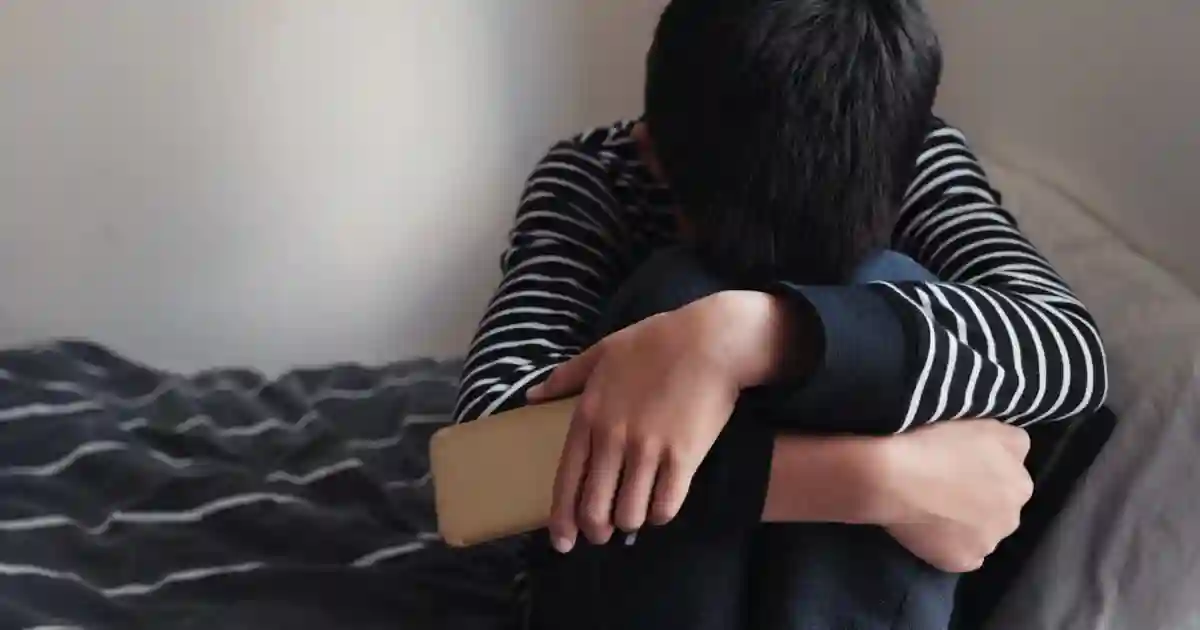
5年ごとの「先進諸国の子どもの幸福度」レポート 5月14日、ユニセフが5年ごとに公表している「 先進諸国の子どもの幸福度レポート・カード19(RC19) 」が公開となった。同調査は毎年同じ指標に基づいたもので、41ヵ国調査をして結果が集計できた36ヵ国のランキングと分析が発表されている。 2020年のレポート(RC16)での日本の総合順位は、38ヵ国20位で、精神的幸福度がワースト2位の37位だったことが大きく報じられた。 それから5年経った今回発表された精神的幸福度の順位は、日本は36カ国中14位。精神的幸福度は37位から32位、身体的健康は1位、スキルは27位から12位と「ワースト2位から脱出」はしている。しかし細かいその内容には、決して「好転した」と言い切れない“危うさ”があった。レポートを詳しくみてみよう。 SNSを6時間以上利用する子の満足度は最も低い 「先進諸国の子どもの幸福度レポート・カード」はユニセフ・イノチェンティ研究所による調査で、精神的幸福度、身体的健康、スキルの3つの分野についてそれぞれ2つの指標に基づいて順位が計算されているものだ。調査期間は2018年から2022年とまさにコロナ禍と重なっている。 結果、日本は36カ国中14位とやや上昇している。分野別では、精神的幸福度は37位から32位、身体的健康は1位のまま、スキルは27位から12位と上がっている。身体的健康が1位にもかかわらず、14位なのは、精神的幸福度が低いことが大きく影響している。 ちなみに総合1位はオランダで、精神的幸福度1位、身体的健康4位、スキル11位。ついでデンマーク(精神的幸福度3位)、フランス(同11位)、ポルトガル(同2位)と、総合上位は精神的幸福度も高い傾向にあることもわかる。 では、日本の子どもたちの精神的幸福度が低い最も大きな原因は何だろうか。 精神的幸福度は「生活満足度調査」と「自殺率」から判断される。 まず「生活満足度調査」からみてみよう。15歳児を対象に、以下の7つの要素が「少ない」か「中くらい」か「多い」かで、OECDが満足度を調査している。ちなみに、日本の満足度は全体的に高くはなく、平均値をわずかに上回る数値だ。 1) 性別(Gender) 2) 社会経済的背景(SES) 3) 運動量(Exercise) 4) 宿題の量(Homework) 5) SNSを使用する時間(Social Media) 6) 親との会話の頻度(Talk with parents) 7) いじめの有無(Bullying) この7つの中でまず「いじめが多いと生活満足度がとても低い」ことは当然だ。これは誰もが納得することだろう。 注目すべき点は、「SNSを多く使う子どもの満足度もとても低い」ということ。使用量が少ない子、中くらいの子の差はそれほどではないが、6時間以上使用する子の満足度は最も低いのである。SNSといじめもつながりを感じる。 「経済的背景」が与える生活満足度 さらに、安心・安全の生活を送れているか否かは生活の満足度につながる。わかりやすいのは社会経済的背景だろう。お腹が空いていたり、暑かったり寒かったりしても対策できないとなったら当然生活満足度は低くなる。 2022年の国民生活基礎調査によると、日本の子どもの貧困率は11.5%。約9人に1人の子どもが貧困に直面している。中でもひとり親家庭の貧困率は44.5%、つまり約2人に1人が貧困だ。日本の平均世帯年収は546万円だが、母子世帯の平均は328万円だ。その多くはシングルマザーの家庭で、養育費を受け取れていなかったり、子どもがいることで条件の良い就職ができなかったりとさまざまな要因が考えられる。物価高になる前から、満足する量を食べることができない家庭も少なくないのだ。 困窮家庭を支える「NPO法人キッズドア」が2025年4月に出した 報告書 によれば、生活を苦しいと感じている母子世帯は約 8 割となっている。また、生活を苦しいと感じている割合は、所得が低い・貯蓄が少ないほど高く、回答者の約6割が、食料の困窮を、約7割が「子どもの服と靴」の困窮を、8割が「自分の服や靴」の 困窮を経験していた。経済的背景が不安定だと、生きていくことに不安になるのは当然だ。実際最も低い層の生活満足度は64%、最も高い層が70%となっている。 経済格差と同じく影響する「親との会話の量」 そして、経済格差と同じくらい影響しているのが「親との会話の量」だ。 親との会話の少ない層の生活満足度は、経済的背景とほぼ同じ64%。中間が69%、最も高い層が71%。「衣食住」と同じくらい影響しているのだ。 しかし満足度を高めうる「親との会話」にもかかわらず、親から生活すべて指示されていたり、否定され続けていたらどうなるだろうか。 実際、経済的背景として裕福な暮らしをしていても、親子が断絶してしまった実例がある。リッツ横浜探偵社の山村佳子さんのもとには多くの相談が来るが、そのひとつが63歳の女性から寄せられた「36歳の息子に居場所をつきとめ、元気に暮らしているかどうか調べてほしい」というものだった。彼女は専業主婦で、夫は会社経営をしていてかなり裕福だ。 この36歳の男性は女性の長男だ。背景を聞いていくと、「できのいい」次男と常に比較され、「できが悪い」と言われ続けていた。母親が「良かれと思って」長男の生活に干渉し、受験に「失敗した」ことを嘆き続け、口を出し続けていた。 このような否定の言葉ばかり受けていたら、満足度があがるはずもない。いい影響をもたらしうるものが、真逆の結果となってしまうのではないだろうか。だからこそ長男は33歳のとき行方をくらまし、母親との連絡を一切断ってしまったのだ。 日本で深刻な「子どもの自殺率」 「精神的幸福度」を示すもう一つの指標が「若者の自殺率」だ。生活満足度の低さに加え、日本は自殺率も平均より高く、その結果、精神的幸福度の低いランキングとなっている。東京都立大学子ども・若者貧困研究センター長の阿部彩氏は、今回のレポートを受けてユニセフにコメントを寄せている。 報告書 で阿部氏は以下のように綴る。 “日本の子どもにおいて特に深刻なのは、子どもの自殺率である。日本の子どもの自殺率は、そもそも高い値であり、また、RC16からRC19にかけて最も増加幅が大きく、本報告書では上から4番目の高さとなっている。生活満足度が平均的な子どもの精神的幸福度を示しているのに対し、自殺率は最も厳しく、危機的な精神状況の現れであり、これが悪化していることは大きな懸念材料である。子どもの自殺者数の増加傾向は2024年も続いており、過去最多となっている。” 実際、文部科学省は2025年2月、学校関係者に自殺に関するある通知を出した。「 令和6年の児童生徒の自殺者数(暫定値)の公表を踏まえた 児童生徒の自殺予防に係る取組の強化について(通知) 」というものだ。 警察庁・厚生労働省の自殺統計(暫定値) から、令和6年の児童生徒の自殺者数が527人と過去最多になる見込みだと分かった上での警告である。令和6年の日本の自殺者数は20,320人で、前年と比べ1,517人減少し、過去2番目に少ない数値となった。しかし若者の自殺者は過去最多と増加しているのだ。 2025年5月14日、36歳の男性が10歳の女子高生を誘拐した容疑で逮捕された。この容疑者は別の10〜20代の男女4人に対する自殺ほう助や嘱託殺人未遂などの罪で起訴されており、遺体で見つかった女子高生の死亡にも関係しているのではないかと目されている。 命が誕生するのは奇跡だ。授かりたくても授かることができない人も多い。かたや、せっかく誕生した命なのに、自ら断ってしまいたいと感じてしまう子どもが多いというのはなんと悲しいことか。そして日本の未来の危機にもつながる。 子どもたちの生活満足度を高めることは、自殺をしたいと感じてしまう社会を変えることと同義のはずだ。安心し、安全な暮らしができること、自分を認められる場所があること。そのためにも、10代の子どもや若者の自殺、いじめ対策、子どもがデジタル空間を安全に利用するための支援については、早急に改善する必要があることがわかる。さらに貧困対策、そして家庭での親子の関係性を良くすることが、子どもたちの幸福度を高めるために有効ということだ。 この調査は指標にすぎないが、我々が今すぐにしなければならないことが浮かび上がってくるのだ。 「裕福な家庭」で36歳の長男が3年行方不明…63歳の母が探偵に依頼した意外なこと