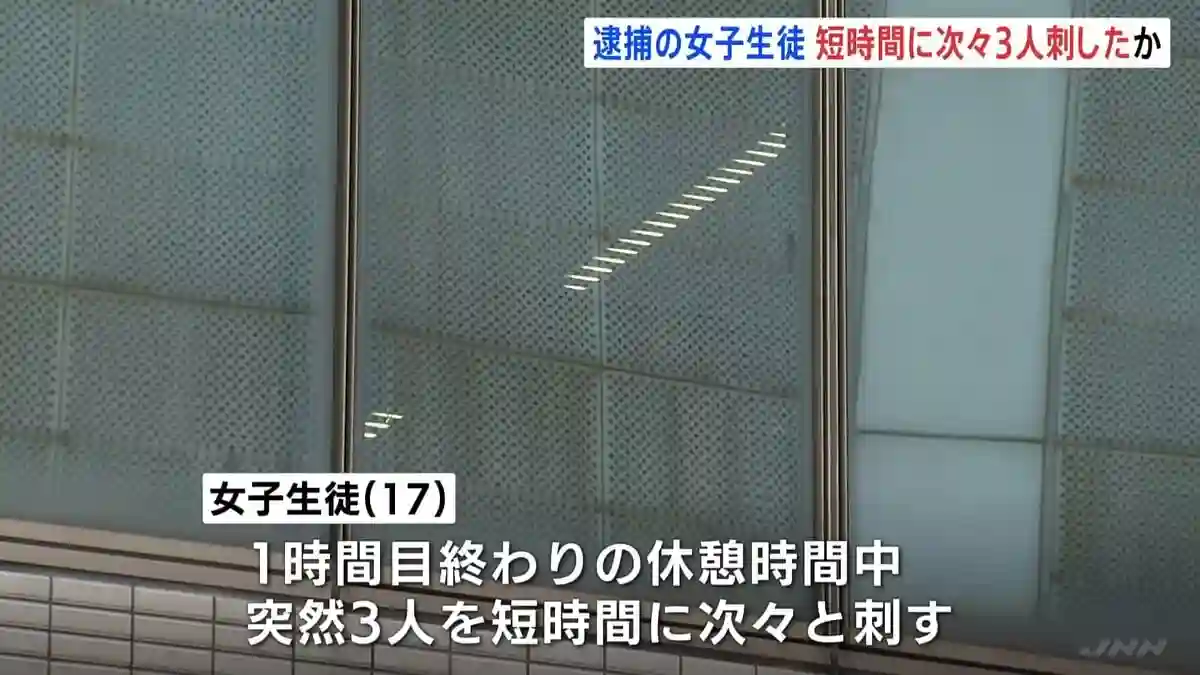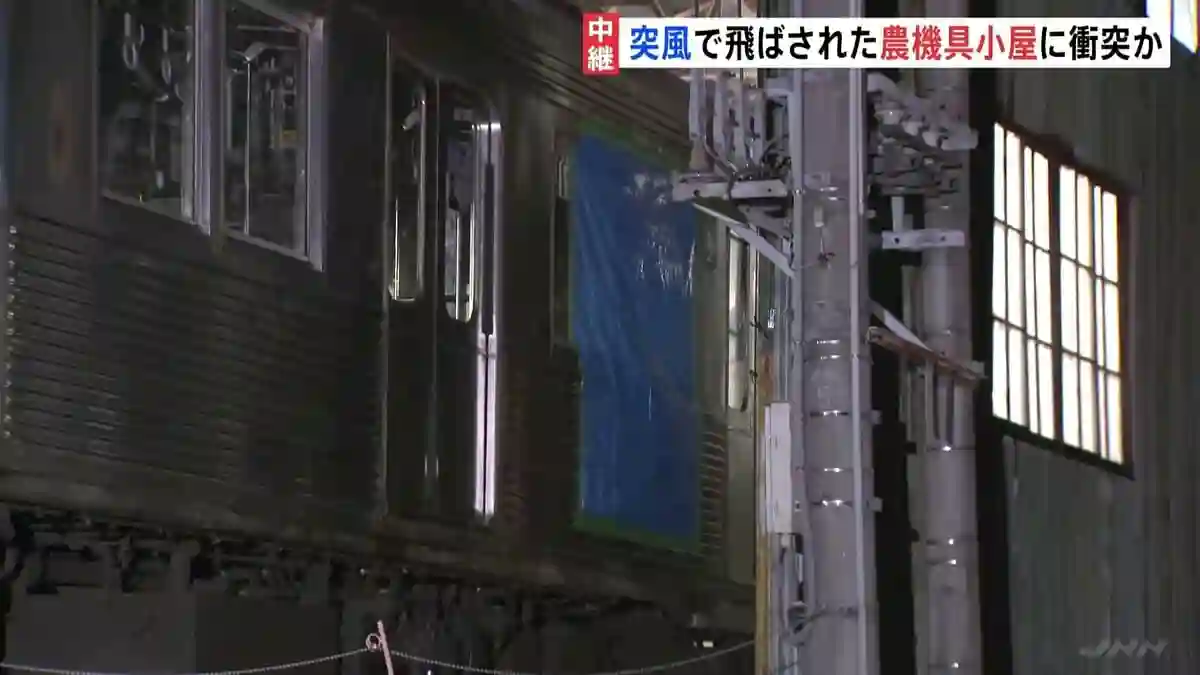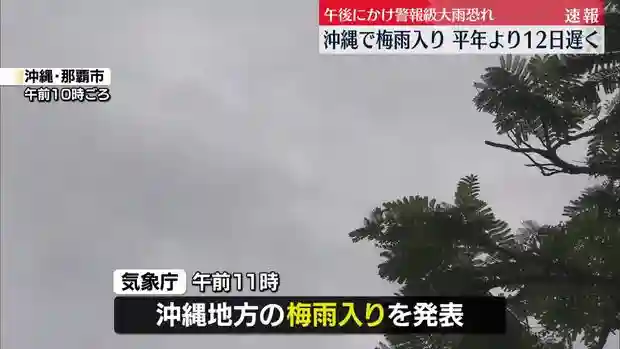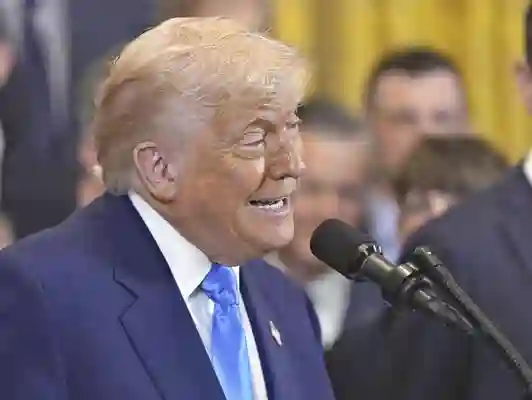人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。 世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。 この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか? オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』(長谷川圭訳)が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。 『MORAL 善悪と道徳の人類史』 連載第119回 『ナチスは人間の“本性”を利用して成功した!?…文明を完全に崩壊させる「新しい道徳」が登場、従来の美徳が放棄されたワケとは』より続く 戦争と人類の繁栄 原子爆弾による広島の破壊で幸運にも九死に一生を得た山口彊は、傷つき、やけどを負い、片耳の聴力を失い、ほうほうの体で3日後-この上なく悪いタイミングで-故郷の長崎にたどり着いた。 2010年に93歳で他界した山口は、これまで日本政府が公式に「二重被爆者」、つまり1945年の二度の原爆投下で2回とも被爆したと認めた唯一の人物だ。山口ほど、説得力をもって平和のために発言できる人物はほかにほとんど存在しない。実際に晩年の彼は、核軍縮を求める発言を繰り返した。 ドイツでは、全国各地のツィーテン通り、ヨーク通り、グナイゼナウ通りに兵役不適格者や兵役拒否者が暮らしている。どれも、何十年あるいは何百年も前の騎兵隊長や元帥にちなんで名付けられた通りだ。そうした名称は過ぎ去った世界の証人である。 なぜなら、第2次世界大戦を通じて、直感的に理解しやすい洞察が非常に広く世間に浸透したからだ。それは、戦争をするのはほぼいつでも悪いアイディアであり、人類は戦争をしないほうが繁栄できるという洞察だ。今では信じられないことだが、当時この考え方はとても斬新だった。 冷戦という均衡状態 数百人の兵士が発砲するのと同じぐらいの数の弾を発砲できる機関銃があれば、戦争に送る人の数を減らせるので、戦死者も減るのでは?威力をどんどん増しつつある殺人兵器を発明しつづければ戦う必要がなくなるはず、という考えは明らかに間違いなのに、これまで何度も繰り返されてきた。 機関銃の前身であるガトリング銃の発明も、アルフレッド・ノーベルによるダイナマイトの発明も、殺人の効率化による平和という希望を実現することはできなかった。そして、核兵器による絶滅の脅威を通じてようやく、人類の最終兵器が世界の敵対国家に相互抑止というある程度の均衡状態を実現するという、逆説的な結果に落ち着いたのである。 この均衡状態を、今の私たちは「冷戦」と呼んでいる。技術の革新が文明化という副作用をもたらしたのだが、しかしそれだけが、「戦争は別の手段を用いた政治に過ぎない」としたクラウゼヴィッツ的なプラグマティズム〔訳注:カール・フォン・クラウゼヴィッツ。プロイセンの軍事学者で、戦争は政治の道具であると説いた〕から政治と戦争を解放できた理由ではない。戦争に対する嫌悪感は、暴力的な紛争を規則で封じ込めようとする意図的な努力の結果でもある。 戦争はなくならなかったが… 法学者のウーナ・ハサウェイと法哲学者のスコット・シャピーロは、過小評価されがちな「ケロッグ=ブリアン条約」の役割の重要さを強調する。 1928年8月27日にパリのオルセー通りで、条約名のもととなった米国国務長官のフランク・ケロッグとフランス外務大臣のアリスティード・ブリアン、加えてドイツ外務大臣のグスタフ・シュトレーゼマンが署名した協定書のことだ。署名に先立って、ケロッグはシュトレーゼマンに金の万年筆を寄贈した。 そこには「Si vis pacem, para pacem(平和を望む者は平和に備えよ)」と刻まれていた。その極めて短い協定書の2つの条文には、今後は一切の国際紛争を平和的な手段をもって解決すると記されていた。 「パリ条約」とも呼ばれるこの条約は、今では底抜けのお人好しの証として冷笑されることが多い。違法と宣言することで戦争をなくそうとする態度は、子供じみているとも言えるし、皮肉と捉えることもできる。あらゆる協定が反故にされて戦争が起こっている場所に、そのような協定を突きつけたところで、何の役に立つというのか?しかし、そのような見解もまた、殺人と窃盗を違法と宣言したところで殺人も窃盗もなくならないのだから、それらを違法とすることには意味がない、と主張するのと同じぐらい的外れだ。 実際には、紛争を平和的に解決するという公的な意志宣言は史上初の快挙であり、国際政治にとって真のパラダイムシフトであった。この条約に第2次世界大戦を防ぐ力はなかったが、それはどの法律にも言えることで、法律があるから侵害行為がなくなるというわけではない。にもかかわらず、この条約が規範となって、強い緊張関係にあったドイツとフランス、あるいはイギリスとロシアなどに、かつては考えられなかったほど長い年月にわたって争いのない期間、すなわち「長期平和」が実現したのである。 『「社会の豊かさ」が「平和な世界」の実現に直結…戦争が紛争解決の“最終手段”でしかなくなった「世界平和」の裏側』へ続く 【つづきを読む】「社会の豊かさ」が「平和な世界」の実現に直結…戦争が紛争解決の“最終手段”でしかなくなった「世界平和」の裏側