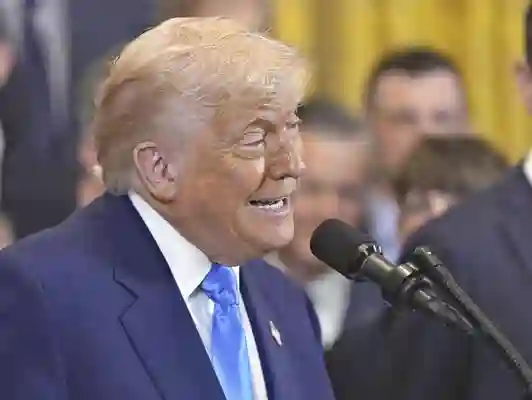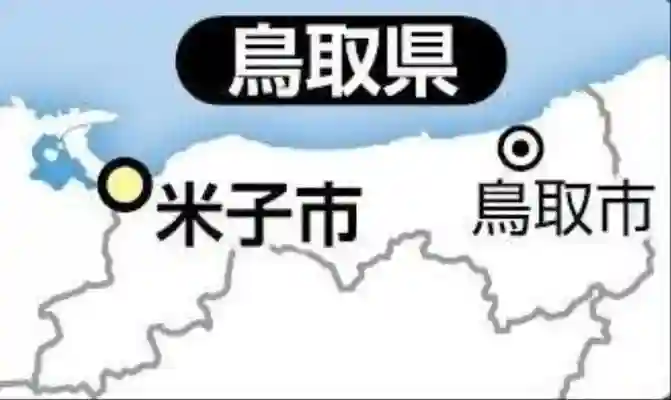道東を恐怖と混乱に陥れた「牛を襲うヒグマ」の正体とは? ハンターの焦燥、酪農家の不安、OSO18をめぐる攻防ドキュメント『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』。 追うハンター、痕跡を消すヒグマ、そして被害におびえる酪農家の焦燥をつづり、ヒグマとの駆除か共生かで揺れる人間社会と、牛を襲うという想定外の行為を繰り返した異形のヒグマがなぜ生まれたのか、これから人間は変貌し続ける大自然とどう向き合えばいいのか。『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』から抜粋・再編集してご紹介! 山の神を「怪物」に変貌させたのは大自然か、それとも人間か? 『「牛66頭を無差別に襲ったヒグマ」OSO18の始まりの物語…突然変異の怪物ヒグマの「最初の被害者」が見た「異様な現場」』より続く オスとメスで違う 「ヒグマは、オスとメスで、まったく行動が違います。オスは行動範囲が広く、生まれた場所から遠く離れていく。一方、メスは、生まれた場所の近くで一生を過ごします。冬眠場所も、非常に近い範囲に限られています。だいたい1年に2頭の子どもを産みます」 OSO18については、報道でしか知らないと断りながら、坪田はこう言った。 「これだけ捕まらないわけですから、賢いヒグマだと思います。人間に対する警戒心が非常に高い。不思議なのは、やはり食べていないことです。ヒグマは、人を襲ったときも食べるわけですから。食べないのに襲うというのは、聞いたことがありません。きわめて特殊です」 坪田によれば、ヒグマは元々食肉類で、ウシやシカのように胃が複数あるわけでも、ウマのように盲腸が発達しているわけでもない。解剖すると内臓は肉食仕様のままだが、数百万年の進化の過程で、次第に草食に傾いていったのだという。 「専門的には『日和見的な雑食』と言いますが、要は、手に入れられる食糧は何でも食べるわけです。もし、肉食だけだったら、ヒグマは絶滅していたかもしれません。肉はいつも得られるわけではありませんから。正しく言えば、草食化していった個体群だけが生き残ったわけです」 そして坪田は、意外なことを口にした。 「そもそも、いま北海道にいるヒグマのなかで、肉を食べたことのある個体はほとんどいないと思います」 「え、そうなんですか?」 予期せぬ話だった。人間が襲われたときに無残に食べられるイメージから、私には、ヒグマは肉食が中心だという思い込みがあった。それは間違いだと、坪田は明確に指摘した。 「春は山菜、それから夏にかけてはキイチゴやベリー類を食べ、秋にはドングリなどの木の実。9割のヒグマは一生のうちで一度も肉を食べたことがないはずです。木彫り熊のイメージがあるかもしれませんが、いま、サケやマスが手に入る地域は北海道でも知床くらいです。ただ、学習能力が高いので、一度味をしめると学びます。美味しくて栄養価が高い肉を覚えたヒグマは厄介です。一度人を襲ったヒグマは、必ず捕獲しなければならないのも、同じ理由からです」 肉の味を覚えると… 「エゾシカや牛を食べることはあるのではないでしょうか?」 「それも、滅多にないと思います。まず、牛のような家畜を襲うこと自体、近年は聞いたことがありません。牛も大きいですから、獲物として認識していないのだと思います。それから、意外かもしれませんが、生きているエゾシカをヒグマが捕らえるのは難しいんです。森の中でエゾシカは相当なスピードで逃げますから。例外があるとしたら、生まれたての子ジカか、交通事故などで死んでしまった個体の死骸でしょうか」 ヒグマは、血の匂いを好み、死んだエゾシカを食べて肉の味を覚えた可能性は十分にあると、坪田は言う。だが、だとしたら、なぜ襲った牛を食べないのか。 「それは、本当にわかりません。ただ、被害が6月から9月に限られているなら、食べることと関係しているとは思います。冬眠明けからしばらくは、胃も小さくなっていますし、山菜などで十分です。9月や10月になるとドングリのような木の実があるし、大好物である飼料用トウモロコシのデントコーンもあります。夏が、一番ヒグマにとって餌が厳しい時期なんです。だからその時期にだけ、牛を襲っているのかもしれません」 言葉を選び、わからないことはわからないと明言しながら、坪田はOSO18の実像を推理していった。だが、この日、最も印象的だったのは、次の言葉だった。それは、北海道のヒグマが絶滅の危機に瀕していた時代から、40年にわたり研究を続けてきた坪田の、ヒグマへの愛情を感じないわけにはいかないものだった。 「OSO18は、本当はとてもいいクマだと思います。慎重さと臆病さを持った、賢くて、学習能力の高いヒグマ。だけど、どこかで道を間違えて牛を襲うようになった。これだけの被害をもたらしているわけですから、捕獲しなければなりません。ただ、大事にしなければいけない、いいクマを殺さなくてはならない状況になっていることが、私は残念です」 坪田が残念だと言うほどの、とてもいいヒグマが、なぜ牛を襲う凶悪な連続犯になったのだろう。いったい、どんなヒグマなのだろう。取材の帰り、坪田の言葉を反芻し、ますますOSO18に興味を惹かれていった。 『牛66頭を襲った怪物ヒグマ「OSO18」の被害を防げなかったのはなぜか…酪農の「大規模化」が放牧地にもたらした影響』へ続く 【つづきを読む】牛66頭を襲った怪物ヒグマ「OSO18」の被害を防げなかったのはなぜか…酪農の「大規模化」が放牧地にもたらした影響