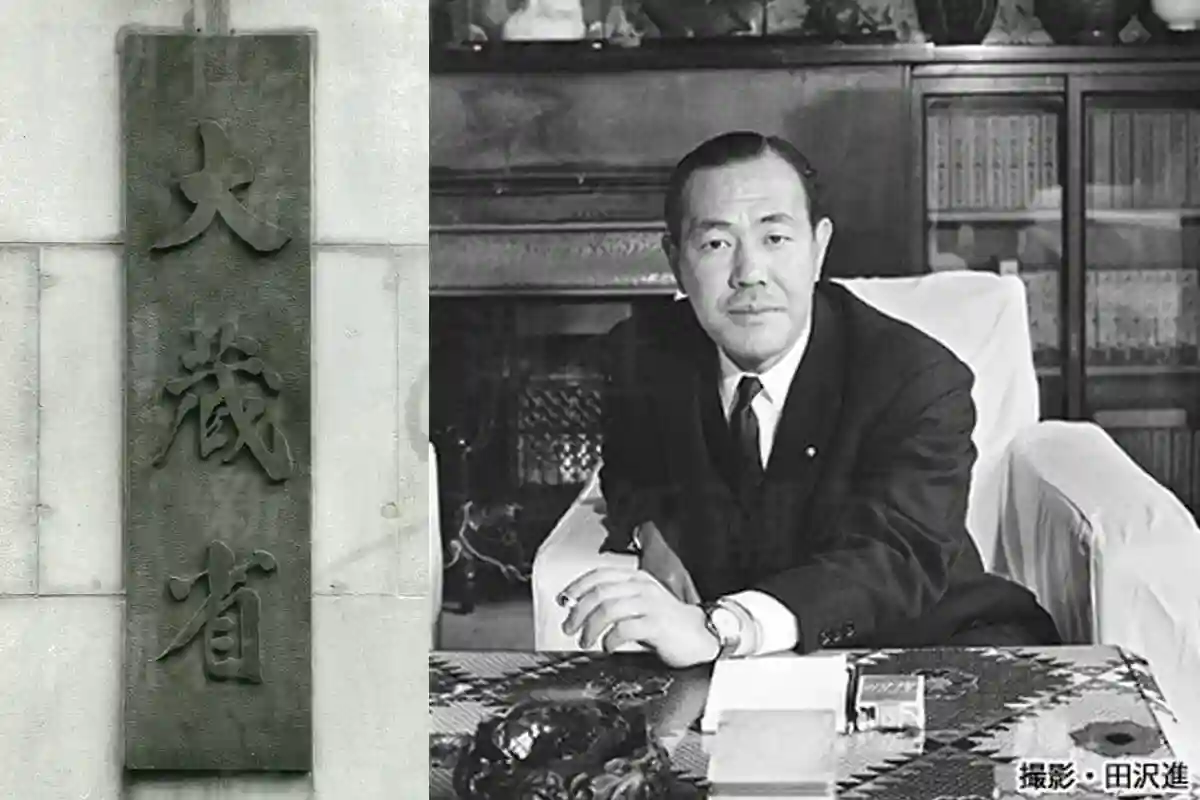蔦重に500両で身請けさせたい 蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)にとっては、かつて世話になり、手助けをし、また、眼の上のたんこぶでもあった地本問屋の鱗型屋孫兵衛(片岡愛之助)。だが、海賊版に手に染めて摘発されたダメージが大きく、再起できないまま店を畳むことになった。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢〜』の第19回「鱗(うろこ)の置き土産」(5月18日放送)。 【写真】「誰袖」を演じる福原遥、艶やかなドレス姿「4変化」 “シックな黒色”さらに“シースルー”も そこで蔦重が、吉原内の稲荷神社に「鱗の檀那の店も、うまくいきますように」と祈願して、両手を合わせていると、後ろから女性が蔦重に抱きつき、合わせた蔦重の手に自分の手を重ねて、「わっちらの恋も、うまくいきんすように」といった。大文字屋の売れっ子の花魁、誰袖(福原遥)である。 誰袖を演じる福原遥 蔦重は嫌がってため息をつき、彼女を振り払って「お稲荷さんの境内でこんな」というが、誰袖はまったく気に留めず、「お稲荷さんはお怒りになりんせんよ。だってわっちら、夫婦(めおと)になりんしたゆえ」といって、1枚の証文を蔦重に見せた。そこには「誰袖は蔦屋重三郎に500両にて身請けを許すこととす」書かれ、大文字屋の楼主、市兵衛(伊藤淳史)の署名があった。 「親父様から遺言をいただきんした」と誰袖。大文字屋市兵衛は少し前に病死したが、いまわの際に、誰袖は証文を無理やり書かせていたのだ。「これであとは兄さんが500両、支度するだけでありんす」。そういって誰袖はお稲荷さんに手を合わせ、「500両、500両、500両」と祈願をはじめたが、蔦重は顔をしかめて立ち去ってしまった。 幼少のころに吉原に売られて 続いて蔦重はひとり歩きながら、「ああいうのが大奥で毒盛ったりすんだろうな」とつぶやいたから、蔦重は誰袖のことをよほど煙たがっているという設定のようだ。しかし、蔦重はともかくとして、誰袖と身請けは切っても切り離せない。 それについては後述するとして、誰袖は小芝風花が演じて評判になった瀬川と入れ替わるように『べらぼう』に現れたが、じつは、以前にも登場していた。そのときはまだ女郎見習の振袖新造で、名も誰袖ではなく「かをり」。子役なので福原遥ではなく、稲垣来泉が演じていた。 誰袖の出自などについては、ほとんどわかっていないが、子供のころに吉原に売られた可能性が高い。吉原では、貧しい親が妓楼(女郎屋)に借金した担保として売られた娘は、まず禿と呼ばれ、花魁のもとで雑用をこなしながら作法を学んだ。少し成長して13〜16歳になると振袖新造と呼ばれて女郎の見習いを務め、おおむね17歳から客をとった。 むろん女郎にもランクがあり、蔦重の同時代には上から順に「呼出」「昼三」「座敷持」「部屋持」……などに分かれていた。このうち花魁と呼ばれたのは呼出と昼三で、場合によっては座敷持も花魁にふくめた。とくに呼出と昼三は、妓楼の格子越しに並んで客をとる張見世はせず、引手茶屋に上がった客の指名を受けると、禿や振袖新造らを引き連れて仰々しく練り歩いて引手茶屋にやってきた。これが花魁道中である。 教養があり狂歌を遺した すでに『べらぼう』の第18回で、誰袖が朋誠堂喜三二(尾身としのり)のもとへ花魁道中する場面が流された。実際、誰袖は「呼出」だったのである。蔦重が天明3年(1783)正月に刊行した吉原のガイドブック『吉原細見』には、「大もんじや市兵衛」のもとの女郎として「たがそで」という名が記され、名前の右上に「よび出し」と明記されている。 花魁ともなると、教養ある客を相手にすることが多く、女郎にも一定の教養が求められたが、誰袖の場合、身につけた教養の痕跡がいまに残されている。彼女は狂歌を詠んだことで知られる。和歌の定型に滑稽な内容や皮肉、風刺などを盛り込んだ狂歌は、天明の時代に大流行し、蔦重も狂歌絵本に力を入れることになる。 誰袖の歌は天明3年、蔦重以外の版元から刊行された『万歳狂歌集』に載っている。「わすれんと/かねて祈りし/紙入れの/などさらさらに/人の恋しき」。忘れたいと祈っていても、彼からもらった紙入れを見ると、ますます恋しくなる、という恋の歌だ。 彼女が所属する大文字屋の楼主の市兵衛は、前述したように病死した。このため養子が後を継ぎ、同じ大文字屋市兵衛を名乗った。この2代目は、じつは天明の時代を代表する狂歌師でもあり、「加保茶元成」という狂名(狂歌を詠む際のペンネーム)で活躍した。自分の別宅で頻繁に狂歌の会を開催したほどだから、誰袖も手ほどきを受けたのではないだろうか。 誰袖はほかに、自分の姿絵も後世に伝えている。山東京伝(浮世絵師の北尾政演と同一人物)が記した蔦重刊『吉原傾城新美人合自筆鏡』には、大文字屋の女郎たちが描かれた錦絵のなかに「たか袖」の名が見える。 身請けにかかった1,200両の出所 状況証拠からして、かなり売れっ子だったはずの誰袖だが、彼女が呼出と記されて1年後に刊行された蔦重版『吉原細見』には、その名が消えている。身請けされたのである。身請けとは、客が女郎の身請け証文を買い取って、女郎の身柄を引きとることだ。しかし、客は『べらぼう』の第19回で誰袖が望んだ蔦重ではなかった。 それは旗本で幕府の勘定組頭を務め、『べらぼう』では桝俊太郎が演じる土山宗次郎だった。1,200両(1億2,000万円程度)が投じられたと伝えられる。ドラマで誰袖が蔦重に求めた500両(5,000万円程度)よりだいぶ高額だが、じつは、必ずしもそうではない。女郎を身請けする際は身請け金だけで済まないのが一般的で、祝儀を渡したり祝宴を開いたりして出費がかさみ、身請け金のグロスの2倍程度かかることは珍しくなかった。だから、身請け金は500〜600両程度だったかもしれない。 だが、それにしても、一介の旗本に払える金額なのか。瀬川を身請けした鳥山検校は、旗本の困窮に付け込んで法外な高利で金を貸し、旗本たちを破滅に追い込んでいた。土山宗次郎が支払えたのは、どうやら勘定組頭という仕事と関係があった。 諸大名が幕府になにかを依頼するとき、窓口といえば勘定組頭で、その際、贈り物をするのが事実上の習わしだった。とくに田沼意次は新規事情を次々と進め、宗次郎も蝦夷地の開発やロシアとの交易など、意次が検討する事業にかかわりをもっていた。田沼時代の汚点とされるのが、新規事業に関して賄賂を受け取る人間が増えた点だが、宗次郎はまさにそういう窓口だった。 身請けしてくれた客は斬首に 土山宗次郎は実際、吉原でかなり豪遊していた。戯作者として名高く、本職は幕府の御家人である大田南畝とつるむことも多かった。そのための費用は、勘定組頭の職務にからんで手にした不正な金だったといわれる。結局、天明6年(1786)8月、10代将軍家治の死とともに田沼意次が失脚すると、しばらくして、宗次郎には公金横領の嫌疑がかけられる。誰袖を身請けして、およそ3年後のことだった。 宗次郎は行方をくらまし、しばらく戯作者の平秩東作の庇護のもと、武蔵国所沢(埼玉県所沢市)に潜んでいた。東作は宗次郎の指示のもと、蝦夷地の調査を行っており、その関係があってのことだろう。そのとき宗次郎は誰袖を連れていたようだ。1,200両で買い取った女性を、それなりに大事にしていたのだろう。 しかし、結局は発見され、天明7年(1787)12月5日、切腹することも許されずに斬首された。その後、誰袖がどうなったのか、記録はまったく残っていない。『べらぼう』で彼女が望んだように蔦重が身請けしていれば、もう少し幸せになれただろうか。 香原斗志(かはら・とし) 音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。 デイリー新潮編集部