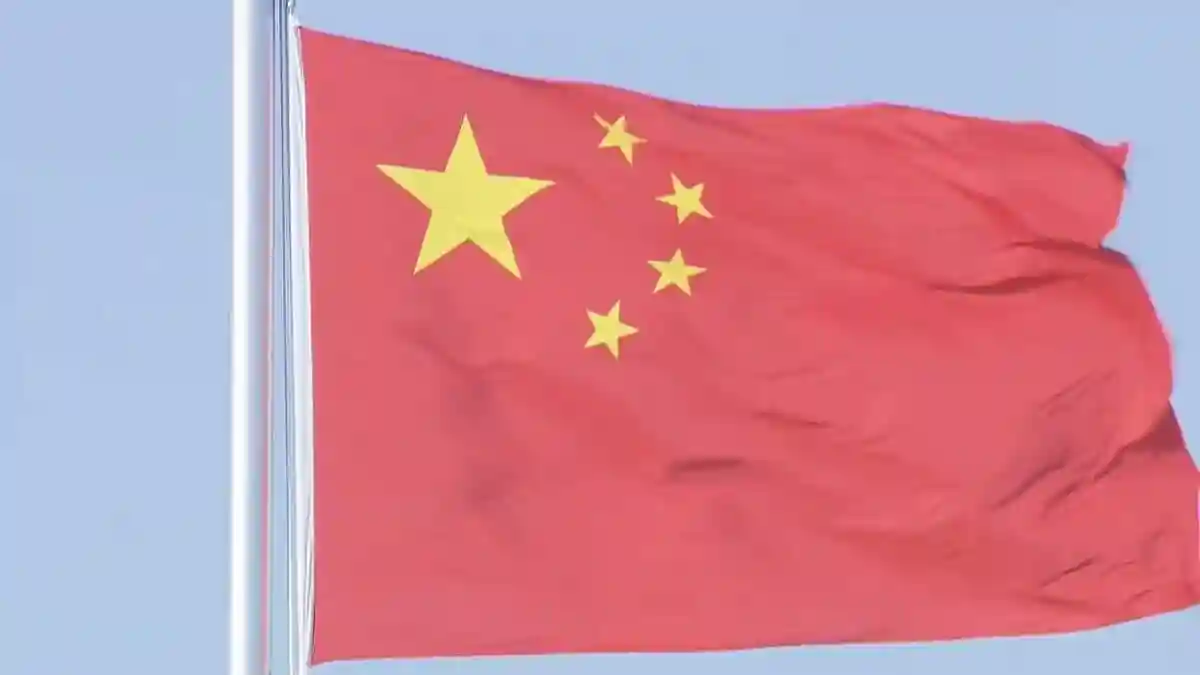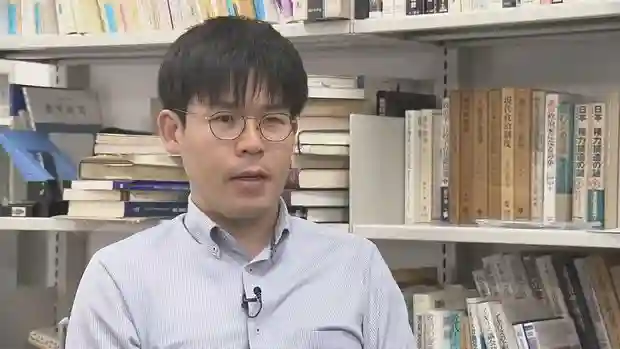
今年の東京都議会議員選挙と参議院選挙に向けて、選挙やSNSの情報をめぐる様々な課題や疑問について、各分野のスペシャリストに話を聞くシリーズ。 第5回のテーマは「選挙ハックは防げるって本当?」。選挙制度に詳しい日本大学・安野修右准教授に聞きました。 ■“選挙ハック”はなぜ起きる? —選挙制度を金儲けや売名などに利用する、いわゆる“選挙ハック”がいま課題になっていますが、なぜ起きるのでしょうか? 日本大学・安野修右准教授 (選挙ハックの)典型的な事例というのは、例えば昨年の都知事選におけるポスター掲示場のジャックであったりとか、同じく昨年の兵庫県知事選挙における2馬力選挙ですね。 公職選挙法はこういう、何て言うんですかね、選挙ハック的なあるいはもっと言えば、新規参入的なものに関して、非常に強固で幾重にもわたるような防護壁をずっと設けているんですね。 それを設けてきたことによって、なかなか有権者の人にとっては、既存の選択肢にしか投票ができないような状況になっていたんですけれども、それがもういよいよ掘り崩されて、突破をされている形で解釈をするというのが、おそらく正確な理解なんだと思います。 現時点において、既存の政治勢力の弱さが表れているという意味では、ある程度仕方がないことなのかなと思います。 ■“選挙ハック”への対策は? —選挙ハックなどをめぐり、どのような対策が必要だと考えますか? 対症療法的な方法はいろいろあると思いますけれども、根治は難しいと思います。対症療法的な方法として考えられるものは、例えばSNSとか動画のサイトに関する収益を停止させたり、ということですよね。 あるいは、他にも誹謗中傷に対する、刑事罰則を強化したりとか、別に行政罰則みたいなものを新設したり。そういった方法をとるということも、できるのではないかと思います。だから現行の法の枠組みでやれることは多少あると思うんです。 しかしながら、今起きている問題というのは、基本的に有権者の支持というものがある程度あってということですよね。その人たちがどういう意見を持っているのか、政治に対してどういう不満があるのかという、意見をまずちゃんと聞くということが必要なのではないかなと思います。 ■法改正の実効性は? —今年公選法が改正されましたけれども、実効性はどのぐらいあるとお考えですか? (実効性が)あってお守りのようなものだと思いますね。確かにポスター掲示場に対するその(枠の)売買とかですよね。その他、公序良俗に反するようなそういうものを、制限する規定が加えられたので、多少その点では実効力を上げるとは思いますけれども。 しかしながら、政見放送にも、そういうような規定があっても、眉をひそめるようなものも中にもあったりするわけですよね。そう考えた時に、なかなかポスターだけ(新たな)規定を設けてうまく回るとは考えられないと思います。 ■有権者はどう向き合うべき? —これから私たち有権者は、どんなことに注意を払っていくべきだとお考えですか? 今の世の中というのは目に見えない、あるいは形も分からないようなそういう情報とか、ものがあふれすぎていて、そういう世の中だと思うんですよね。 なので、今は立ち止まって考えてみるべき必要があるとすると、自分の身の回りに起きている政治とか、自分で関心を持ってみたりとか、主体的に情報を取ってみたりとか。 自分の目で見たことを判断するという、そういう態度を取るということが、ひとつ重要なのかなと思いますね。 ◇ ◇ ◇ 選挙にまつわる候補者の発言や動画などで、偽の情報や誤った情報と思われるものがあれば、「日テレ情報提供サイト」に情報をお寄せください。いただいた情報のうち、特に選挙に影響を与えそうなものについて、日本テレビ報道局が検証します。