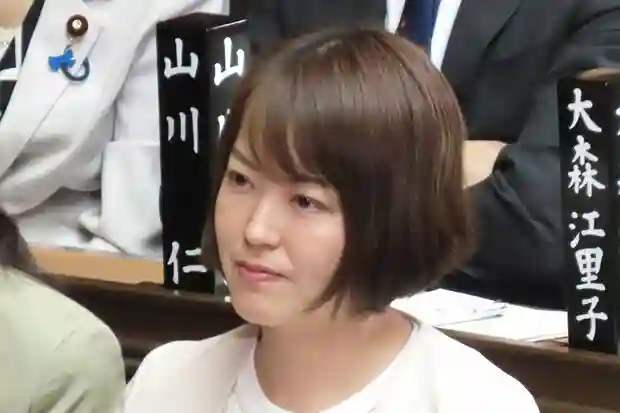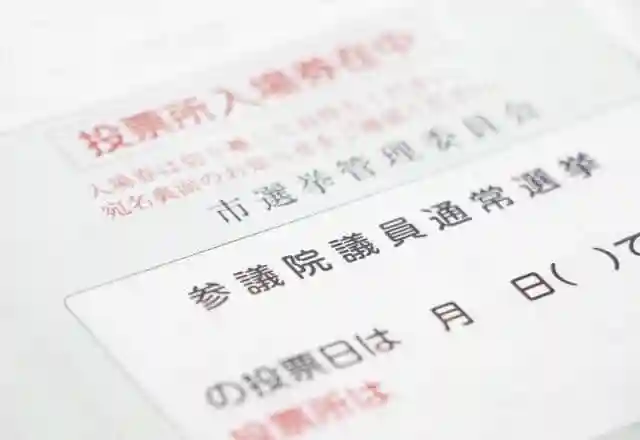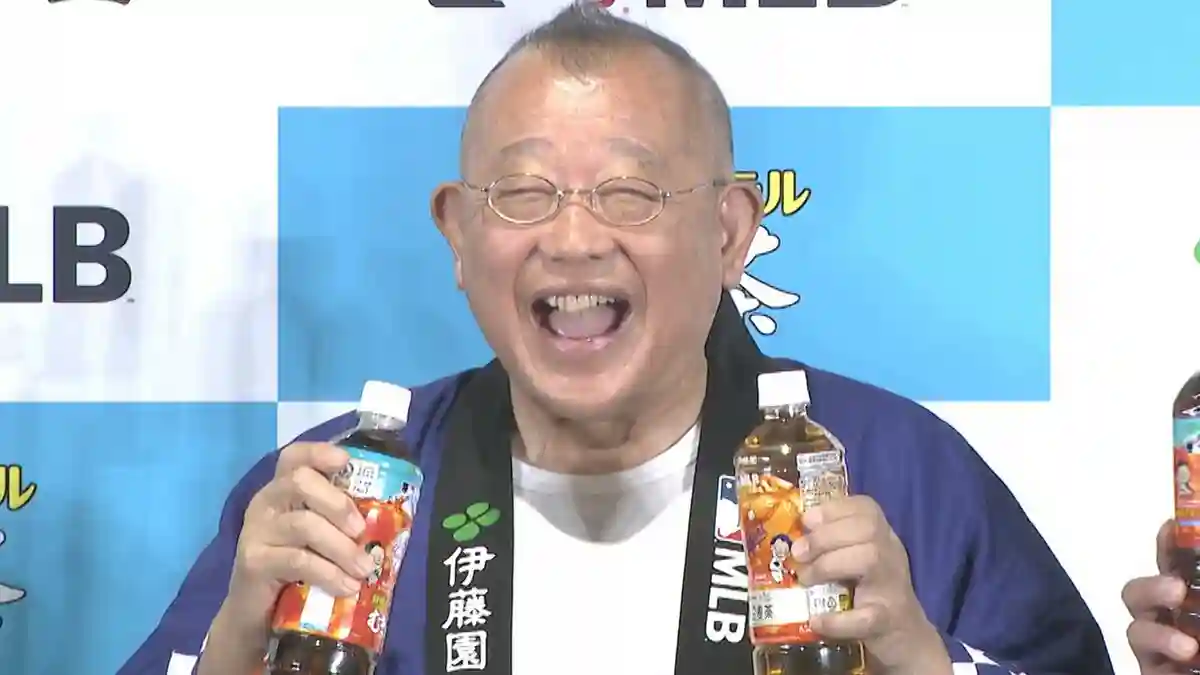おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は? 住まいは? 親の介護は? お墓はどうしよう? 日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか? 合理的で節約を重んじているのか? 親子関係はどのようなものだろう? 日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第34回 『「ボランティア活動」で老後も生き生きと! 「現役時代」に身に着けたスキルを駆使して「引退後の人生」も華やかに』 より続く。 窓から顔を出す高齢者 ドイツを観光しているだけだと意識しないかもしれませんが、少し長めに住んでいると、気づくこと。それは街中や住宅街を歩くと、窓から顔を出しているおじいさんやおばあさんがいることです。窓台(窓敷居)にクッションを敷いて腕を乗せ、身を乗り出すようにずっと外を見ている高齢者、特に男性をドイツではよく見かけます。 私も住宅街を散歩していて、「この家の花はきれいだなあ〜」なんて見上げた瞬間、窓から顔を出したおじいさんと目が合うということが何度かありました。 ドイツでは、知らない人同士が会話をすることは珍しくありません。そこですかさずこちらから「こんにちは。素敵なお花ですね」なんて話しかけると、先ほどまでブスっとしていたのが嘘のように、フレンドリーな笑顔が返ってくることもあります。 ドイツのきれいな家は「監視社会」の産物? ドイツの一般論でいえば「窓辺の高齢者」の評判は決して良くありません。近所の出来事を随時観察し、記憶し、時には記録し(!)、集合住宅の場合、その詳細を管理会社に「告げ口」するという「勝手にひとり警察」をやっている高齢者も少なくないからです。 「子どもが中庭で大声を出していた」「鬼ごっこを30分もしているのは長すぎではないか」などといった「子どもの騒音」に関連するクレームに始まり、ご近所の帰宅時間を注意深く監視し、「あの人の自動車は日曜日の朝には駐車場にあった。旅行から帰ってきているはずなのに、日曜日のミサに行かなかった」などと言い出す人も。 「誰々さんは何年か前に買ったばかりなのに、先日また新しく車を買った」など、どう考えても妬みだとしか思えないものもあります。そこに外国人嫌悪が加わると、もう目も当てられません。 「いつもスカーフで頭を覆っているあの奥さんは、なぜあんなに子どもの数が多いのか」などという発言も多々あります。そしてなぜ「人の子だくさん」が気になるのかというと……やはり暇さえあれば窓の外を眺めているから「一言、言いたくなる」わけなのです。 「ドイツの家は外から見ても中から見てもきれい」という日本人旅行者の感想どおり、確かにマメに窓ふきをし、窓辺に花を飾り、外観の美を追求している人は多いのです。しかし私は、「きれいな理由は個人の美意識だけではない」と感じます。 「自分が人の家を見ているから、人も自分の家を見ているだろう」 その思いからせっせと窓を磨いて、明るい色の花をベランダや窓に飾る……。ドイツの家の外観がきれいなのは、もしかしたらある種の監視社会だからかもしれません。 一軒家が建ち並ぶ住宅地では、近隣住民から「外観や庭の手入れが行き届いていない」とクレームが入ることさえあります。そんなこんなで、窓辺の花も窓に張り付いているおじいさん・おばあさんも、「ドイツの風物」ではあります。 『「あなたは本当に人に慕われていますか?」…ドイツの日常から学ぶ、人と人のつながりの大切さ』 へ続く。 【つづきを読む】「あなたは本当に人に慕われていますか?」…ドイツの日常から学ぶ、人と人のつながりの大切さ