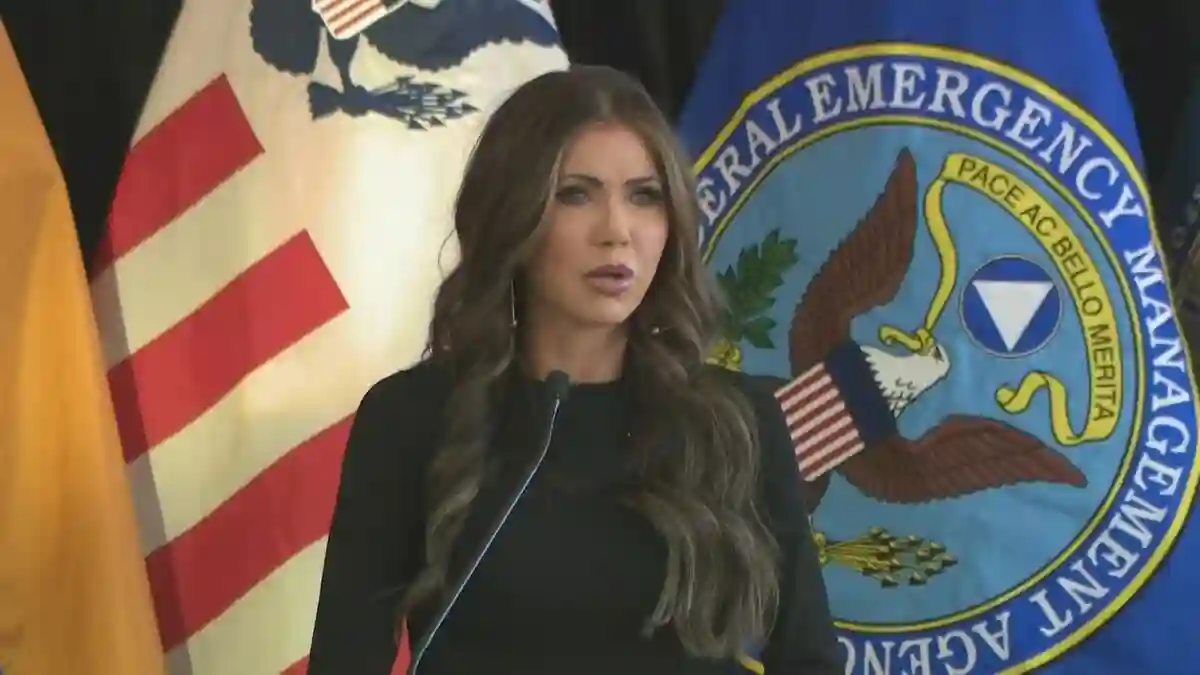障害年金の「不支給」の増加が問題になっている。金銭面での支援がなくなってしまうのは、もちろん経済的に大打撃だ。だから障害年金は重要なのだが、公的な経済的支援にはお金以上の「意義」があることは意外と認識されていない。 精神保健福祉の専門家で、『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』など多数の著作がある青木聖久教授(日本福祉大学)が、「障害者にとっての経済的支援」が持つ意味をあらためて問い直す。 制度の「目次を知る」ことが大事 近ごろ障害年金制度がニュースなどでよく話題になっています。今回の記事では、障害年金を主な例に取り上げつつ、 ●経済的支援の受給を阻む壁を異業種連携によってどう乗り越えるか ●制度をどのように人間味あふれるかたちで活用できるか を考えてみたいと思いますが、そのまえに制度の全体像を押さえるところから始めましょう。 日本には障害年金のような、「経済的支援制度」がいろいろあります。ひとつひとつを知るのも大事ですが、諸制度を体系として大づかみにすることも大事です。全体像が明確になり、それによって部分もよく見えるようになるからです。 たとえば私は既刊『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』では次のようなインデックスを作成しました。 ひとつの例ですが、こんなふうに「目次を知る」のが大事なのです。この点については後でまた触れるとして、ひとまず別の角度から、あらためて経済的支援制度全体の体系をまとめてみることにします。 経済的支援の制度がよって立つ「3つの根拠」 経済的支援制度を成り立たせている根拠には3つあります。制度を運営している主体と言い換えることもできますが、その3つとは、(1)法律、(2)自治体、(3)各企業です。たとえば障害年金は法律(国民年金法と厚生年金保険法)にもとづいてできている国の制度です。だから日本国内であれば、どこに住んでいても同じように適用されます。 ところが地域ごとに事情は異なりますから、当然、法律だけでは不足する部分が出てきます。そこをカバーするのが自治体、すなわち都道府県とか市町村です。自治体は条例や要綱などを定めることで独自の制度を設けます。 「医療費助成」がいい例です。既刊ではその全体像を、下のようにマンガでまとめていただきました。最後のコマの一覧表が大事です。 表で「4」の番号をつけられた「福祉医療」を、〈聞いたことがない〉と思われた方がけっこういるのではないでしょうか。これは市町村が実施している制度で、障害を抱えている人(この場合は精神障害のみならず、身体障害、知的障害も含みます)が負担する医療費を一部または全て肩代わりする仕組みです。 たとえば岐阜県には42の市町村がありますが、精神障害者保健福祉手帳で1〜2級をお持ちの方であれば、通院や入院共に、医療機関を受診する際は全科無料になります。岐阜県内であれば、どの市町村住んでてもそうなるのです。東京都ではあり得ないことですが、そんな仕組みをつくったのは誰なのかというと、それぞれの自治体です。 そして最後に、各企業による障害がある方向けのサービスがあります。そのなかには経済的な制度も含まれているのです。企業は独自の規定をつくって制度を運営しています。新聞などでご覧になった読者も多いことと思いますが、今年からJR6社が、精神障害がある方への運賃の割引きを開始しました。 九州の西鉄、千葉の京成電鉄など、地方の私鉄ではすでに厚い支援サービスを設けているところもありますから、それに比べるといささか遅ればせではあります。しかしながら、とにかく割引制度が開始されたのは進歩と言えるでしょう。 「収入」「支出」の軸でわけて捉えてもいい このように、3つの実施主体を軸に制度をとらえることもできますが、別の角度、すなわち「収入を増やす」のか、それとも「支出を減らす」のか、という収支の面から制度を大づかみにすることもできます。すなわち、次のような具合です。 ●収入を増やす(所得増額) 障害年金、各種の手当(特別児童扶養手当、障害児福祉手当)、生活保護など ●支出を減らす(出費軽減) 高額療養費制度、自立支援医療、自治体の医療費助成など 障害者手帳はこれらの制度につながる「入り口」ともいえる制度ですが、交通運賃や施設利用料などの減免サービスがついてくるという点から見れば「支出を減らす」制度のほうに分類することもできます。 このように2つの視点(実施主体/お金の流れ)があることを覚えておくと、諸制度を整理してとらえやすくなります。 ここで少し余談が入りますが、以上のような制度の全体像について、近々お話する機会をいただけることになっています。概要を貼りつけておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。 ● セミナー名 人間味あふれる折り合い点の創造〜精神障がいがある本人や家族との37年間の追体験を中心に〜 ●開催日時 2025年7月26日(土)13:30〜 (開場13:00〜) ●開催場所 主婦会館プラザエフ「カトレア」(〒102-0085東京都千代田区六番町15番地) ●申し込み https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAMqXyxgQutClIzmCOcNhl36UGVSh1Nuv7TtiZHHrLqjBmTA/viewform ●プログラム概要 ≪第1部≫記念講演会 13:40〜15:00 「人間味あふれる折り合い点の創造〜精神障がいがある本人や家族との37年間の追体験を中心に〜」講師 青木聖久先生(日本福祉大学 福祉経営学部 教授) ≪第2部≫トークセッション 15:20〜16:30 「生きづらさと人間らしさ」堀合悠一郎氏(認定NPO法人さざなみ会理事長)× 青木聖久先生 ≪第3部≫懇親会 17:00〜19:00 希望者のみ。会費は懇親会場にて申し受けます 【参考ウェブサイト】 https://nfu-alumni.netnfu.ne.jp/topics/kanto_hokushinetsu/000801.html 制度の「基準」と「論点」とは何か 話をもとに戻しましょう。 制度を知る上では「基準」と「論点」を知ることも欠かせません。「基準」とは誰が対象か、ということであり、「論点」とは支援すべき問題をどこに設定するか、ということです。ここでは障害年金と生活保護を対比させてみましょう。すると「基準」「論点」がなぜ重要かがわかります。 障害年金と生活保護は、知っていなければソーシャルワーカーの業務が成り立たない、最も基本的かつ重要な制度でもありますから、取り上げないわけにはいきません。 あくまで仮の話として、ここに精神障害を抱え、経済的にも困窮しているAさんという方がいるとします。この方には、仲の良い同居している兄(Bさん)がいます。Bさんは成功した実業家で、年収は数億円を超える資産家です。 折からの物価高もあり、Aさんは食べる物にも事欠くようになってしまいました。生活保護を受けるべきではないかと考え始めますが、決心がつかないのでBさんに相談します。 「兄さん、生活保護を受けようと思うんだけど」 驚いたBさんはこう答えます。 「すまん、ぜんぜん気づけなかった。十分な額を毎月わたすから、俺に頼ってくれ」 このような状況ですと、Aさんが生活保護を受けるのはちょっと難しい可能性があります。というのも、生活保護の「基準」、すなわち支援対象は、個人ではなく世帯だからであり、また、「論点」、すなわち支援すべきとされる課題は困窮だからです。 Bさんに支援する経済力がない(あるいは支援する気がない)ならば、Aさんは生活保護を受けられるでしょう。しかしBさんには十分な経済力があり、弟を支援する意志もあります。Aさん・Bさんをひとつの世帯とみれば困窮しているとは言えないため、生活保護の前に家族内扶養でやりくりすることを勧められるでしょう。 障害年金の持つ大切な意義とは 一方、Aさんが障害年金を受給したいと思った場合は、どうなるでしょう。仕送りの可能性があるから不支給になるかというと、そのようなことは法律上あり得ません。なぜなら障害年金の基準は「個人」、論点は「障害状態」だからです。 仮に兄のBさんの資産がいまの100倍あっても、あるいはAさんが相応の資産を保有していたとしても関係ありません。Aさんという人物が障害を抱えているのであれば、その障害状態に応じて、障害年金を受給できる可能性は常にあるのです。 障害年金は「経済的支援の中核」と言われることも多いのですが、その理由はここにあります。基本的に障害を抱えていれば、誰でも受給できる可能性がある。そこがポイントです。 もちろん、「障害があること」以外にもいくつかの要件を満たさなければ障害年金は受給できません。この点については長くなるので今回は省略します(知りたい方は<参考>に掲げた過去の記事をご覧ください)。いずれにしても大事なのは、障害が主な論点になるという点です。 <参考>著者の過去の記事から 【希望者必見】専門家が超わかりやすく解説。障害年金「受給に必要な3つの要件」満たしていないと受給不可に。 受給によって増える選択肢 精神疾患や発達障害などの「精神障害」を抱えている人は、一見すると不自由があるようには見えない場合が多く、しばしば世間から誤解を受けながら、「無理して働く」か「働くのを諦める」かの二択を迫られるような状況に陥ってしまうこともあります。 しかし障害年金が受給できれば、“障害年金を基礎収入に据えて、それでも足りないぶんだけを働いて稼ぐ”という無理のない「第3の働き方」という選択肢ができるわけです。このように、「経済的支援を受けるということ」は、単に使えるお金(可処分所得)が増えるということだけを意味するわけではありません。 人生の選択肢を増やす意味でも、あるいは当事者の精神的支えになるという意味でも、いろいろな意義があるのです。このことは、ぜひ押さえていただきたいポイントです。 これもまた仮の話ですが、たとえば「まだ現役で働いている親と同居しているが、将来のことを考えて〈独立したい〉と望んでいる精神障害の当事者」がいたとします。この当事者が生活保護を受けるのは難しいでしょう。しかし、障害年金を受給できれば自己実現できる可能性が出てくるわけです。 あるいは「生活保護を受けられるほどにまで追い詰められてはいないけれども、困窮している精神障害の当事者」を考えてみましょう。こうした方も、障害年金を新たに受給することで安心して生活できるようになるかもしれません。こんなふうに、結果(お金がもらえる)が似ているようであっても、論点が異なる制度があるというのは大切なことなのです。 近ごろ、障害年金の不支給件数が増えてきていることが新聞などで問題になりましたが、大きなニュースになる背景には、そういう事情もあるわけです。障害がある方にとっては、貴重なライフラインがひとつ、絶たれやすくなったようなものなのです。 ※この記事は2025年2月9日に大正大学社会福祉学会第48回大会にて行われた著者講演に大幅に加筆して作成しました。 中編記事『【専門家が解説】支援の申請から相続の手伝いまで…「異業種連携」でこんなに広がる障害者福祉の可能性』へ続く。 実際の健康寿命はもっと長かったと判明。にもかかわらず70代で老けこむ人に共通する思いこみとは…