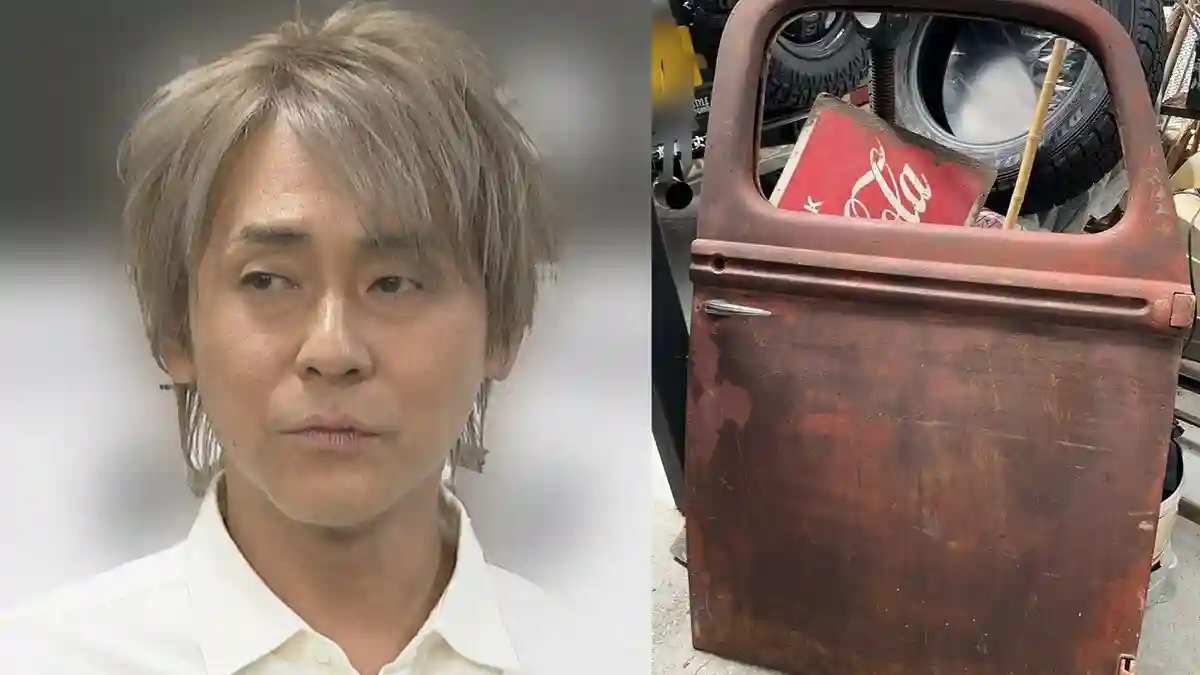プロ野球はオールスター休みまで2週間。阪神が頭ひとつ抜け出したセ・リーグとは対照的に、パ・リーグは上位3チームが1ゲーム差以内にひしめく大混戦となっている。 ご存じの通り、今年の交流戦はパ・リーグがセ・リーグを圧倒。ペナント争いで、このまま阪神が独走するようなら、「熱パ」に対して「冷セ」と呼ばれる可能性も出てきそうだ。 【八木遊/スポーツライター】 *** 【愕然】これじゃ見ててもつまらない? 「投高打低」が一目でわかるセ・パ両リーグの投打成績表 5年で1試合2得点以上も減少 交流戦で8勝10敗と負け越した際は、阪神・藤川球児監督の采配に対する批判の声も少なくなかった。ところがリーグ戦再開後は初戦こそ落としたが、その後は8連勝中。現在、2位の広島に6.5ゲーム差をつけており、オールスターまでに阪神が優勝マジックを灯らせる可能性も出てきている。 セ・パ両リーグでチーム防御率1位の阪神・藤川監督、日本ハム・新庄監督 8連勝を支えたのは、間違いなく阪神の投手陣だ。連勝中の8試合中4試合で相手打線を零封し、与えたのは5点のみ。今季のチーム防御率はなんと1点台に突入している。リーグ1位の得点数を誇る打線も切れ目がなく、交流戦の期間に聞かれた藤川監督に対する不満の声も静まりつつある。 一方で、一部のファンから漏れ始めたのが、あまりにも得点が入らない試合ぶりに対してだ。それは鉄壁を誇る阪神の投手陣に対してというより、プロ野球界全体に対してのものである。 プロ野球の「投高打低」は今年になって突然始まったわけではない。コロナ禍で120試合制となった2020年以降の1試合平均得点を見ると以下のように推移している。 2020年 8.23 2021年 7.51(−0.72) 2022年 7.14(−0.37) 2023年 6.97(−0.17) 2024年 6.57(−0.40) 2025年 6.11(−0.46)※7月6日現在 ※()内は前年比 2020年は両チームが1試合当たり4点ずつを奪い合っていた。ところが、翌年の21年にガクンと下がると、それ以降も緩やかにだがその流れは止まらず、今季は6日時点で6.11まで落ち込んでいる。つまり、5年前と比較すると、1試合平均で2得点以上、1チームあたりで1得点以上も減少しているのだ。 個人成績にも「投高打低」が反映 数年前から言われていた「投高打低」の波は一向に収まる気配を見せないが、各選手の成績にもそれは反映されている。 3割打者は両リーグ合わせて8人。これは昨季の3人から増えてはいるが、規定打席に達した打者の数が両リーグ合わせて41人しかいない。5年前の53人、昨季の47人と比べても減少中といえるだろう。それだけ、レギュラーを張り続けるほど打てる野手が少なくなっているからではないだろうか。 投手の防御率ランキングはさらに顕著だ。現時点で規定投球回数に達しているのは両リーグ合わせて26人いるが、このうち半数を超える14人が防御率1点台をマークしている。防御率4点台はDeNAのバウアー1人だけである。 ほんの数年前には、規定投球回数に達する投手が少ないあまり、規定の引き下げが議論されていたこともあった。いまや、「6回以上を投げ自責点3以下」のクオリティースタートではなく、「7回以上を投げ自責点2以下」のハイクオリティースタートが、先発投手にとって“好投”の基準と化している。 上原浩治氏も現状に警鐘 「投高打低」になっている根本的な原因の一つとして考えられるのが、プロ野球の統一試合球が“飛ばない”問題である。 日本野球機構(NPB)や公式球を製造するミズノ社が公に認めているわけではないが、昨年の春以降、現場の選手たちからは「ボールが飛ばない」という声が出続けている。 そんな状況に声を上げ始めた著名なOBもいる。例えば元メジャーリーガーの上原浩治氏は、「Yahoo!Japan」に掲載された自身のエキスパート記事(6月26日付)で、「野球は『点取りゲーム』で『2−1』の投手戦よりも、同じ接戦でも『5−4』『6−5』のように点数が入ったほうが盛り上がる」と持論を展開。その上で、「もちろん、息詰まる投手戦も見応えはある。エース級同士の1点勝負は球場にも緊張感が漂う。しかし、どの試合でも点数が入りにくいとなれば、面白みに欠けてしまう面は否めない」と、行き過ぎた「投高打低」の現状に警鐘を鳴らしているのだ。 さらに「日本のファンに楽しんでもらうために、ボールを少し飛ぶように規定を変えてみるのはどうだろうか」「少しの変化がスタジアムの盛り上がりにつながるのであれば、検討の余地はあっていいと思う。皆さんはどう考えますか?」と、ボールの変更をファンに問いかけている。 上原氏の忖度のない意見には当然、反対の意見もあるだろう。しかし、多くのファンにとって野球観戦の醍醐味は、応援するチームが得点した際の歓喜の瞬間にあるのは間違いない。5年前と比べ、その機会が減っているのは明らかで、不満が漏れてくるのは当然なのだ。 DH制の有無も「投高打低」に拍車? また、「投高打低」がより顕著となっているのが、セ・リーグの方だ。今季の両リーグの1試合平均得点を比べると、パ・リーグの6.39に対して、セ・リーグはわずか5.82。両者の間には小さくない差が生まれている。 その理由として考えられるのが、やはり指名打者(DH)制の有無である。日本ハムのレイエスや、ソフトバンクの山川穂高のように、DH制を採用しているパ・リーグの各球団には“打つ専門の選手”がいる。もちろん、セ・リーグ球団の本拠地で戦う際はDH制を使えないハンデはあるものの、それも年間わずか9試合だけだ。 さらに、DH制が間接的に投手の能力アップに寄与している面もある。9番打者がほぼ自動アウトのセ・リーグに対して、パ・リーグの投手は、普段から常に9人の打者と対峙しており、気を抜くことが許されない。これも長い目で見ると、パ・リーグ投手のレベルアップにつながっているという声もある。 ここ数年の交流戦はセ・パがほぼ互角の戦いを見せていたが、今季はふたたびパ・リーグが圧勝。これを機にセ・リーグのDH制採用の声が高まったのは間違いない。 また、高校野球や大学野球にもDH制採用の波は押し寄せている。日本高野連は早ければ来年の選抜からDH制の導入を検討中。また、東京六大学野球も来年からの導入を決定済みだ。セ・リーグにはいまだDH制に否定的な球団も多いが、外堀は埋まりつつある。 上原氏が言うように、行き過ぎた「投高打低」はファン離れにつながりかねない。今こそ、飛ぶボールやセ・リーグにおけるDH制導入の議論を活発化させる時ではないだろうか。 八木遊(やぎ・ゆう) スポーツライター 1976年生まれ。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。 デイリー新潮編集部