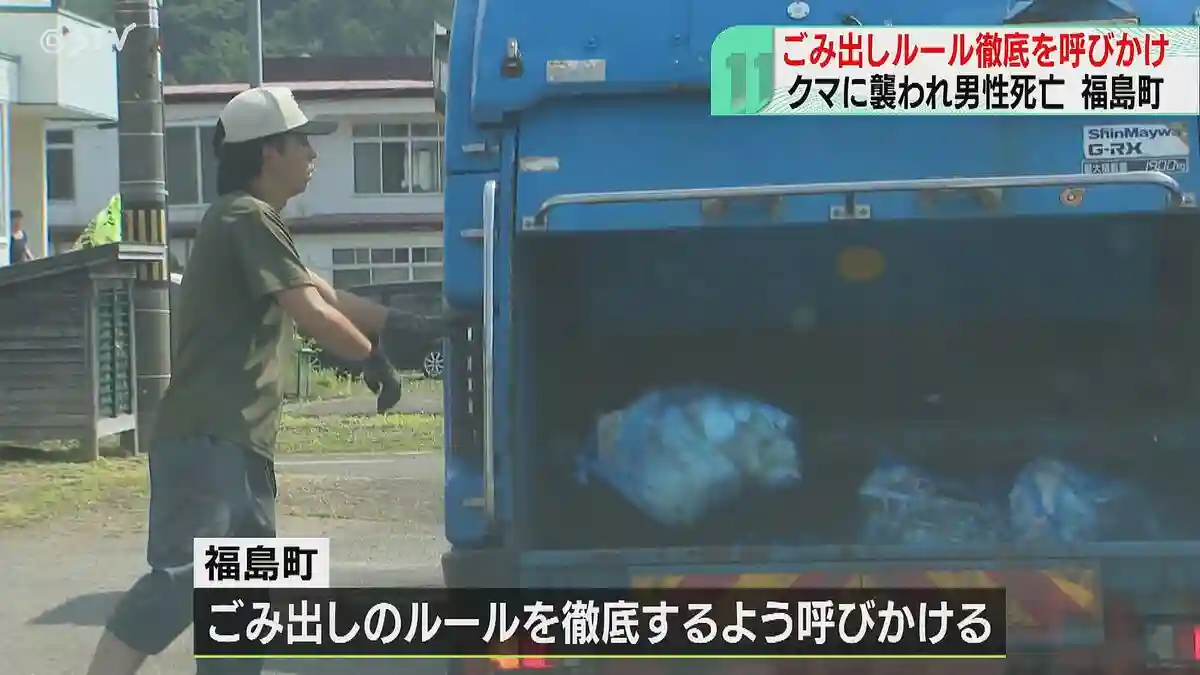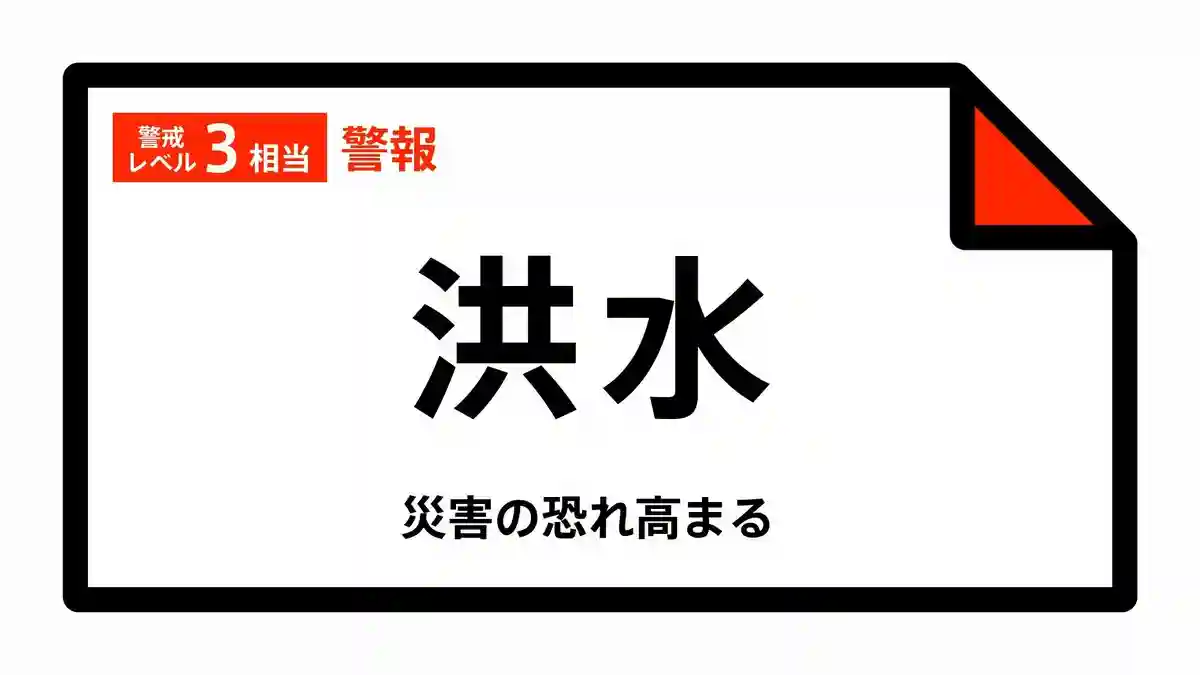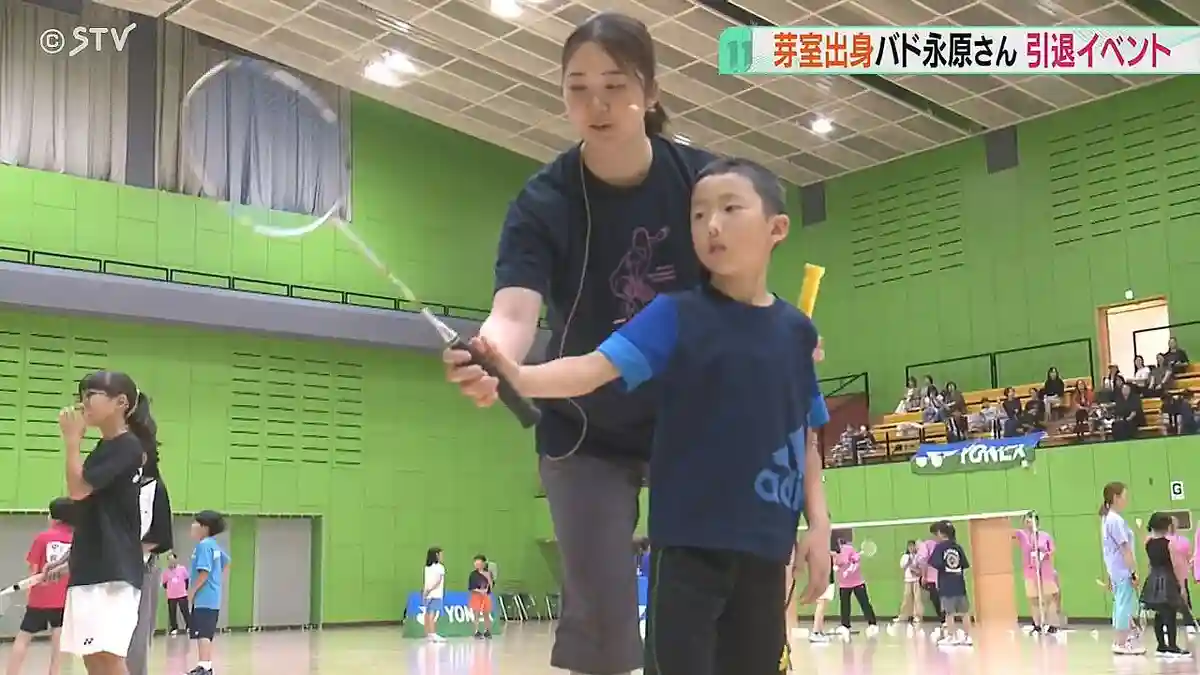「割り算の余り」について この話題に入る前に、一言述べておきたい関連する話題がある。4月16日の朝日新聞朝刊に掲載された記事『一部私大の授業「義務教育のようだ」財務省「助成見直しを」』において、数学に関して「四則演算や方程式の取り扱い」の指導が含まれている。 4月15日に財務省で開催された財政制度分科会の資料によると、正確にはやり玉に挙がった数学に関する内容は次の4つである。 (ア)四則計算、(イ)割合%、(ウ)約数と倍数、(エ)方程式と不等式 実際、筆者は桜美林大学での最後の10年間あまりは、さまざまな授業のほかに「数の基礎理解」という授業を設けて、「算数+α」の内容を講義し、定年退職後に授業内容をまとめた書『昔は解けたのに……大人のための算数力講義』を上梓した。本稿での「割り算の余り」および「貧困」については、この書を参考にして述べるものである。 まず、 7÷3=2…1(…は余りの意) 7(割られる数)−3(割る数)×2(商)=1(余り) を見ても分かるように、 「余り」=「割られる数」−「割る数」×「商」……(*) という式が基礎としてある。そこで、割り算の余りは、上式を用いて計算すれば間違うことはないだろう。ところが、残念ながら次の例題を大人に行ってもらうと、多くが間違えてしまう。 例題 7.232÷8.81の商を小数第2位まで計算して余りも求めよ。 解説:なぜ多くが間違えてしまうかについて述べると、とりあえず下図において、縦の点線と最下段にある点線のない筆算を行うだろう。そして、商は「0.82」で、余りは「0.78」とか「78」と答えることが多い。 商は正しいが、正しい余りは「0.0078」である。実は、「余り」のある「小数」÷「小数」の計算は、90年代辺りまではそれなりに小学校で学んでいたが、その後は学んでいない状態である。そのため、「やり方」に頼る学習法で学んできた人にとっては、割り切れる場合の「小数」÷「小数」の筆算に頼ってしまうようである。 「余り」に関する基礎として重要な式(*)に戻れば、上の例題での「余り」は、 7.232−8.81×0.82=0.0078 と計算すれば間違わないはずである。 筆算での「余り」に関して間違わないようにする要点を以下、述べよう。 筆算での「余り」を間違えないようにするには 準備として、次の6つの計算式を確認する。 700÷300=2…100 70÷30=2 …10 7÷3=2 …1 0.7÷0.3=2… 0.1 0.07÷0.03=2…0.01 0.007÷0.0003=2…0.001 上の6つの計算式が示していることは、割られる数と割る数が共に10倍、100倍、1000倍になれば、商は同じでも、余りはそれぞれ10倍、100倍、1000倍になっていることである。 したがって「小数÷小数」の割り算を考えるとき、小数点の位置をずらして「小数÷整数」の割り算を行うまではよいが、余りの小数点の位置はずらした分を戻した位置になることに注意しなくてはならない。 それが、「やり方」だけで学んできた方々が間違える要点なのである。上で述べたことを「数の基礎理解」の中でも堂々と解説した次第である。 「貧困」の定義とは?ニュース報道に思うこと 2016年8月18日放送のNHKニュースで、実際に取材に応じた「貧困女子高校生」が取り上げられた。それを端緒に、国会議員をも巻き込んで、異なる立場の人達の間で意見の対立が起こった。「大した貧困ではないじゃないか」、「この状態で勉学を続けるのは困難ではないか」、「日本は格差問題にもっと真剣に取り組むべきだ」などの意見がネット上を駆けめぐったのである。 偶然にも、将来このようなトラブルが起こることを危惧して「相対的貧困率」について定義からまとめたことがある(拙著『論理的に考え、書く力』光文社新書、2013年)。 まず、貧困には絶対的貧困と相対的貧困があり、前者は、必要最低限の生活水準が満たされていない状態、すなわち衣食住に関しても困っている状態を指す。 一方、後者に関しては以下のように捉える。 世帯の可処分所得とは、世帯の所得(世帯員全員の年間所得の合計)から税金と社会保険料を差し引いた残りの所得のことである。 次に、世帯の1人当たりの可処分所得を定義するが、世帯には1人もあれば3人もあれば4人もあるように、その構成人数の世帯員数はいろいろ異なるのが普通である。単純に思い付くことは、世帯の可処分所得を世帯員数で割ることであるが、同じ家の中での生活では共用するものも多く、世帯員数で割ると割る数が大きくなり過ぎると判断できる。 そこで現在、国際的に広く採用されている「世帯の1人当たりの可処分所得」はOECD の「等価可処分所得」というもので、 世帯の可処分所得÷(世帯員数の正の平方根) という式によって与えられる。 √1=1、√2=1.414…、√3=1.732…、√4=2 なので、1人世帯、2人世帯、3人世帯、4人世帯それぞれの等価可処分所得は、世帯の可処分所得をそれぞれ1、1.414、1.732、2で割った商になる。 たとえば、夫婦共働きの2人世帯の可処分所得が1414万円の場合、その等価可処分所得は1414万円を√2で割って、1000万円となる。また、父・母と子2人の4人世帯の可処分所得が1000万円の場合、その等価可処分所得は1000万円を2で割って、500万円となる。 相対的貧困率の定義を考えてみる 次に国民全体の等価可処分所得を大小の順に並べて、その「中央値」の半分に満たない人達を相対的な貧困層と捉え、その割合をOECDの「相対的貧困率」と定義する。なお、いくつかのデータの中央値とは、それらを大小の順に並べたときの真ん中の値である。たとえば、奇数個のデータ 1、3、6、8、13、17、19 の中央値は8である。また、偶数個のデータ 1、3、6、8、13、17 の中央値は、真ん中にある2つの数6と8の平均値:7を、これらの中央値と定める。 厚生労働省発表のデータによると、1985年の日本の等価可処分所得の「中央値」は216万円で、その半分の108万円未満の相対的貧困率は12.0%であった。そして2009年の等価可処分所得の「中央値」は実質で224万円(名目で250万円)、その半分の112万円未満の相対的貧困率は16.0%に上昇した。 なお、名目値とはその年の等価可処分所得をいい、実質値とはそれを、1985年を基準とした消費者物価指数で調整したものである。 ここで注意すべきことは、豊かな国の「中央値」と貧しい国の「中央値」には、生活実感として相応な開きがある。ようするに、絶対的貧困と相対的貧困とはまったく別のものである。それをゴチャゴチャにして議論を展開したから、冒頭の問題がトラブルに発展したのだ。言葉の定義こそ、大切にしたいものである。 比例選挙の「ドント方式」はどのように決まる? 最初に具体例を使って、比例選挙のドント方式はどのようなシステムなのかを解説しよう。 当選者数が10人のドント方式による比例選挙があり、立候補政党はA, B, Cの3党であったとする。そして選挙での得票数は、Aが7080、Bが4920、Cが3840とする。 このとき、次のような表を考えてみる。 当選者が10人であることから、表の中の大きい方の数字から10個を選び出すと、太い線に囲まれた部分になる。その部分の数字の個数は、Aの下に5個、Bの下に3個、Cの下に2個ある。そこで、A、B、Cの当選者数はそれぞれ5人、3人、2人とするのである。 実際のドント方式による比例選挙では、立候補政党数も得票数も大きく異なるであろう。そして、当選人数を決定する表の中の商は、多くが割り切れない小数であり、また表の中の数字どうしが一致することはほとんどあり得ない。 そこで、以下ドント方式における重要な性質を証明するが、当選人数を決定する表の中の数字どうしは、すべて互いに相異なるものと仮定する。 ドント方式における重要な性質 上の表で示した選挙において、もしBとCが合併してDという新政党を作って選挙を行ったとする。そしてDの得票数はB、Cのそれぞれの合計であるとすれば、選挙結果はどのようになるだろうか。 それは次の表で示すように、Aは4人、Dは6人当選することになる。すなわち、BとCは合併効果としてプラス1議席あり、その分Aはマイナスになるのである。 上で述べたBとCの合併効果を一般化すると、次の性質が得られる。 性質:ドント方式による比例選挙で、2つの政党X、Yが別々に選挙を行うときの得票数をそれぞれx,yとし、また当選人数をそれぞれa,bとする。もしXとYが合併してZという政党を作り(他の政党は変更なし)、Zの得票数がx+yになるとすれば、Zの当選人数はa+bまたはa+b+1になる。 証明:先に、Zの当選人数はa+b以上であることを示そう。aまたはbが0のときは明らかなので、a≠0かつb≠0を仮定する。いま xb≧ya が成り立つならば、両辺にybを加えると xb+yb≧ya+yb となる。よって、 (x+y)/(a+b)≧y/b……(1) を得る。一方 xb<ya が成り立つときは、両辺にxaを加えると xb+xa<ya+xa となる。よって、 x/a<(x+y)/(a+b)……(2) を得る。(1)、(2)より、Zの当選人数はa+b以上である。 次に、Zの当選人数はa+b+1以下になることを示そう。いま y(a+1)≦x(b+1) が成り立つならば、両辺にxa+xを加えると (x+y)(a+1)≦x(a+b+2) となる。よって、 (x+y)/(a+b+2)≦x/(a+1)……(3) を得る。一方 y(a+1)>x(b+1) が成り立つときは、両辺にyb+yを加えると y(a+b+2)>(x+y)(b+1) となる。よって、 y/(b+1)>(x+y)/(a+b+2)……(4) を得る。(3)、(4)より、もしZの当選人数がa+b+2上になるならば、XとYが別々に選挙を行ったとき、Xがa+1人以上当選したか、またはYがb+1人以上当選したことになり、矛盾である。よって、Zの当選人数はa+b+1以下である。 上の性質と証明は拙著『新体系・高校数学の教科書(上)』に載せたものであるが、元々は30年ほど前に政治学を研究している方から質問をいただき、当時刊行した拙著に上記と同じ内容のことを書いた。 質問をいただいたとき、ドント方式の定義に戻って考えたのである。なお、表の中の複数の商が一致する場合の対応についても、当時の自治省に電話を入れて尋ねたことを思い出す。今から思うと、ずいぶんと迷惑な電話をかけてしまったと反省する次第である。 高校時代に習った「数学的帰納法」は、どんなときに使えるのか?「あみだくじの仕組み」から考えるその思考法