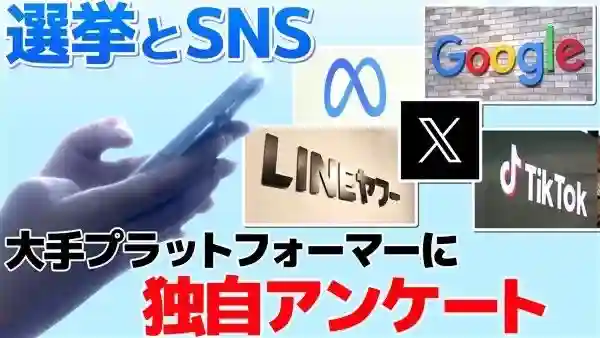
問題視されるようになったSNSに広がる選挙・政治をめぐる「偽誤情報」。与野党7党による協議会も6月下旬、参院選を前に、ソーシャルメディアを運営するプラットフォーマーに「偽誤情報」への対策などを求める共同声明を発表。法制化に向けた検討もはじまっています。 こうした中、日本テレビでは、東京都議会議員選挙や参院選にあわせて大手プラットフォーマー5社に独自アンケートを実施した。 アンケートを送ったのは、・Google(YouTube)・LINEヤフー(LINE/Yahoo! JAPAN)・Meta(Instagram/Facebookなど)・X・TikTok Japan(TikTok)の5社で、6月中に全社から回答があった。 後編となるこの記事では、SNS上の「偽誤情報」への対応について、プラットフォーマー各社がいま感じている課題を分析した。 ◇ ■「偽誤情報」は「深刻に受け止め」…ルールの見直しで対応 まず、選挙・政治コンテンツにおいて「偽誤情報」などが問題視される現状について、どう考えているのか。 Xは、選挙でSNSを活用することは「多様な意見の共有」や「公共の対話の促進」の観点で重要な役割を果たしているとした上で、ユーザーが信頼できる情報を得ようとするのを偽誤情報が妨害する可能性があることを「深刻に受け止めている」とした。一方、Metaは、「表現の自由をめぐる問題は、主観的・情緒的な議論ではなく客観的、科学的、法学的な研究に基づく議論が必要」とした。 一方、対策としてはこのような回答があった。 Googleは「信頼できるニュースへの投資」がこれまで以上に重要になっているとした。また、その他の社からは、リテラシー教育の促進やファクトチェック機関・有識者・報道機関など関係機関との連携の強化、利用方法について定めたルールの見直しが対策例として挙げられた。 ■カネ稼ぎ目的の悪質投稿を防ぐため…“政治・選挙コンテンツ全般の収益化停止”はあり?なし? 報酬をもらうこと、つまり収益化を目的とした悪質なコンテンツを防ぐため、政治・選挙コンテンツすべてで収益化を停止することについて意見を聞くと、そもそもそういったコンテンツを見分けることが難しいと指摘する声があった。 例えば、LINEヤフーは、「再生・閲覧数稼ぎとそうでないものの区別など様々な課題」があるとし、コンテンツが再生・閲覧数稼ぎで投稿されたものか否かを区別するのは難しいとした。また、Xも「政治や選挙に関するコンテンツは口で言うほど単純ではない」と指摘。 例として、料理について投稿するアカウントを挙げ、このアカウントが「物価高」について投稿した場合、「候補者の経済政策にかかわる政治・選挙コンテンツと言えるかもしれない」として政治や選挙をめぐるコンテンツの複雑性を指摘した。 一方、TikTokは、投稿した動画を通して報酬を得るためには、ガイドラインを守ったり、質の高いコンテンツを投稿していたり、一定の条件を満たす必要があるとし、「悪質なコンテンツが自動的に収益化される仕組みにはなっていない」と主張した。 ■課題は「ファクトチェック機関の定着」と「関係機関の連携」 選挙や政治におけるSNSをめぐって、一部のプラットフォーマーからは大きく2つの課題が聞かれた。 1つ目は、ファクトチェック機関をめぐる課題。投稿された情報が「偽誤情報」かどうか判断するときに参照するファクトチェック機関が十分に定着していないことを指摘したのだ。 定着が遅れている理由として、活動資金が足りていないことなどを挙げ、社会全体で支援する必要があるとした。また、ファクトチェックには専門性が必要だとして、「社会全体でファクトチェック機関をいかに育成し、定着させていくかを考えるべきだ」とした。 2つ目には、関係機関の連携の必要性だ。LINEヤフーは、偽誤情報について、「複数のプラットフォームにまたがって行われる可能性もある」と指摘。こうした偽誤情報の特徴から、「一部のプラットフォームだけが対処するのでは限界がある」とし「関係機関が連携する仕組みが必要ではないか」とした。 ◇ ◇ ◇ 【アンケート回答全文】※質問に対して回答がリンクしない場合は、無記載※2025年6月中に回答 ———選挙・政治コンテンツにおける偽誤情報やひぼう中傷の問題、どう受け止める? 感じる責任と今後の対応は? 【Google】情報を与えられた市民をサポートし、健全な政治的議論を促していく責任を負うと考えている。信頼できるニュースへの投資は、これまで以上に重要になっている。有識者にとって、信頼できる選挙のニュースや情報が最前線で届けられる場所であり続けている。 ガイドラインは、表明されている政治的見解、コンテンツの言語や生成方法にかかわらず、選挙を含むあらゆる種類のコンテンツに対して、すべての人に適用される。これには、ヘイトスピーチ、ハラスメント、暴力的で刺激の強い・技術的に操作されたコンテンツ、選挙の誤った情報に対するポリシーが含まれる。 例えば、次のようなコンテンツは削除される。他人に対して、脅迫や嫌がらせを呼びかけるもの、間接的または暗示的な脅迫を含むもの、身体的に誰かを脅迫するもの、文脈を無視した切りぬき動画の範囲を超えて、ユーザーを誤解させるような方法で技術的に操作または改変されていて、重大な危害をもたらす深刻なリスクを生じさせる可能性のあるもの。 度重なる違反があった場合、または悪質な不正行為が一度でも確認された場合は、アカウントが停止される可能性がある。YouTubeは、同じ90日間に3回の違反警告を受けたチャンネルは停止される。 【LINEヤフー】ユーザーや社会の声に耳を傾けながら、対策や周知啓発、リテラシー教育の推進に取り組んでいるが、今後も関係機関や有識者との連携を深め、情報空間の健全化に一層力強く貢献したい。安心で信頼のあるプラットフォームであり続けることを目指す。 予防施策として、「専門家・有識者など信頼性の高い意見の積極掲出」「ユーザー認証の強化」「情報リテラシーの啓発活動」などを行いつつ、事後対応としても「ファクトチェック関連団体支援」「Yahoo!ニュースが提供するコメント添削モデル」「コンテンツモデレーション」などの取り組みを行っている。 今後もプラットフォーム事業者として、運営のあり方の透明性を確保していくとともに、ファクトチェック機関やマルチステークホルダーとの連携を図っていくことが重要であると考えている。 【Meta】表現の自由をめぐる問題は、主観的、情緒的な議論ではなく客観的、科学的、法学的な研究に基づく議論が必要。研究者がプラットフォームの影響を研究できるようにする。 法令順守と自らのポリシーを厳正に執行し、必要なポリシーの見直しを不断に行う。さらに、政府がリードする取り組みの下、報道機関をはじめとする多くの関係機関の連携が求められていると考える。 【X】選挙におけるSNSの活用が、多様な意見の共有や市民参加を支え、公共の対話を促進する重要な役割を果たすと認識している。一方で、「ひぼう中傷」や「偽誤情報」といった課題は、文脈に依存し、単純なラベルでは捉えきれない複雑な問題。 こうした課題が有権者の信頼できる情報アクセスを損なう可能性を深刻に受け止めている。今後も弊社のミッションである言論の自由と公共の福祉とのバランスを追求する。 「ひぼう中傷」や「偽誤情報」は、それぞれケースバイケースで判断が難しい課題。Xは、ルール・ポリシーに基づいた対応を行ってまいります。また、コミュニティーノートを中心に、より正確な情報を入手できるように不断の改善を進める。 【TikTok Japan】ユーザーの安心安全が最優先事項。幅広い年代におけるリテラシーの向上や選挙における偽誤情報の取り組みの重要性を認識していて、積極的に取り組んでいる。プラットフォームを運営する立場として、偽誤情報防止に関する独自の取り組みを実施している。 イノベーションには責任が伴うことを認識していて、安心して安全に想像力を発揮してもらうべく、引き続き安心安全対策に向けて取り組む。 ———選挙・政治コンテンツをめぐっては、収益化を目的とした悪質なコンテンツも確認されているが、こうしたコンテンツ全般の収益化を停止させる考えはあるか? 【LINEヤフー】一般論として、収益化の停止はコンテンツモデレーションのいち施策として有用な場合もあると考えているが、再生・閲覧数稼ぎとそうでないものの区別や、収益化対象外のアカウントによる問題、「収益化」の定義など具体化には様々な課題があり、今後、更に予断を持たず検討を行っていくべきと考えている。 なお、当社において一般ユーザーが投稿コンテンツの収益化を行うことができるサービスはLINE VOOMのみだが、当社の収益化に関しては各種の審査基準を設けている。現時点では「再生・閲覧数稼ぎを目的とした「選挙や政治のビジネス化」を目的とした投稿が拡散しておらず、今後とも適切にモニタリングを行っていく予定。」 【Meta】弊社が日本で展開しているサービスに該当するものはありません。 【X】例えば、料理アカウントが物価高について投稿した場合、これは料理の話題でも、候補者の経済政策に関わる政治・選挙コンテンツと言えるかもしれない。このように政治や選挙に関するコンテンツは口で言うほど単純ではない。 なお、Xでは、2023年7月より要件を満たすクリエーターへの収益分配を行っているが、2024年11月にはそのルールを変更。また、コミュニティノートがついた投稿は収益対象外となっている。 【TikTok Japan】TikTokは、真正なコンテンツが輝き、安全が常に最優先される場所であるよう努めている。TikTokのプラットフォームにおける仕組みでは、日々TikTokに投稿される動画と広告として投稿される動画は直接的には紐づかず、ユーザーの投稿した動画が自動的に再生回数に応じて収益化されることもない。 現在、TikTokでは、クリエイターが自身の動画を通して報酬を得られる収益化プログラム「Creator Rewards Program」を提供している。 ユーザーが「Creator Rewards Program」に参加するには、18歳以上であること、コミュニティガイドラインを遵守したコンテンツであること、質の高いコンテンツの投稿者であることなどの条件を満たしていることが必要となるため、悪質なコンテンツが自動的に収益化される仕組みにはなっていない。 ———選挙や政治における候補者や有権者のSNSの利用方法について、プラットフォーマーとして課題に感じていることは 【LINEヤフー】偽・誤情報の定義・判断が難しい中で、プラットフォーム事業者による参照先となるファクトチェック機関の活動が資金難などの課題に直面しており、今後、社会全体として更なる支援の強化が必要ではないかと考えています。 加えて、偽情報などの悪用については、複数のプラットフォームにまたがって行われる可能性もあります。一部のプラットフォームだけが対処するのでは限界があると感じており、具体的なイシューに関しマルチステークホルダーが連携する仕組みが必要ではないかと考えています。 【Meta】ファクトチェックの必要性と重要性が認識されるようになった。ファクトチェックには専門性を必要とする一方で、財務的に成立することが難しいことも知られるようになった。我々は、これをどのように育成、浸透、定着させていくのか、日本社会として問われていると認識している。 【X】様々な課題があるが、検索やGrokのようなAIツールで多様な情報に触れ、広い視点で選挙を考えていただければと思います。また、より多くの方にコミュニティノートの協力者として参加いただきたい。 【TikTok Japan】選挙や政治においても、TikTokを安心安全に利用いただくべく、引き続き継続的に安心安全対策に向けて取り組む。









