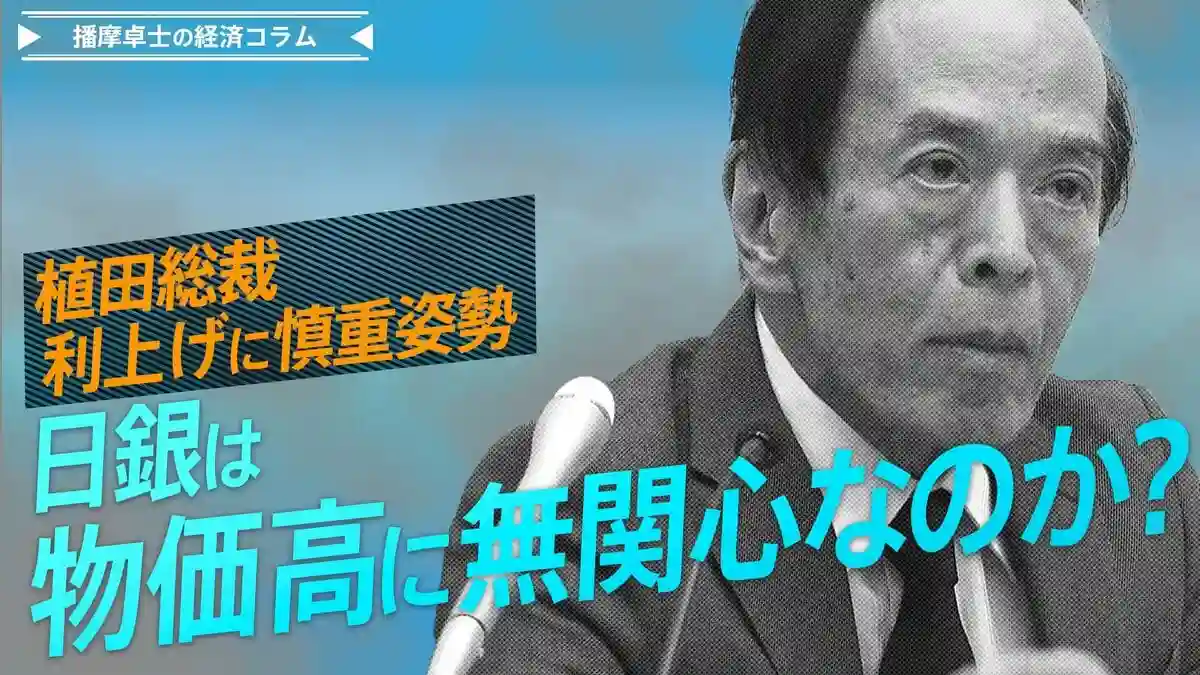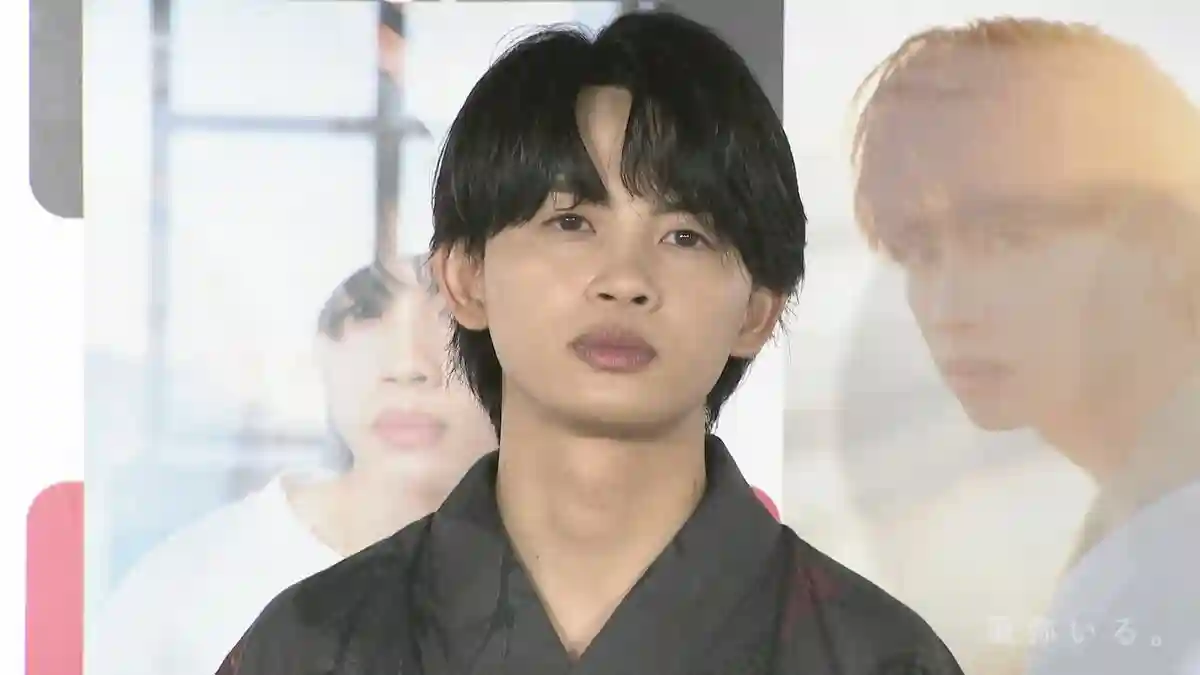直木賞作家の奥田英朗さんが10年間、原稿用紙3000枚をつかって書き上げた大巨編『普天を我が手に』がついに開幕! 戦前から戦時中、戦後をまたいで「昭和」を描く圧巻の大河小説を、昭和に詳しい有識者の方々に読んでいただきました。 今回は大澤聡さんによる書評を公開します。 奥田秀朗(おくた・ひでお) 1959年岐阜県生まれ。プランナー、コピーライターなどを経て1997年『ウランバーナの森』でデビュー。第2作『最悪』がベストセラーに。2002年『邪魔』で大藪春彦賞を受賞。2004年『空中ブランコ』で直木賞、2007年『家日和』で柴田錬三郎賞、2009年『オリンピックの身代金』で吉川英治文学賞を受賞。ほかの著書に『リバー』、『罪の轍』など。 エンタメを創るための「戦略的アナクロニズム」 めずらしく、大河ドラマを毎週かかさず観ている。『べらぼう 蔦重栄華乃夢噺』である。 横浜流星演じる主人公の蔦屋重三郎は、江戸後期に洒落本や黄表紙、浮世絵版画などのヒット作をいくつも世におくり出したことで知られる。版元だ。 「江戸のメディア王」「名プロデューサー」「ヒットメーカー」と大仰に紹介されることもある。どうもアナクロにひびく。ビジネスの構造も職業がカバーする範囲も現代とはずいぶん異なっていたから、その偉業や規模を感覚的にイメージしてもらうのに、いまの語彙を借用するよりしかたないらしい。 『べらぼう』のセリフのそこここにもまたアナクロがちりばめられている。あえてなのだろう。厳密さをいくらか犠牲にしてでも、本質を直感的に摑む。摑ませる。そちらを優先するわけだ。 なんの本質だろうか? そう、わたしたち人間の本質である。 かりそめに戦略的アナクロニズムと呼んでみてもいい。たとえ厳密を期したとしても、現代のセンスに照らして、おもしろくなければエンタメは観られない。観られなければエンタメにならない。 ドラマには、田沼意次や平賀源内、喜多川歌麿など、中学の社会科の教科書で太文字になっていた人物たちも数多く登場する。実在の人物たちだからといって、ドラマの内容をぜんぶ歴史的事実とうけとる視聴者はいない。たぶん。 エンタメとして成り立たせるために創作は不可欠だ。 経緯不詳の欠損がそこらじゅうに穴をあけている。都合や空想や飛躍がそれを埋める。フィクションならではの穴埋めの過剰さがおもしろさをもたらしもする(こうした創造力もSNS時代には陰謀論と背中あわせにある)。おもしろさと辻褄あわせが共犯関係をもつ。 事実と創作のあわいにだけ宿る「真実」 そもそも、史実ベースだからといって、過去の現実世界をそのまま再現することなど誰にもできない。どうしたって、作り手の解釈なり取捨選択なりの恣意的な操作性が混ざってしまう。わかりやすさとしての加工や編集は再現行為につきものだ。 かつて、現代思想や文学理論がせっせと批判的に研ぎすませていった「物語化」の概念は、そこを突っつくものだった。「歴史其儘」(森鷗外)も、「只ありのまゝ見たるまゝ」(正岡子規)も、じっさいには不可能だ。一九九〇年代のナイーブな議論は、そこに再現の不可能性、はたまた暴力性など、物語のかかえるネガティブな顔を見た。そこには一定の達成があった。 だからといって、歴史改竄だ、修正主義だ、捏造だとドラマのアナクロにクレームを入れる野暮な視聴者は、きっと、そう多くない。絶妙なバランスで引かれたお約束ごとの線上にぎりぎりのっかって、わたしたちは「事実」と「創作」のあわいをぐらぐらとたのしんでいる。たのしみの度合いや、その先にある景色は観るひとによる。 ともあれ、事実と創作のあわいにだけ宿る「真実」がある。 こまごまとした事実の網羅でも、まったくのゼロからの創作でも、そのどちらの手によっても届きようのない、そんな真実だ。 「事実(ファクト)」とは別のレイヤーにある「真実(トゥルース)」をつたえるには、個々の感情へうったえる「創作(フィクション)」の力がどうしても必要になる。「物語(ストーリー)」の力といってもいい。 もっとも、これも時と場合と目的におうじてというほかないのだけれど(別の機会にわたしは、近年の報道の文学化や感情化を批判している)。 物語だからこそ触れられる歴史の「真実」 奥田英朗の最新長篇『普天を我が手に 第一部』もまた、「大河小説」と形容してみたくなる、そんなスケールの超大作である。 これを読みすすむ最中に感得されるのも、まさに「事実」と「創作」のあわいに宿る「真実」の手触りにほかならない。エンタメや物語というフィクションの形式だからこそ触れることのできる、あるいは触れさせることのできる真実。そう、歴史の真実。 おもな登場人物たちは架空の存在だけれど(モデルは複数ありそうだ)、それらをとりまく時代状況のもろもろや関連人物、国内外の情勢や社会風俗や文化などはかなりのところ史実にのっとっている。綿密な調査と計算が下敷きにあるのだろう。おおきな歴史的事実とおおきなフィクション、双方が紙のうえでがっぷり四つに組む。 およそ六百ページのボリュームをほこる本作『第一部』の物語世界には、十五年という時間が流れている。大正十五(一九二六)年十二月二十五日から、昭和十六(一九四一)年十二月八日直後まで。すなわち、大正天皇の崩御から太平洋戦争の開戦まで。 物語をすすめる軸となるのは四人の人物である(文字どおり「四つに組む」のだ)。 陸軍省軍務局に所属する少佐・竹田耕三、金沢で賭場の運営を生業として一家をかまえる俠客の親分・矢野辰一、女性啓蒙文芸誌『群青』の編集者である森村タキ、中国の大連でジャズ楽団を主宰する五十嵐譲二。どれも大正末時点の肩書きで、十五年のあいだにうつりかわる。 四人とも明治二十年代生まれだ。物語開始時にみな三十代と世代こそ近いものの(とはいえ、じつは明治の数年の差はおおきい)、あとは居住地から、社会的な立場から、イデオロギーから、なにからなにまでてんでばらばら(竹田と森村はどちらも東京市内在住で距離的には近いが)。ただ、なにかのためには「死を恐れていない」(四十二節)、そんな行動的な生き方を選ぶ覚悟という点ではみな共通する。比喩としても直接の意味でもそうなのだ。 それ以外は、おたがいに面識もなく、独立した別々の人生(=物語)を生きている。ようするに、四つの【小物語】の集合体として小説全体がある。全体のほうは【大物語】ととりあえず呼んでおこう。 浮かび上がってくるもうひとりの主人公! それぞれを視点人物に設定したパートが、節単位でぱちぱちときりかわる。理論的には、多元焦点化といっていい。一節は竹田、二節は矢野、三節は森村、四節は五十嵐、五節はまたもどって竹田、六節は矢野……といったぐあいに、律儀なほどきちんきちんと順番をまもりながら、最後の五十二節まですすむ。ほぼ均等な分量で四人の小物語をローテーションしてゆきつつ、だいたい時系列にそうかたちで、大物語は十五年を経る。 読者はそのつどの節の主人公にどっぷり没入しては、小物語どうしのあいだをぐるぐるぐるぐると定期巡回する。水平の移動だ。ところが、ページをくりつつスパイラル状に時間をかさねてゆくうち(物理的には左手よりも右手にもつ紙のボリュームが増すにつれて)、小物語たちを統制的に俯瞰する場所に自分が立っていることにふと気づく。そんな瞬間が増えてくる。大物語に焦点があう。 たとえば、普通選挙、張作霖爆殺事件、満洲事変、満洲国成立、五・一五事件、満蒙開拓団、国際連盟脱退、関東防空演習、二・二六事件、日中戦争勃発、国民精神総動員運動、南京陥落、第一次人民戦線事件、第一次近衛声明、国家総動員法、満蒙開拓青少年義勇軍、七・七禁令、日独伊三国同盟、隣組の組織、ハル・ノート……高校の日本史で暗記させられた歴史的事項の群れが、順次、小物語たちの遠景や近景を織りなす。 会話や地の文のなかにごく自然に流しこまれたそれらに関する言及や解説めくナレーションを読みながら、このあとに起こるであろう「未来」の出来事を正確に予期するとき、読者は各節の主人公へどっぷり内在しているのではなくて、いってみれば神のごとき超越的な地点に立っているはず。小物語から大物語へ。さきほどの「水平の移動」に対応させるなら、こちらは「垂直の移動」。 そんな瞬間がかさなった果てに、四人の主人公たちとはまた別の、さらにもうひとりの主人公が、読者の眼の前に浮かびあがってくる。 それが「昭和」だ。 昭和に幻視する「人称性」 架空の四人の主人公たちが生きる個々の人生。そこに描かれようのない物語の外側にある、やはり架空の人物たちの無数の人生。それらをぜんぶ「昭和」という名の激動の時代が吞みこむ。そして、ぶくぶくと肥大化してゆく。 いびつなその成長っぷりや変形のあり方に、わたしたちは人称性を幻視する。時代に人格がそなわっている。 じっさい、登場人物たちはことあるごとに、まだはじまったばかりの昭和時代の性格について評価をくだしてみせもするのだ。ときに希望、ときに恐怖の対象として(作中には出てこないが、昭和二年に自殺した芥川龍之介はその時代の性格を過度に察知したのではなかったか)。くりかえし飛び出す単語は「岐路」「分岐点」「分かれ道」。これほど俯瞰的な評価のことばもないだろう。 主人公たちのそうした時代認識はあながち的を外してはいない。そうやって判定できる未来にわたしたち読者は立つ。だから、小物語の各主人公までもが読者といっしょに超越的な視座を手にしかかっているようにすら見えてしまう。エンタメ特有のあのアナクロニズムが顔を覗かせる。むしろ、そこがおもしろい。 昭和とともにうまれた四人の人生 とはいえ整合性もちゃんとある。大物語の主人公である「昭和」とともに産声をあげた子どもをもつという決定的な共通点が四人にあたえられているからだ。 竹田家待望の長男の志郎(上に三人の姉)は大正天皇が崩御した直後、おなじ夜に生まれているし、矢野家では、つきあいのある社長の妾が懐妊ということであずかっていたところ、同日に四郎が生まれて、しかし母親の産褥死のため養子に入れる。どちらも「昭和の最初の日に生まれた子」(二節)なのだ。 十二月二十八日、森村が妻子ある無責任な社会活動家とのあいだの娘ノラ(イプセン『人形の家』からとった)を産んでシングルで育てはじめ、三十一日には大連で五十嵐のところに満(満洲からとった)が生まれた。一週間しかなかった「昭和元年」に、みな子どもが誕生している。さきほどのローテーションの順は子どもが生まれた順でもある。 昭和元年生まれの子をもつ四人は、いきおい、昭和という時代区分を強烈に意識するよう運命づけられるし(作中に書かれてこそいないが子どもたちもいずれそうなるはずだ)、なにはさておいても、そんな彼ら彼女らを軸に構成される物語全体は【未来志向の気配】をまとわずにはいない。 たとえば、竹田の内面を代弁する位置にある地の文は、長男の誕生早々「この先、日本は一等国になるべく発展する。その主役は息子たちの世代だ」(一節)とずいぶんテンション高く語っている。子どもの誕生という家庭内のプライベートな出来事が、パブリックな世界情勢や歴史と直結する。この感覚が本作をつらぬく。 自分の子のあるなしにかかわらない。ちいさな子どもと接することは、必然的に、個人のライフスパンをこえた未来への思考を可能にする。さっそく竹田は、「息子が大きくなる頃には」(九節)……と自分の人生とは別の時間的な長さとリズムのもとで社会の動態をとらえはじめている。 壮大なスケールをもつサーガ(=大河小説)は、こうした時間感覚の拡張を読者にももたらしてくれる。それが時代小説を読む副次的な効用でもある。 わたしたちは実人生で歴史の全体像を眼にすることなどない。小説のなかでは、読書のなかでは、それが可能になる……といえば、あまりにも陳腐な理解だろうか。けれども、本作を読みながら実感するのはなによりもそのことなのだ。 戦時ゆえに存在しない「中物語」 ところで、出産を控えての募金活動中に民間右翼の襲撃をうけて不意に産気づく森村が運びこまれたのが、その三日前に竹田の妻が出産した病院だとさりげなく記されている。そうやって序盤早々に予告されたとおり、個別の小物語たちは、登場人物どうしのニアミスや鉢合わせや加害被害など、節を越境したピンポイントの接点をすこしずつ増やしてゆく。独立性を保ちながら大物語への合流を示唆する構造になっている。 接点は東アジア全域にひろがる。これ以上はネタバレになるので作品にゆずるが、一例をあげるなら、満蒙開拓青少年義勇軍の存在によって、矢野のいる金沢と五十嵐のいる満洲はつながっている。内地で立った法案が外地に影響する。経済もそうだ。こちらとあちらがリアルタイムで連動する。小物語の部分的な融合に歴史の立体感をわたしたちは垣間見る(ちなみに、『ヤングマガジン』で連載中のマンガ「満州アヘンスクワッド」が重点的に描くのもこの立体感だ)。登場人物たちも「世間はどんどん狭くなる」(三十一節)という感触をいだいている。 大物語、小物語と呼んでおいた。おおきな世界情勢と、ちいさな個人の人生。両極をむすぶ中物語がそこにはない。これもまた戦時の特性だろう。 つながるはずのなかった人生と人生が接触したことによって、あるいは戦争という事態がふかまるにつれて、それまで気づかなかったいくつもの分断線が剝き出しになる。反対に、まっこうから対立するイデオロギーの人物どうしが心情的に連帯する可能性も生まれる。 そうした歴史の位相は、政治や経済、軍事、外交などパブリックな側面だけを相手にする、客観性をよそおった歴史叙述にはカバーできない(だからこそ、近年は政治学や経済学の方面で情動が論点にもなる)。それらをじっさいに動かす個別の人間たちの感情、その交錯、さらには家庭や生活といったプライベートな側面までふくんだ遠近大小を多角的に描ける、自由度の高いフィクションだからこそ、そこに宿る真実がある。 四人は架空のモデルケースだ。けれども、現実の歴史もまたそのように生成してゆくのだと読者は感覚的に理解するだろう。理解へと導くための膨大な歴史的事実の的確な配置と、物語のリズムの精密な操作、にもかかわらず、それらをつつむ圧倒的なリーダビリティを本作はそなえている。 だから個人的には、いっそ二日間ほどで読破してしまうことを推奨したい。「昭和」の激動っぷりと、歴史が生成するメカニズムをいっきに体感できるはずだ。もちろん、日数をかけて一パート一パートじっくり読みすすむことで、主人公たちとシンクロしつつ昭和を生きてみるのも悪くない。 最後に、ちょっと打算的かつ蛇足的なことを記しておくなら、知識としての歴史的事実を一定のパースペクティブのなかに正しく位置づけるために(ありていにいえば暗記をしっかり定着させるために)、良質のフィクションはかなり有効に機能する。むしろ、これまでもこうした物語たちの力を借りて、先人たちもまた歴史への想像力を鍛えあげてきたのだ。 奥田英朗『普天を我が手に 第一部』 大正15年(昭和元年)12月25日未明、東京・麹町の陸軍少佐・竹田耕三の元に、待望の長男が誕生した。〈志郎〉と名付けられた子供は、日本中が大正天皇崩御の悲しみに暮れる中で、一家の新たな希望となる。 同日、北陸・金沢では、矢野一家の親分・矢野辰一が、賭場での諍いの落とし前をつけに、敵対する一家に乗り込んだ。帰宅した辰一を待っていたのは、懇意の社長から預かっていた女工の出産と死だった。辰一は孤児を〈四郎〉と名付け、自分の手元で養育することに。 一方その頃、東京・神保町で進歩的な婦人雑誌「群青」の編集者として働く森村タキが、社会運動家との間に女子を出産。『人形の家』にあやかり〈ノラ〉と名付けたその子を、身勝手な父親から引き離し、女手一つで育てることを決意する。さらに同年の大晦日、野心を胸に中国・大連へわたった五十嵐譲二は、主宰するジャズ楽団の年越しパーティ中に妻から出産の報告を受ける。出生した男子を〈満〉と名付け、昭和元年最後の夜に最高の演奏をする。 昭和100年、戦後80年に生まれる、壮大な昭和史サーガ三部作。 第一部は、親世代の視点を中心に、大正天皇の崩御から太平洋戦争開戦までを描く。 「論破」「陰謀論」「マスゴミ批判」…「事実」をもって「イデオロギー」を批判する現代の言論スタイルはいかにして生まれたのか?