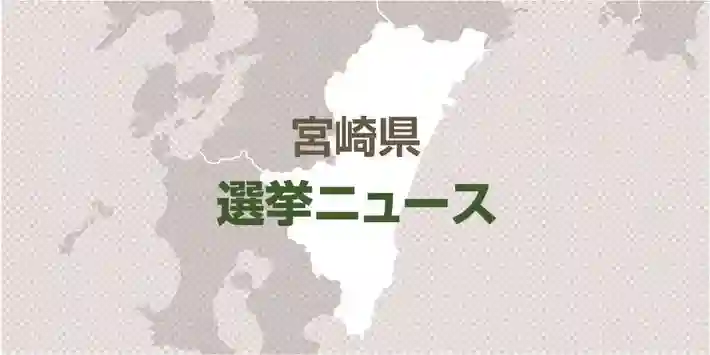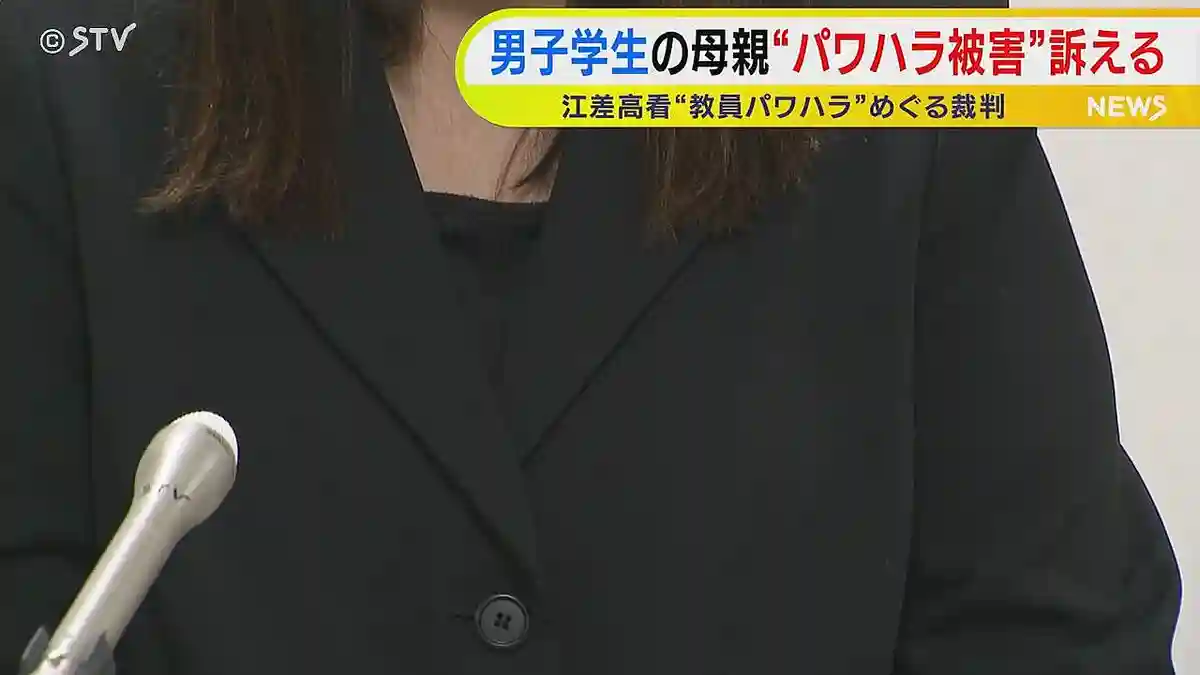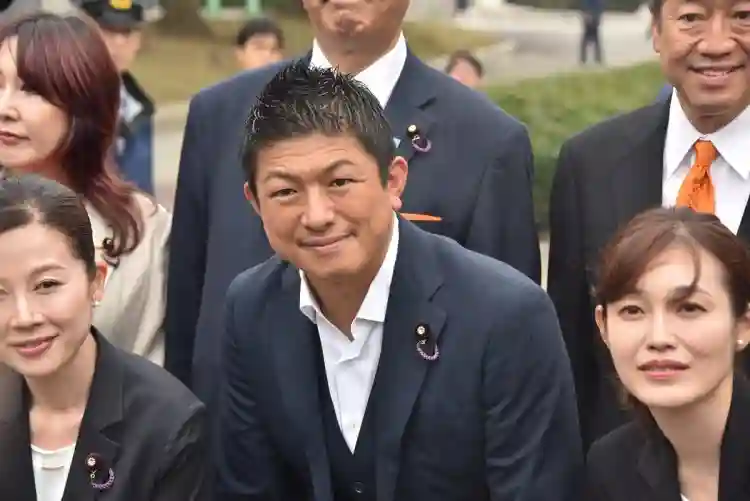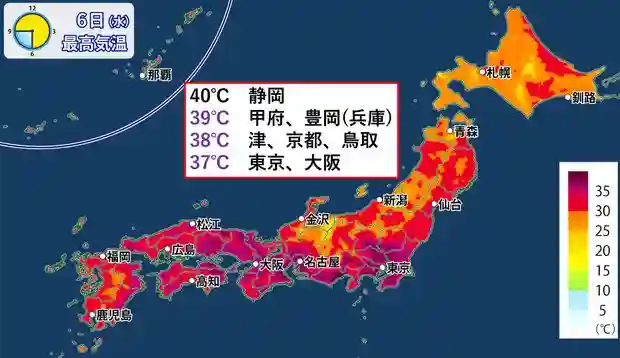太平洋戦争で日本軍が交戦した相手と言えば、もっぱらアメリカ軍とイギリス軍が想起されがちであるが、じつは開戦当初、当時インドネシアを植民地化していたオランダ軍(蘭印軍)とも戦い、これを降伏に追い込んでいる。 【写真を見る】残留が決まり日本人を絶望させた「ジャワで最悪」といわれた作業場 インドネシアに約7800人の日本人が留まった 日本軍は多くのオランダ人を捕虜として現地で抑留するが、日本が敗戦すると、一転して日本人がオランダ人に抑留される立場となった。はたして、反日感情に駆られたオランダ人に、日本人はどのような扱いを受けたのだろうか。 日本軍人らの貴重な日記類を読み解き、南方抑留の歴史的背景と過酷な実態を明らかにした『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』(林英一著、新潮選書)から、一部を再編集して紹介する。 オランダの植民地インドネシア・ジャワ島に上陸した日本軍(1942年3月1日) (出典:Imperial Japanese Army -- archived by U.S. Army Center of Military History, Public domain, via Wikimedia Commons) * * * ジャワ島に取り残された日本兵 16世紀初頭にはじまったヨーロッパ勢力による東南アジアへの進出は、交易独占を目的とした「点と線の支配」から、植民地を開発する「面の支配」へと変貌し、第一次世界大戦の頃までにはタイ以外の東南アジア全域が欧米列強の植民地となっていた。 このうちインドネシアでは、1830年にオランダ植民地政庁が住民の一部にコーヒー、サトウキビ、藍などの特定作物の栽培を義務づけ、その加工製品の独占的輸出で莫大な利益を上げた後、各地の小王国を次々と統治下に治めてオランダ領東インドが誕生した。 南方抑留関連地図 ※画像は『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』(新潮選書)より その一方で、ジャワ島中部の農村で大規模な飢饉が起こるなど、農民たちは重い負担を強いられた。20世紀に入ると、オランダ世論の批判もあり、オランダ政庁は住民の福祉向上、キリスト教布教、権力分散を骨子とする「倫理政策」に転じた。この後、民族意識に目覚めた住民の間で民族主義運動が広がるが、1934年に独立運動の指導者スカルノとモハマッド・ハッタが流刑に処されるなど、オランダ当局に抑圧されていた。 そのような独立運動の停滞期に到来した日本軍は、1942年3月12日にスマトラ島北端のアチェに無血上陸を果たすなど、初めこそ解放者として住民に歓迎された。しかし、1943年5月の「大東亜政略指導大綱」で「『マライ』『スマトラ』『ジヤワ』『ボルネオ』『セレベス』ハ帝国領土ト決定シ重要資源ノ供給源トシテ極力之ガ開発並ニ民心ノ把握ニ努ム」とし、日本はインドネシアの独立を認めず、帝国領土に編入した。 独立宣言を読み上げるスカルノ(1945年8月17日) (出典:Frans Mendur (also Frans Mendoer) (1913 - 1971), Public domain, via Wikimedia Commons) その後、戦局が悪化すると、翌年8月19日の最高戦争指導会議の「今後採ルヘキ戦争指導ノ大綱」で「将来東印度ヲ独立セシムルコトヲ成ル可ク速カニ宣明ス」として、将来の「独立」を許容した。 これを受けて現地では「独立」の準備が進んだが、それが実現する前に日本軍は連合軍に降伏してしまう。そして玉音放送2日後の8月17日にスカルノが独立宣言書を読み上げ、インドネシアは革命の時代に突入する。 【シベリア抑留の陰で繰り広げられていた「もう一つの悲劇」】敗戦の屈辱に耐えながら炎天下で重労働を強いられた兵士たちは、飢えと望郷の日々の中で何を考え、どう行動したのか。日本軍人・軍属の貴重な日記類を読み解き、南方抑留の歴史的背景と過酷な実態を明らかにする。 『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』 降伏時に第一六軍(治集団)作戦主任参謀だった宮元静雄陸軍中佐(陸士四四期、陸大五二期)によれば、終戦から復員までの約2年間で犠牲となった日本人の数は1078人で、その内訳はイギリスとインドネシア間の戦闘による死者が562人、自殺が60人、その他(病死・事故死など)が456人。地域別ではジャワ西部が600人、ジャワ中部が308人、ジャワ東部が149人、バリ島が21人と、西部ジャワが突出していた。1078人という死者数は開戦時のジャワ作戦中の戦死・戦傷者957人に匹敵し、革命が暴力性を孕んでいたことが窺い知れる。 そうしたなかでジャワ島に上陸したイギリス進駐軍がインドネシア側とスラバヤなどで武力衝突し、インドネシア人が就労拒否した結果、連合軍の支配地域での労働力が不足した。そこで白羽の矢が立ったのが降伏した日本人たちで、1946年2月15日に西部地区隊長の馬淵逸雄陸軍少将(陸士30期、陸大41期)は、ジャワ視察に訪れた南方軍総参謀長の沼田多稼蔵陸軍中将(陸士24期、陸大31期)に対して、「現在迠(まで)ニ当地ニ於テ武装解除ノ上『ジヤカルタ』ニ送レルモノ四千四百三十九名ニシテ其他毎日概ネ約千二百名ノ労役ニ服シアリ」と報告している。 とくに西部ジャワで唯一連合軍の支配下にあったジャカルタ北東部のタンジュン(タンジョン)・プリオク港では、常時約2000人の日本人が住み込みで働き、連合軍の補給を支えた。彼らは早期帰還を信じて、ジャワで最悪といわれた同港での重労働に耐えたが、イギリスに代わってジャワに復帰したオランダは1万3400人の残留を命じ、ジャカルタの他にボゴール、バンドン、スラバヤなどにも作業隊を配置して日本人を絶望させた。 南方残留同胞引揚促進全国家族連盟本部によれば、1947年3月1日時点で、ジャワを含むインドネシアに約7800人が現地残留作業隊として留まっていたという。 オランダ兵の反日感情 さて、イギリスに代わってインドネシアに復帰したオランダ人は「インドネシアの独立戦争を呪い日本人を憎んだ。戦犯を弁護するためにジャカルタに残留した松浦攻次郎陸軍主計中尉は、旧知のオランダ人から「一体君達日本人は戦争中インドネシア人に何を教えたのだ、彼等はまるで変わってしまった」と嘆かれたという。 ジャカルタ海上輸送部の木ノ下甫部長も「和蘭〔引用者注:オランダ〕側に移管されて閉口したのは、何事も一応は英軍当時のままに継承されたが、何か報復的な意地の悪さが、事ある毎に感ぜられることであった」と述べている。 スマトラ島北部のブラワン(ベラワン)収容所で残留作業隊第五中隊長だった柳沢邦夫陸軍大尉は、日本軍の捕虜として泰緬鉄道(タイとビルマを結ぶ全長約415キロメートルの鉄道)建設に参加し日本兵に殴られて前歯3本を失った「歯欠け軍曹」の話を手記に書き残している。「歯欠け軍曹」は抑留者を手荒く扱い、そのあだ名は「恐怖の代名詞」だったと回顧する。また、倉庫の見張り番の「骸骨じじい」は、暴力こそ振るわないものの、いつもオランダ語で罵ってきて、とにかく意地悪だったという。 旧オランダ領のスラウェシ島では、オランダ人に代わってオランダ植民地軍の現地人兵士だったアンボン人が日本兵の監視役となったが、オランダ植民地政庁から特権的な地位を与えられ、親オランダ的だった彼らのなかには日本軍俘虜収容所にいた者が多く、日本人を憎んでいた。終戦後にマリンプン収容所に抑留された奥村明陸軍少尉は、アンボン人の軍曹に敬礼しなかったのを見咎められて、顔に唾を吐かれ、インドネシア語で悪態をつかれて、悔し涙を流している。 このようにオランダ軍が日本人を憎悪したのには、日本軍によって「オランダ女王の首飾り」といわれた豊かな植民地を喪失したことに加え、「2度目の植民地征服」を目指してインドネシア軍と戦わざるを得なくなったことへの恨み辛みがあったと考えられる。 その証拠に、オランダの対日戦犯裁判では停戦協定違反で裁かれたケースがあるが、これは日本軍がインドネシア軍に武器を引き渡したり、逃亡兵がオランダ軍に敵対したりした罪を問われたものである。日本側でも残留日本兵の弁護のため、「脱走日本兵ガインドネシアニ加担シ対和蘭戦斗行為ヲ為シタル場合ニ関連スル規定」として、陸戦法規、降伏規約、戦犯に関する条文の検討がなされていた。 ※本記事は、林英一『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』(新潮選書)を再編集したものです。 林英一(はやし・えいいち) 1984年、三重県生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科後期博士課程単位取得退学。一橋大学博士(社会学)。2025年7月現在、二松学舎大学文学部歴史文化学科准教授。インドネシア残留日本兵の研究で日本学術振興会育志賞受賞。著書に『残留日本兵の真実』『東部ジャワの日本人部隊』(ともに作品社)、『皇軍兵士とインドネシア独立戦争』(吉川弘文館)、『残留日本兵』(中公新書)、『戦犯の孫』(新潮新書)、『残留兵士の群像』(新曜社)など。 デイリー新潮編集部