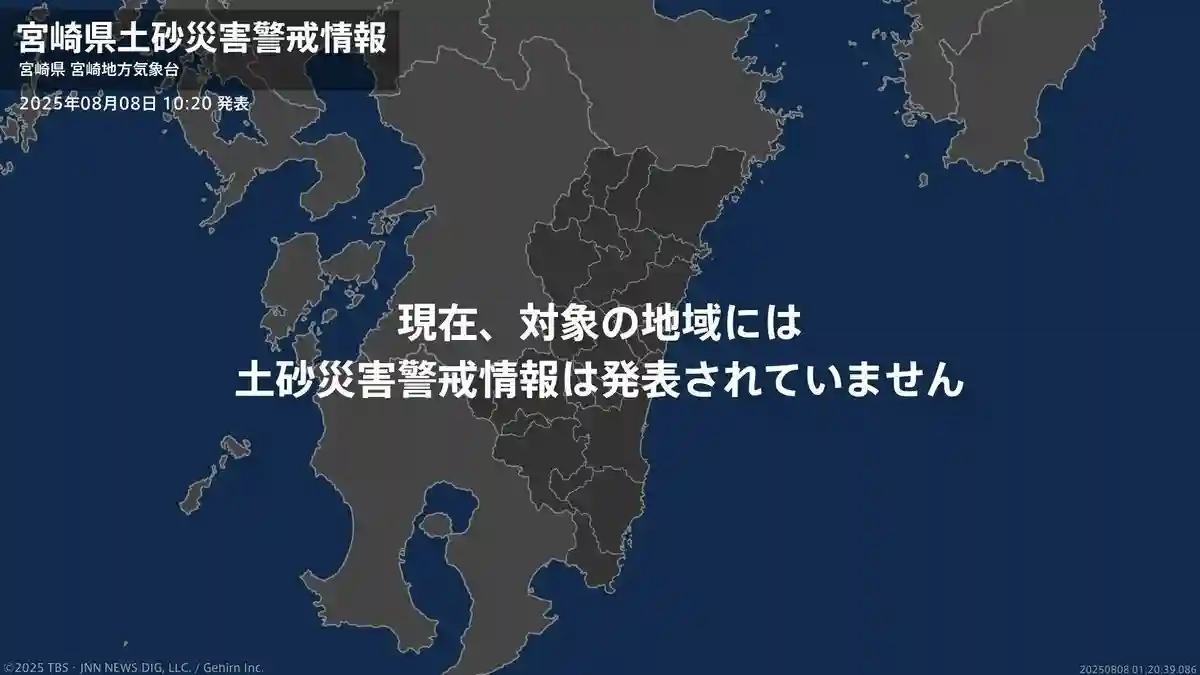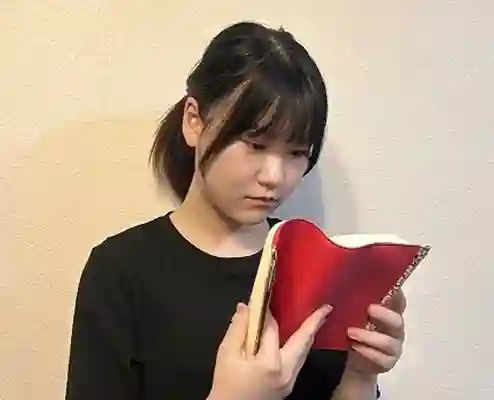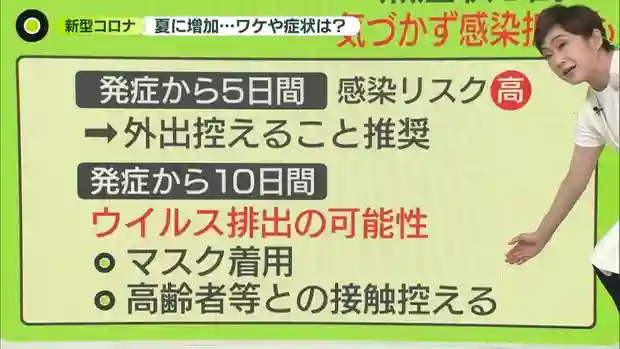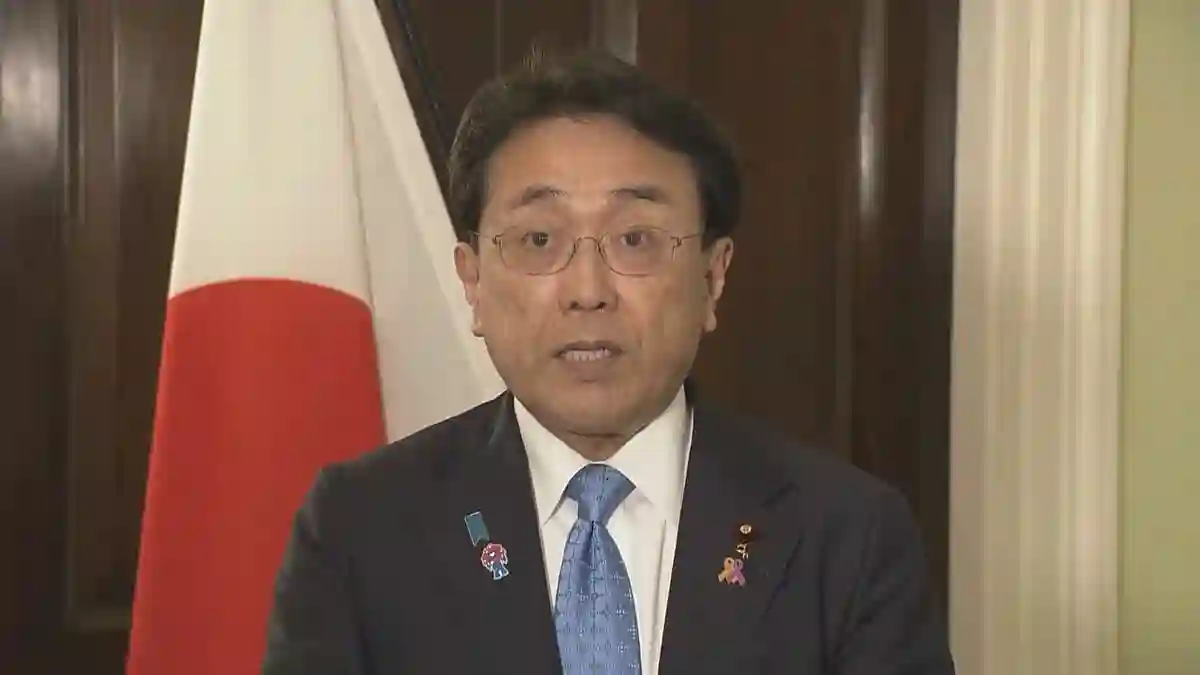配当狙いなら定期預金の方がまし? IPOから9ヶ月あまりが経過した東京地下鉄(東京メトロ、9023)。筆者はその株価が現在「冴えない」理由を前編記事〈「西武」「東急」との差はどこでついた?いま「東京メトロ」の株価が冴えない本当の理由〉でいくつか指摘した。では結局、「東京メトロ」株は買いと言えるのか。個人的な「結論」を本稿でお伝えする。 東京メトロの2026年3月期の年間配当予想は42円で、想定される利回りは2%前後(本稿執筆時点)にとどまる。 日銀が利上げ政策に舵を切った結果、定期預金の金利でも一定の条件を満たせば2%を超える商品も散見されるようになってきた。 株価下落のリスクを負ってまで2%の配当金を狙うよりは、預金保険による元本保証がついて1~2%の預金利息を狙う方が合理的と考える者も少なくない。 PER(株価収益率)は20倍弱と、公共インフラ企業としてはむしろ高めの水準であり、インカムゲイン目的での投資妙味も現状は乏しいといわざるを得ない。 成長の足音が聞こえない 上場当時、市場では「上場益を活かして新たな地下鉄計画や海外展開に打って出る」といった成長シナリオが期待された。特に、ジャカルタ地下鉄構想への参画や、東南アジア市場での都市交通案件は注目を集めた。 しかし、2025年以降東京メトロ側からは、これらの具体的な進捗はほとんど報じられていない。今四半期の決算短信でも言及はゼロだった。海外プロジェクトから東京メトロがどのような収益・果実を得るか、いまだ判然としていない点も懸念要因だ。 また、かつて注目されたスペースマーケットを筆頭とするスタートアップ投資例も未だ4例にとどまっており、「積極投資」の姿勢、つまり”野心”がそれほど強く市場に伝わっていない可能性がある。 東京メトロは、都心一極集中に伴う災害や疫病蔓延リスクを意識していることは確かだ。しかし、依然として訪日研修やオンライン講座など、知見の共有にとどまっている。 「地理的なリスク分散」としての海外展開は、実現には10年以上の単位がかかるほど遠い段階であると筆者は考えており、期待先行であると考えられる。 あのIPOと酷似する株価の軌跡 東京メトロの株価チャートを追ってみると、既視感が襲ってこないだろうか。 それは、2015年に上場した日本郵政(6178)の推移である。 2015年11月の上場から8ヶ月間の値動きを確認すると、東京メトロと同様、IPO直後に大きく値上がりした後、期待が剥落している様子がうかがえる。 日本郵政もまた、上場直後に初値を一時上回った後、半年〜1年以内にじりじりと下落し、以後は初値割れでの停滞が続いた。 両者に共通するのは、「国策上場」であること、そして「成長投資よりも売却益確保が主眼だった」という点だ。投資家は当初の期待感から買い向かうものの、ビジョンや資本政策が打ち出されないまま需給が緩み、株価は素直に需給の重さを映す。 東京メトロ株も今、まさにその郵政型パターンの伸び悩みにはまっている可能性がある。 結局、「買い」と言えるのか? 東京メトロの株式は、「鉄道インフラ×都心不動産」という構造に魅力がある一方で、それを評価するには相当の長期視点が必要だ。時価総額は依然として1兆円程度の水準で推移している。 今後株価が2倍になるには、新たに1兆円分の企業価値を創出しなければならないが、”夢”のあったIPO当初はもとより、目下の決算と向き合って”現実”がみえてきた今、1兆円もの付加価値を市場にアピールすることは以前にも増して困難になっていると言えないだろうか。 株主優待や配当などのインカムゲインで元を取るにも、数十年単位の保有が前提になる。その期間には震災や感染症、そして東京一極集中構造の崩壊といった、潜在的リスクとも向き合わなければならない。 結論として、東京メトロの株式はやはり短期的・投機的な「買い」ではないという見立てを据え置きたい。 むしろ、同社が進めるスタートアップ協業や駅資産の収益化、交通外事業の展開を冷静に見極めながら、地道にバリューを積み上げていくことができるかに、中長期での投資判断の焦点が集まるだろう。 「安定」と「成長」は、しばしばトレードオフとなる。 東京メトロはその両立を実現できるのか、市場は今も静かに見極めているのだ。 【新NISA】8月の「配当取り」を狙える、 注目の日本株「高配当株・増配株4選」を実名公開