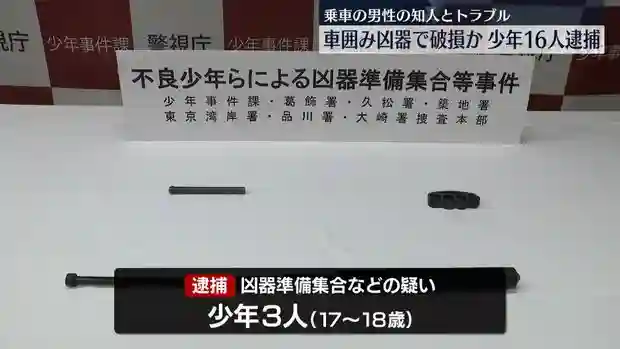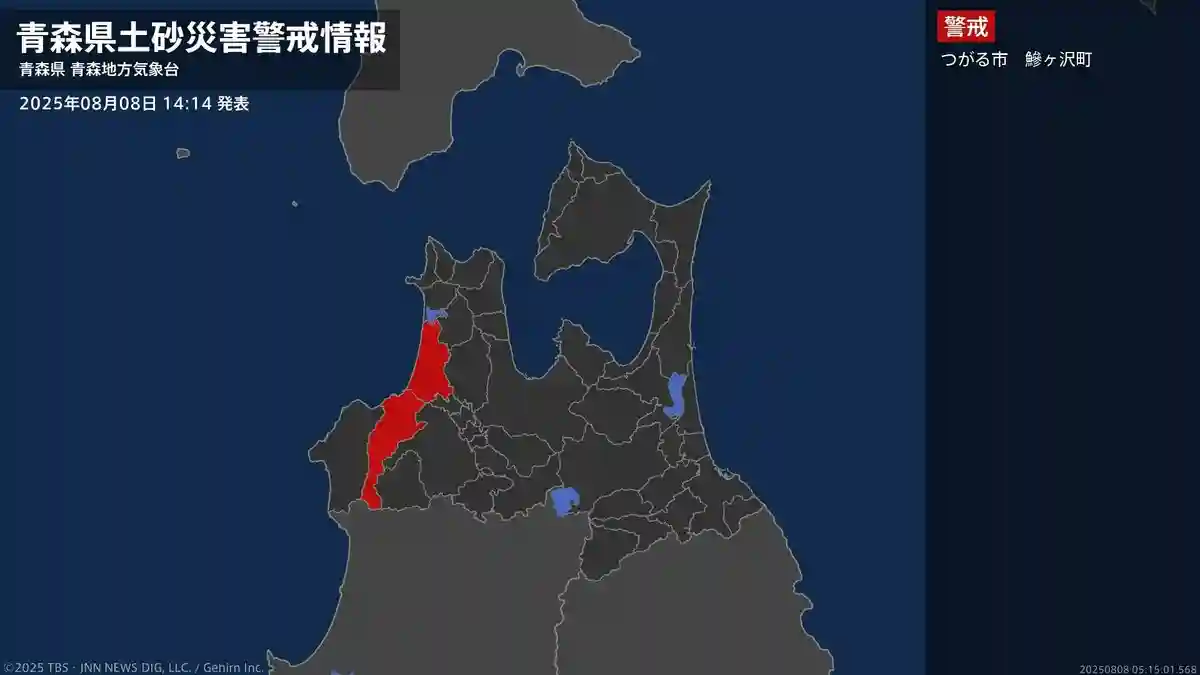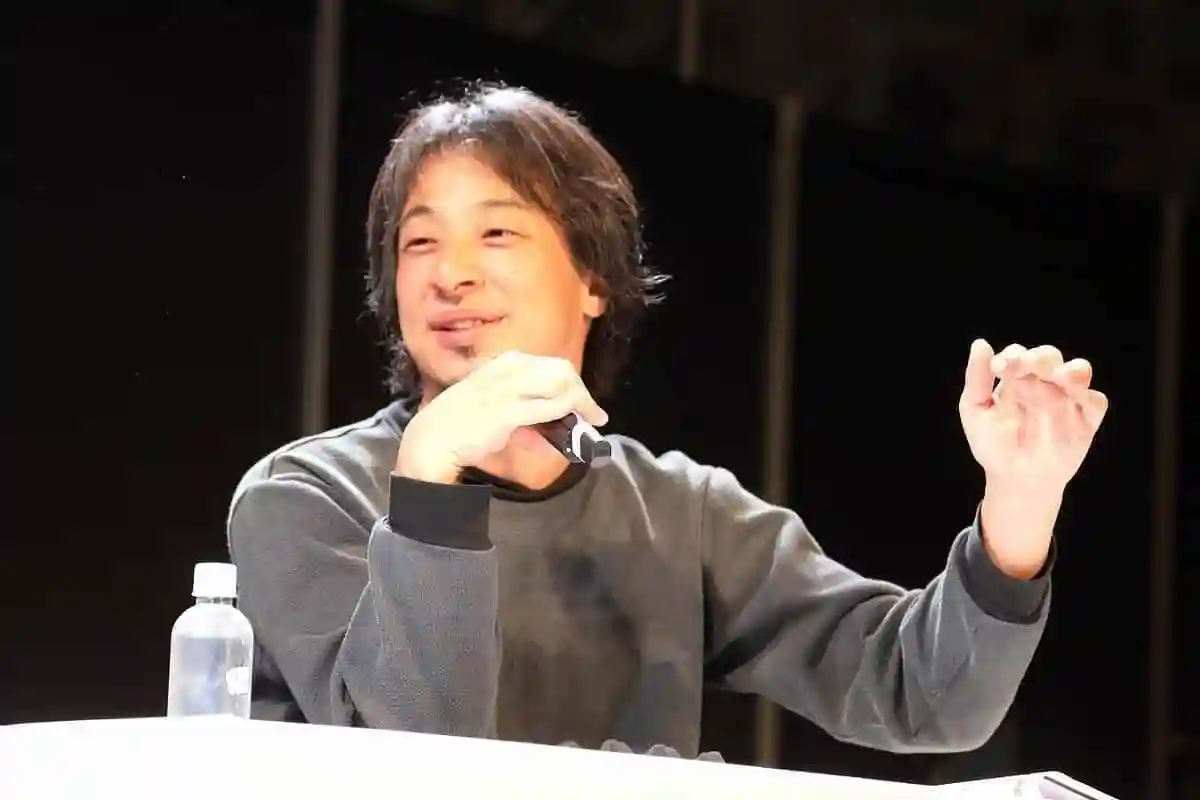ブラジルの名匠、ウォルター・サレス監督の最新作「アイム・スティル・ヒア」(8月8日公開)は、1970年、軍事政権下のブラジルで、最愛の夫を奪われた女性の物語。 彼女は、泣かない、叫ばない。でも屈服せずに静かに闘う。その姿に、その愛情に、その理性に、きっと、心揺さぶられる。目を開かれる。実在の人物たちの物語だ。(編集委員 恩田泰子) 2025年3月、第97回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した作品。主演のフェルナンダ・トーレスは、それに先立つ第82回ゴールデングローブ賞で主演女優賞(ドラマ部門)に輝いている。 映画の冒頭、トーレスが演じる主人公エウニセ・パイヴァはリオデジャネイロの陽光の下、海水浴を楽しんでいる。穏やかな時に水を差すのは、軍用ヘリの不穏な轟音。でも浜辺に目をやれば、いとおしい家族がいる。 エウニセが、元下院議員の夫ルーベンス(セルトン・メロ)、そして5人の子供たちと暮らすリオの家はいつもにぎやかだった。軍政下の社会が息苦しさを増す中にあっても、人々が自由に集い、「トロピカリア」など時代の文化に触れ、世の中について語り合っていた。突然、ルーベンスが連行され、消息を絶つまでは。そして、エウニセの、長きにわたる闘いが始まる。 原作は、ルーベンスとエウニセの息子で、作家・ジャーナリストのマルセロ・ルーベンス・パイヴァが2015年に発表した回想録、『Ainda estou aqui(私はまだここにいる)』だ。 監督のサレス自身、パイヴァ家の人々と親交があったといい、インタビューで「彼らの家は私の思春期に深く刻まれた記憶の場所」だと語っている。世代や立場を超えた人々が自由に集うパイヴァ家は「『こんな国にしたい』という理想の縮図だった」とも。その言葉通り、映画の序盤で描かれる同家の様子は、自由で文化的で活力に満ちている。 そんな家族の受難を、この映画は、エウニセを中心に描く。彼女は子供を守る一方で、夫のこともあきらめない。彼の存在を消し去ろうとした軍政の犯罪を明らかにしようとする。そして、そのために、あくまでも理性的に行動し続ける。恐怖や苦しみ、怒りを、自分の中に封じ込め、なんでもないような顔をして。それがどれだけ大変なことか。 ふと、彼女の顔や体に力がこもる時がある。必死で何かをこらえるように。そうしなければ噴き出してしまう激情が彼女の中には渦巻いている。底知れない痛みや恐怖とともに生きているということが、圧倒的な迫力で伝わってくる。記号的に泣いたり叫んだりするよりも、ずっと強烈に。 そんなエウニセを演じるトーレスがとにかくすばらしい。何も大げさなことはしていないのに、その一挙一動に心揺さぶられる。エウニセの老境を、トーレスの母であり、サレスの名作「セントラル・ステーション」に主演したフェルナンダ・モンテネグロが演じているのも見逃せない。 エウニセは、母として、妻として、愛する者たちのために闘う。国家による野蛮な暴力に対して、個の尊厳を守り抜こうとする。 ある時、取材に訪れた記者とカメラマンは、悲劇の家族のポートレートを撮ろうとするが、彼女と子供たちは笑顔を崩さない。不幸な顔など見せてなるものか。その姿は、夫に続いて、彼女が一時拘束された時、闇の中からきこえてくる誰かの歌声を思い出させる。 歌われていたのは、ネルソン・サルジェントの名曲「サンバは死なない」。黒人らしく力強く恐れることなく、どんなに厳しく迫害されても……という歌詞に宿る精神、ブラジルの文化をも、彼女は体現していく。かつて夢見た自由な未来を、理想を、子供たちにつないでいくために。それは、この映画自体の精神でもある。 映画を彩る気骨のブラジリアンロックのかっこよさにも胸が熱くなる。エウニセが大切にしてきた写真、娘がスーパー8で撮影する(という設定の)ホームムービーの映像が心にしみる。 本作は、ブラジルでは2024年11月に公開され、大きなヒットとなったという。過去を繰り返してはならないという真っ当な危機感から劇場へ足を運んだ人も多かったのではないか。そうした危機感の背景には「権威主義的」とされるボルソナロ前大統領の存在もあるだろう。 ちなみにボルソナロ氏は、22年の大統領選の結果を覆そうとするクーデターに関与した疑いで刑事訴追されているが、同氏とトランプ米大統領は親交が深い。トランプ政権は、ボルソナロ氏の裁判を「魔女狩り」と非難し、関税率の引き上げなどでブラジル政府への揺さぶりを強めていると報じられている。 そんな世界で私たちは何を信じ、何を守って生きていくべきか。エウニセの物語を今こそ凝視すべきだろう。 ◇アイム・スティル・ヒア(原題:AINDA ESTOU AQUI、英題:I’M STILL HERE)=2024年/ブラジル・フランス/ポルトガル語/137分/字幕翻訳:原田りえ/配給:クロックワークス=8月8日から東京・新宿武蔵野館ほか全国ロードショー