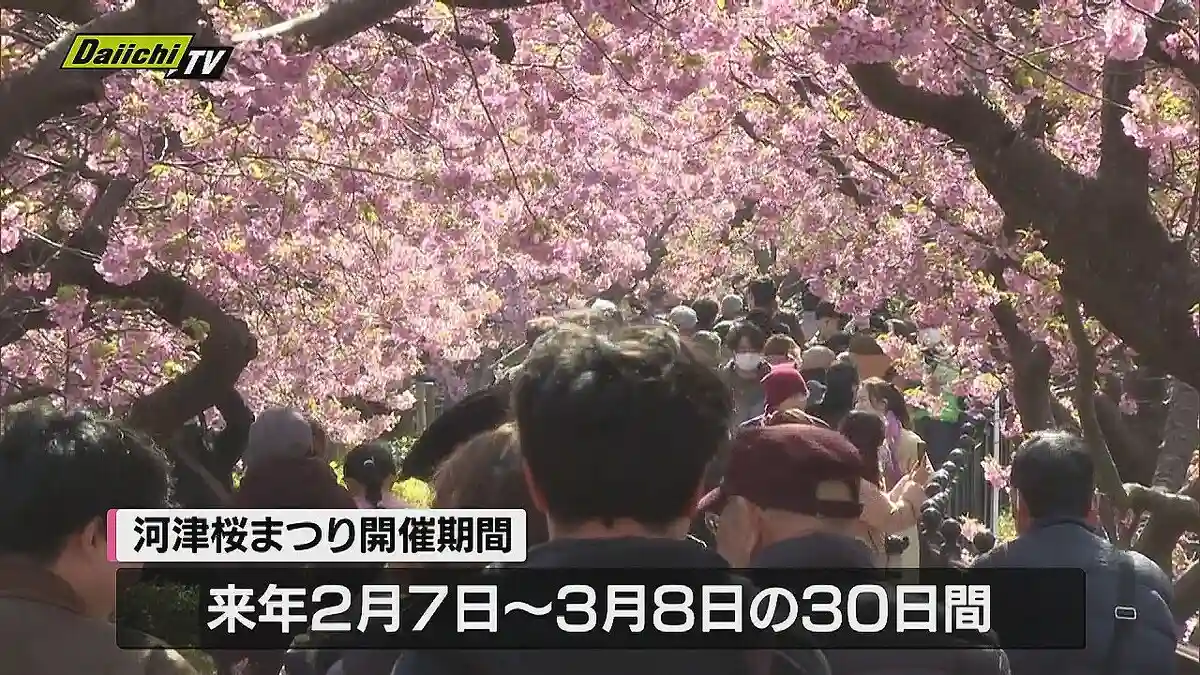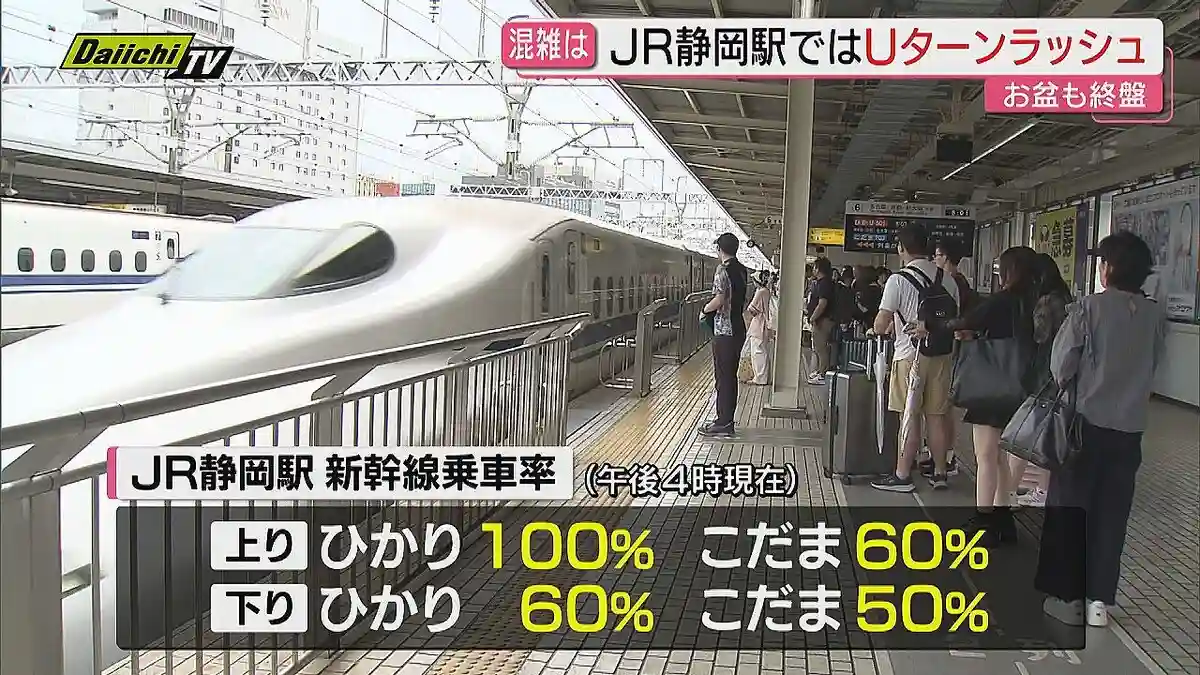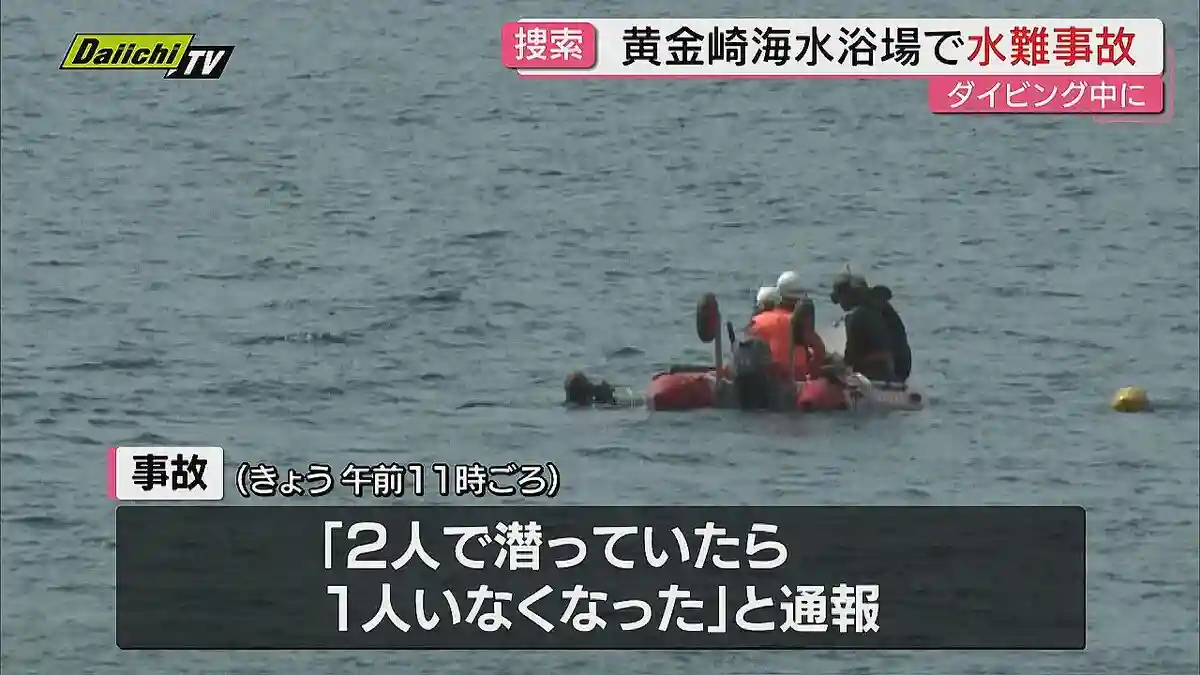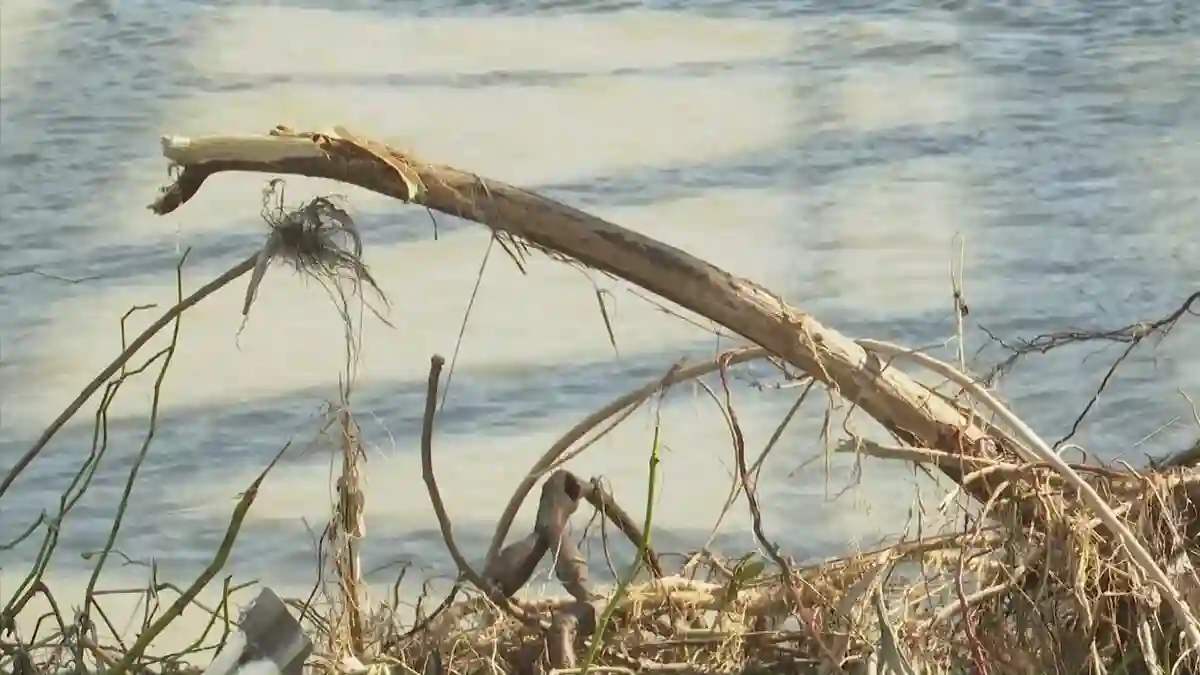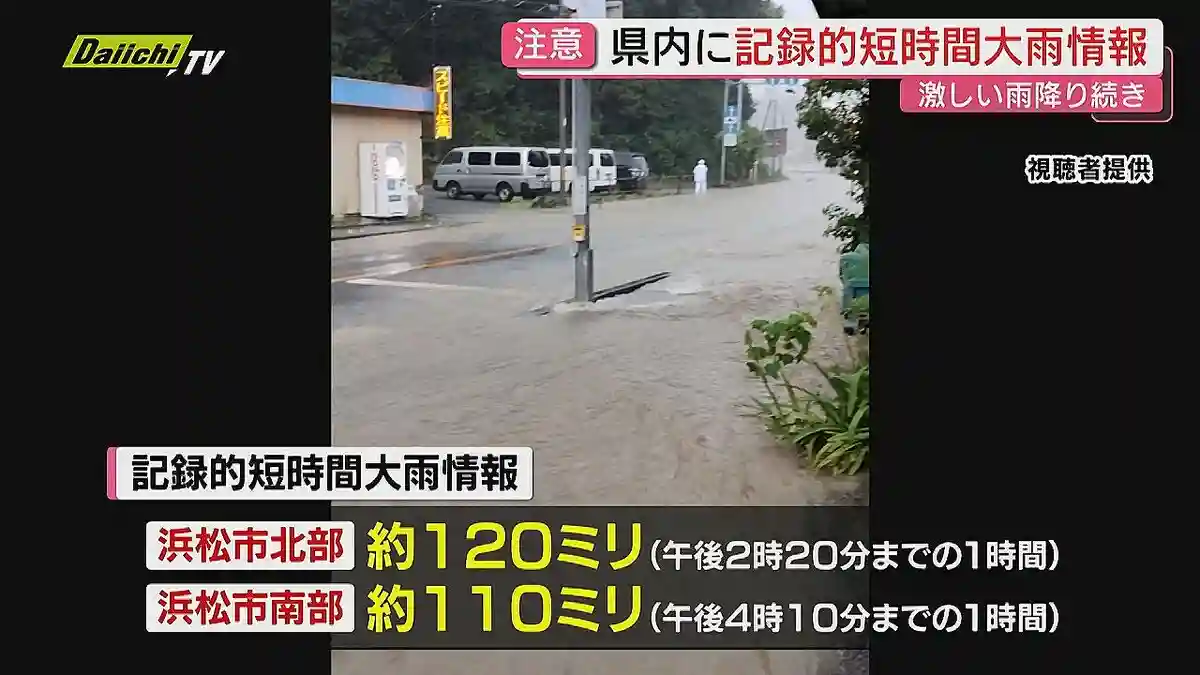「偏向報道」を非難したFCC委員長 まるでエミー賞受賞ドラマの『サクセション(Succession)』を見ているようだった。 2025年7月24日、アメリカの情報通信行政を管轄するFCC(連邦通信委員会)は、80億ドルにものぼるスカイダンス・メディアによるパラマウント・グローバルの買収を承認した。3人の委員のうち2対1の決定だった。2024年7月にスカイダンスとパラマウントの間で合併合意が成立して以来続いていた合併審査にようやく終止符が打たれた。 M&Aの承認というと、反トラスト法を扱う司法省反トラスト局やFTC(連邦取引委員会)が真っ先に思い浮かぶのだが、久しぶりにメディア業界における行政権力の中心としてFCCが前面に出た。FCCが関わったのは、パラマウントの傘下に地上波ネットワークの雄であるCBSが存在したためだ。今回の承認でCBSは合併後も変わらず地上波ネットワーク事業を継続できる。 FCCの権限の源泉は、公共財である周波数の利用の認可ならびにその監督にあるが、それを梃子にして放送局の認可だけでなく地上波ネットワーク事業の全体に干渉し、さらにはその親会社のメディア・コングロマリットにまで影響を及ぼすことができる。従来、この考えは牽制にとどまっていたが、トランプ2.0のFCCは、実際にそのカードを切ってきた。 合併承認の発表の際、FCC委員長のブレンダン・カーは、今後、スカイダンスの経営によってCBSの報道の公正性が向上することに期待を寄せると発言し、そのことによって従来のCBSの報道姿勢に対する不満を明らかにした。さすがはトランプ2.0の設計図と言われる『プロジェクト2025』の執筆者の一人だけのことはある。 特にカー委員長が強調した要件が、公平なジャーナリズムの実現とDEI(Diversity, Equity and Inclusion)の廃絶だ。要するに、これまで報道機関の間で業界標準と見られてきた「リベラルなジャーナリズム」を偏向報道として非難し、保守的でトランピズムに応じたものの扱いも忘れないようにしろ、という要請だ。これに対してスカイダンスは、CBSの報道中立性確保のためにオンブズマンを導入し、DEIの番組を控えると応じた。 老舗のパラマウント、『トップガン』最新作のスカイダンス 今回の合併により、新興の映像製作会社であるスカイダンス・メディアは、パラマウント・グローバルが抱える各種メディア事業部門、すなわち、映画スタジオ(パラマウント・ピクチャーズ)、地上波ネットワーク(CBS)、ケーブルネットワーク(MTV、ニコロデオン、コメディ・セントラル)等を傘下に収め、総合メディア企業へと転じる。合併後の「ニュー・パラマウント」のCEOには、スカイダンスCEOのデイヴィッド・エリソンが就任予定だという。 ドラマ『サクセション』を見ているようだった、というのはまさにこの点だ。 ジェシー・アームストロング創作のこのHBOドラマシリーズは、邦題が『メディア王 〜華麗なる一族〜』とあるように、ニューズ・コーポレーション率いるメディア王ルパート・マードックとその一族を模したものとして話題を呼んだ。「サクセション(Succession)」とは、遺産や威光の「継承」を意味し、しばしばシェイクスピア劇の『リア王』の現代版だと称賛されていた。 シリーズ終盤では、旧来のテレビや映画スタジオからなるメディア・コングロマリットが、新興のITプラットフォーム企業が仕掛ける買収攻勢に抵抗するうちに起こる悲喜劇が描かれていた。そのため、今回のパラマウント買収には、フィクションが現実を先取りしたような既視感があった。 この合併は、様々な点で2025年という今を象徴している。 ひとつには、創業2006年の新興の映画製作会社スカイダンスが、1912年創業のハリウッド映画メジャーの一角であるパラマウントを買収するところだ。新興企業による老舗の買収であり、それは「現行体制に不満を持つポピュリズム的破壊衝動」にも呼応している。 スカイダンスが製作に加わった作品というと、映画では『ミッション:インポッシブル』シリーズの過去5作に『トップガン:マーヴェリック』。いずれもトム・クルーズ主演のヒット作だ。あるいはAmazon Primeのオリジナルドラマシリーズである、トム・クランシー原案の『ジャック・ライアン』。基本方針は、ハリウッドの過去のヒット作を掘り起こし、リブートし、新たなフランチャイズにしてシリーズ化していくというもので、他には『ターミネーター』や『スター・トレック』などの人気作品の再起動を試みている。今回、多数の映画アーカイブを抱えるパラマウントを手に入れたことで、新たに息吹を与えられる過去の名作が続出するのかもしれない。 だが『サクセション』を想起させた要素としてより気になったのは、今回の買収が、間接的にではあるが、テック資本によるメディア資本の制圧のように見えたことだ。それは、スカイダンスCEOのデイヴィッド・エリソンがオラクルの創業者ラリー・エリソンの息子だからだ。つまり、スカイダンスの背後にはいつでもアクセス可能な巨大なIT資本が控えている。そこからデイヴィッド・エリソンは、この合併をストリーミング時代に向けた、オールド・ハリウッドの飛翔機会として売り出している。 20世紀初め、映画の時代に誕生したハリウッド・スタジオは、これまでに何度もオーナーを変えては存続してきたが、多くの場合、オーナーが変わるだけでハリウッドの事業形態には手を出さないことが一種の不文律だった。その昔、ハリウッド・スタジオを所有することは、アート作品を所有することに近かった。ピカソの絵を所有するのと似て、所有すること自体が名誉なことと思われていた。 だが、今は違う。メディア技術の変容によってビジネスモデル自体が変わり、事業構造にも手を加えざるを得なくなった。デイヴィッド・エリソンは、単にストリーミング化の波に応じるだけでなく、人工知能革命を控えるTikTok時代にふさわしいメディア事業への変容を計画している。テクノロジーを中心に据え抜本的な改革を断行する予定だ。そうして合併後のニュー・パラマウントを、レガシーメディアの構造改革の雛形にするという触れ込みだ。あたかも『サクセション』終盤のITガイたちの売り込み口上を聞いているようなのだ。 大統領との裁判の「顛末」 このレガシーメディアのデジタル時代への変容という点で無視できないのが、オラクルの創業者で、合併後、新生パラマウントコーポレーションの共同設立者であるラリー・エリソンの存在だ。長年共和党を支持してきた保守派の彼は、トランプ大統領とも懇意の仲で知られる。保留されているTikTokの有力な買収先のひとつにオラクルの名が上がり、AIについても、ホワイトハウスで発表されたAI振興策である「スターゲイト」計画に加わり、AI用のデータセンターの建設を進めている。 実のところ、今回のFCCの承認にあたって、エリソン家とトランプ家の近さは承認条件を詰め、合併へと進むうえで大いに役立っていた。ホワイトハウスの望むようにCBSの舵を切り直したからだ。 トランプは昨年(2024年)、大統領候補という、あくまでも私人としての立場からCBSを訴えた。同局の老舗報道番組『60ミニッツ』が、民主党の大統領候補であるカマラ・ハリスに有利に働くよう編集した番組を放送したという理由で100億ドルを求める損害賠償訴訟を起こしたのだ。賠償額は後日200億ドルにまで上げられた。 この訴訟に対してCBSは、7月1日、1600万ドルの和解金の支払いで決着させた。過去の判例から見てCBSの法務は勝訴を見込んでいたが、この訴訟が継続される限り、トランプ政権下で、CBSの親会社であるパラマウント・グローバルとスカイダンスとの合併承認は難しいという判断からなされた和解だった。 いうまでもなく、この和解はCBSの製作陣の望むものではなく、和解成立後、『60ミニッツ』のエグゼクティブ・プロデューサーのビル・オーウェンは辞任し、CBSニュースのCEOのウェンディ・マクマホンは退任させられた。 親会社の都合で実現した和解の余波はこれだけではなかった。人気コメディアンのスティーブン・コルベアはこの和解について、さっそくその日の夜、「A Big Fat Bribe(大きく太った賄賂)」とコケおろしたのだが、その3日後、彼の番組である『The Late Show with Stephen Colbert』の今季いっぱいでの打ち切りが発表された。来年5月をもってCBSでの放送は終了となる。 そして、この発表からほどなく件の合併承認が公表された。となると、合併を認めてもらうために、スカイダンスがトランプ2.0のメディアバッシングの意向に応じたと捉えるべきなのだろう。 トランプは昨年12月、ABCとの間でも1500万ドルの和解を取り付けていた。同社の著名司会者であるジョージ・ステファノプロスに名誉毀損の損害賠償を求めた訴訟の和解である。 言いがかりのような訴訟を起こし、賠償金の額を釣り上げることで、相手が訴訟期間を長引かせることを避けるため、和解金で解決するよう仕向ける、よくある法務戦略のひとつだ。しかも、私人として起こした訴訟でも、大統領就任後なら和解による解決が提案されるはずと読んだうえでのものだ。それが、政権中枢である大統領が相手になったときの訴訟の顛末である。地上波放送ネットワークの存続のためには、放送免許の継続が必須だからだ。 今やテック支持にシフトしたトランプにとって、従来のマスメディアを使った報道機関はすべてバッシングの対象である。すでに公共放送のPBS(テレビ)とNPR(ラジオ)への政府予算もカットされた。主流メディアの受難の時代だ。気がつけば四面楚歌。「ロングテイル」とはこういうことだったのか、と改めて思い知らされる。 ニューヨーク以外の土地の人びとの文化や価値観、もっといえば「言い分」にも日の目を浴びるチャンスがある。それこそがイーロン・マスクが崇める「絶対的な表現の自由」の本質だ。その結果が、百家争鳴ならぬ「億家争鳴」状態の到来である。収拾がつくはずがない。一なる権威のカトリック教会に楯突いた宗教改革運動に近いし、アメリカの文脈で言えば、そのプロテスタントの精神を、個人レベルで鼓舞しあった「大覚醒運動」に似ている。文化戦争はインターネットを得て、個人個人が言葉の刃を振るう「宗教戦争」に転じた。その急先鋒が、実際にキリスト教に帰依している人たちであることはもちろんだが、アメリカ人に総じて見られる「俺様カルト志向」に火をつけることになった。 CBSに求められる「多様な視点」 残念ながら民主党は、「億」あるうちの「一」、せいぜい「十」程度の価値観しかカバーできていない。それが「主流」ということだ。アメリカが不幸だったのは(あるいは賢かったのは?)連邦で権力を振るう政党を、民主党と共和党の2つに絞ってしまったことだった。「億」の声を「一」に縮約させられるよう最終的に二択にまで絞り込む政治装置をつくりあげた。 先述のように、FCCは今回の合併承認にあたり、合併後のCBSが多様な視点を扱うことを求めた。これはFCC内の右派的には、Wokeを排してMAGAを取り込む、ということでもある。これまで地上波ネットワークは、拠点のニューヨークが民主党支持のブルーステイトの筆頭ということもあり、リベラルで、時にプログレッシブ寄りの言説を流してきたが、インターネットの普及でメディアの脱中心化が進んだ現在、ニューヨークに偏った視点だけでは十分ではなくなった。代わりに、可能な限り全米各地の価値観をとりいれろ、ということで、これはかつてのCNNの創業精神を思い出させる。 CNNは、ニューヨーク発のニュースネットワークに満足できない南部人テッド・ターナーが1980年にアトランタで始めたが、1996年にTime Warnerに買収されたことで、ニューヨークのフレーバーに変えられてしまった。当時のメディア資本の力はそれくらい強かった。だが、それも脱中心的なインターネットが普及し、スマフォによる常時アクセスが社会標準になることで変わってしまった。 ロングテイルは怖い。従来のメディアの中心地ニューヨークもワンノブゼムにおちる。ニューヨーク・フレイバー以外のテイストがメディアで普通に楽しめるのが現代である。テッド・ターナーの悲願の達成であり、「表現の自由」の達成である。 だからここにあるのは「認識のズレ」だ。 やっと好きなことを言って広めることができるようになった者たちに、好き勝手言うのはやめて周りのことも考えろ、などと指摘しても通じない。ましてや制約(=規制)を受け入れろ、など聞く耳を持たない。クールマインドの欠如がポピュリズムの本質で、沸騰こそがポピュリズム。とりあえず「反権威」「反エスタブリッシュメント」を言っておけば連帯できる。そのうえで、対リベラルとして数の上で凌駕、とまでは言えないが、拮抗するところまで来たのがトランピズムである。メディア変貌によるチャンスをテレビマンだったトランプは最大限利用した。 「エンタメの権威」の終焉 ところで、今回のスカイダンスーパラマウントの合併は、メディアビジネスに大きな断絶をもたらす。その近未来への影響を理解するために、パラマウント・グローバルの歩みを見直しておきたい。実はこの点こそ、今回の買収からドラマ『サクセション』を想起した理由だった。政治とメディアとテクノロジーの交差点で起こる悲喜劇だ。 その合併劇の中心は、合併の一方の当事者であるパラマウント・グローバルの前身であるヴァイアコム(Viacom)であり、このメディア・コングロマリットを一代で築いたサムナー・レッドストーンである。彼は2020年8月に97歳で死去し、その事業を継承した娘のシャリ・レッドストーンが、今回の売却を決定した。 『サクセション』というと、Fox newsを連想させる作中のニュースチャンネルATNの存在感が大きかったため、Foxのオーナーであるルパート・マードックが想起されることが多かったが、サムナー・レッドストーンとヴァイアコムの逸話も『サクセション』の元ネタのひとつだった。 パラマウント・グローバルの前身であるヴァイアコムは、サムナー・レッドストーンが家業の映画館ビジネス(=ナショナル・アミューズメント社)を通じて買収に買収を重ねて築いたメディア帝国だった。その快進撃は、CBSの元子会社であるヴァイアコムを、1987年にレッドストーンが買収したところから始まった。 もともとヴァイアコムは、1971年にCBSのシンジケーション部門(ローカル局にCBS製作の番組を再販売するビジネス)がスピンオフしてできた番組販売会社だったが、ケーブルテレビの登場とともにケーブルネットワークビジネスに参入し、レッドストーンが買収するまでに、MTVやショウタイムなどのケーブルチャンネルを有していた。 以後、レッドストーンは、ケーブルテレビの成長を梃子にして1990年代にメディアビジネスの買収を次々と実現させ、ヴァイアコムを新興のメディア・コングロマリットに成長させた。それは1980年代から1990年代にかけてケーブルテレビが急速に普及していく時代の波に上手く乗ることで実現された。地上波テレビネットワークがカバーしきれなかったニッチな嗜好を満たす番組やチャンネルのニーズを満たすことがビジネスチャンスにつながった時代だった。1990年代に入る頃には、ケーブルテレビはアメリカのテレビ視聴の標準になり、もはや放送波を受信する視聴形態は少数派となった。多チャンネル時代の到来だ。 その多チャンネル化の勢いに乗り、レッドストーンは、1994年にハリウッドメジャーのパラマウントを買収した。同年、ビデオレンタル最大手のブロックバスターも傘下に収めた。ついに1999年には、ヴァイアコムのかつての親会社であったCBSを買収し、名実ともにメディア・コングロマリットの仲間入りを果たした。 だが、メディアテクノロジーの変化に伴うレッドストーンの躍進もここまでだった。彼の才覚が発揮されたのはケーブルテレビが切り開いた多チャンネルビジネスまでで、インターネット時代の対応には出遅れ、最終的には今回の買収劇のように身売りするしかなくなった。店舗をもたないオンラインDVDレンタルから始めたNetflixがストリーミングの先駆者になったことを思うと興味深い。要するにレッドストーンの経営判断ミスである。 娘のシャリが引き継いだときには手遅れで、気がつけば、Netflix、Amazon、AppleのIT勢、Disney+、Hulu、maxのハリウッド勢、YouTube、TikTokの新興勢、と新旧の競合に囲まれていた。事業形態も、参加型の広告モデルと、その圧力に応じてやむなく生まれた課金(「サブスク」)モデルへの2本立てが標準となった。 こうした多メディア化が、テックのイノベーション礼賛の中、とどまるところを知らず継続された結果、メディアの断片化だけが一方的に進み、個々のメディアレベルでは、かつての映画やテレビが確立した「エンタメの権威」としての絶対的な地位はどこも享受できなくなった。権威の脱中心化である。 メディア「億家争鳴」の時代に このようにヴァイアコムの盛衰はケーブルネットワークとともにあった。その波を作ったのが、実はFCCの規制の舵取りだった。それは今後のメディアビジネスを見通すうえで何かと示唆に富む。中心にあったのは「フィンシン・ルール」である。 フィンシン・ルール(“fin-syn” rule)とは“The Financial Interest and Syndication Rules”の略称で、全米への番組流通を「寡占」する地上波ネットワーク(ABC、CBS、NBC)が、社外制作番組の配給や販売権、あるいは所有権といった「Financial Interest(収益権、収益機会)」を持つことを禁止し、自社制作番組についても放送後一定期間で市場に開放する(“Syndication”)ことを求めた、FCCが定めた規制のことだ。 地上波ネットワークが番組制作会社に圧力をかけることを阻止し、番組の製作部門と流通部門が独立して成長することを期待してのルールだった。番組制作会社の多くが、ハリウッドの制作会社の子会社であったことを考えると、ニューヨークに集中した(映画から見たら新興の)テレビネットワークから、ロサンゼルスに集中した(テレビという映画上映ビジネスから競争を仕掛けられた)ハリウッド・スタジオを保護するものでもあった。新旧のメディアビジネスの間で均衡を制御するための政策だった。 フィンシン・ルールは、地上波ネットワークが力をもった1970年に導入され、ケーブルテレビが全米に普及した1995年に廃止された。このルールの導入で、レッドストーンが後に買収するヴァイアコムがCBSからスピンオフされた一方、その廃止によって、パラマウントを傘下に抱えたヴァイアコムが、かつての親会社CBSを買収することができた。規制の有無が、業界秩序を決めていた時代に、その規制の舵取りに寄り添いながらレッドストーンはビジネスチャンスをものにしていった。 以前、80年代以降、アメリカのマスメディアの両極化を促した出来事として「フェアネス・ドクトリン(Fairness Doctrine)」の廃止について触れた〈「極右」と化したイーロン・マスクの影響力に欧州のインテリたちが震えている…!〉ことがあったが、それと同様、フィンシン・ルールの撤廃によって、アメリカのマスメディアの地平は、ビジネスとしても視聴環境としても大きく変貌した。端的に、リベラルで中立性を重んじるジャーナリズムの流儀は脇に追いやられ、代わりに、何であれ市井の声を拾いあげる「表現の自由」が絶対善になった。特定の論調や価値観で番組をまとめることは、それによって「封じられた声」の存在を声高に主張することで、真っ向から否定される。その結果、従来、ジャーナリズムの「公平性」の内実も書き換えられた。 FRBのように連日報道される「規制機関(institution)」と違い、FCCは注目を集めることは少ないが、しかし、そのルールの匙加減でメディアのあり方は大きく変わるのである。 インターネットは、ケーブルテレビが開いた「多声性重視の報道」を極限まで引き伸ばし、結果として、誰もが一票を持つのと同様、誰もが発言権を持つ、という風潮を生み出し、その延長線上で「多数決」ならぬ「多声決」というメディア状況をもたらした。最も多くの「賛同」を得られたものが「正しい」ものとして認定される。しかも、インターネットの迅速な情報流通とそれに伴う絶え間ない現実の流動化を通じて、「正しい」ことはつねに暫定的なまま、とりたててその中身について検証されることもなく、次の「正しさ」へと流されていくことが社会の常識となった。インターネットの中で誰もが発言することで、あたかも市場において価格がひとつに収斂していくように、言論の「正しさ」も収束していくように、言論も「正解」に収束していくような錯覚を抱かせた。だが、そんな「正しさ」は、求めたそばから始まる次の「正しさ」の追求によって遮られ、その連続によって収束することなくただただ発散していく。 スカイダンスが、CBSを含めて構築しようとするストリーミング・ベースの新メディアは、このような流動性の高いメディア環境下で試みられる。メディアの変容は、それとは気付かないうちに、人びとが見る世界の相貌を変えててしまう。スカイダンスは「億家争鳴」の時代に、一体どんなメディアの景観を生み出すのだろうか? もっと読む:トランプは真性の「加速主義者」だ…ロビイングでアメリカ経済の覇権を狙う「クリプト・ブロ」の繁栄を祝福する理由 「極右」と化したイーロン・マスクの影響力に欧州のインテリたちが震えている…!