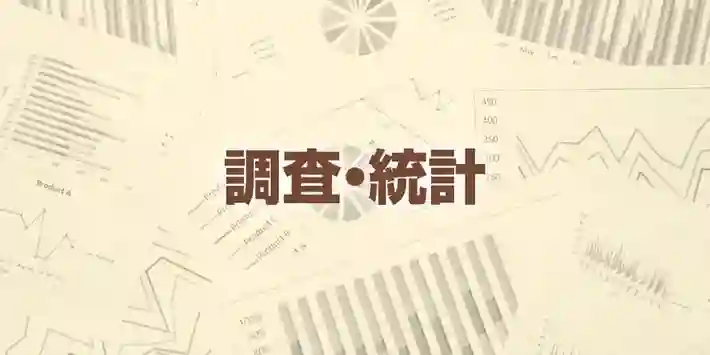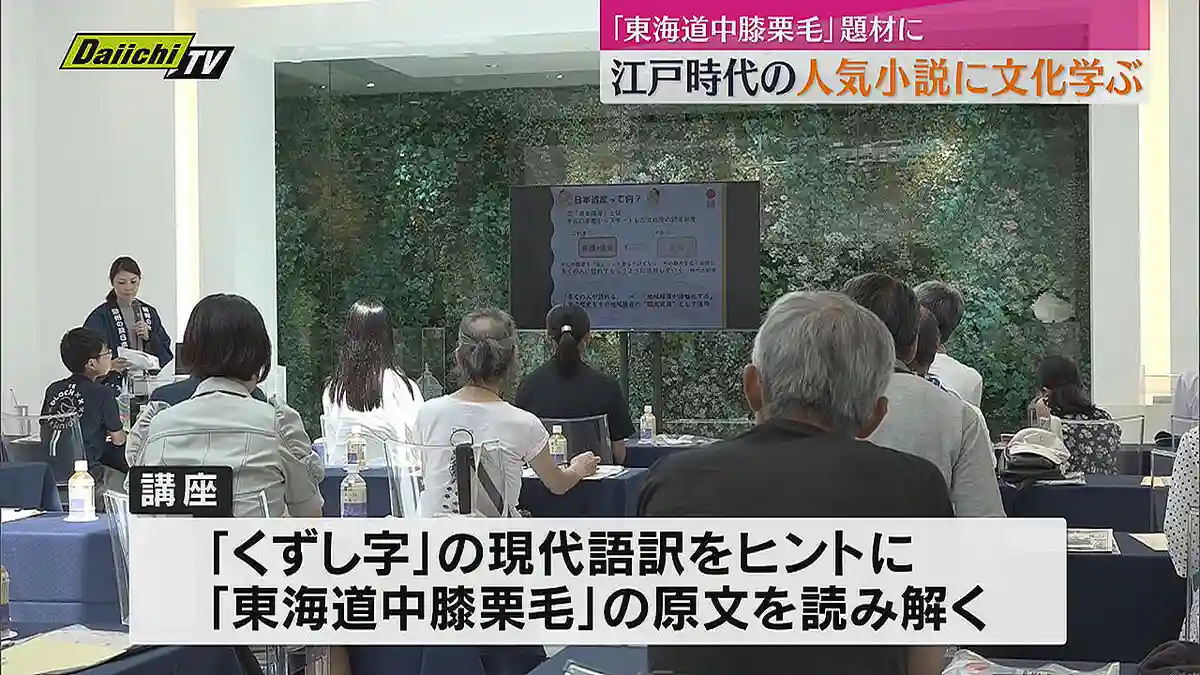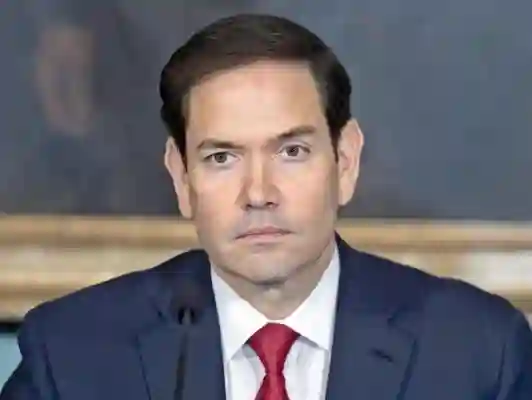「もう普通のサラリーマンが新築マンションを買える時代でない」と言われ久しい。実際、不動産経済研究所が発表した、2025年上半期の東京23区の新築マンションの平均価格は1億3064万円。年収2000万円で何とかローンの審査が通るかどうか、という水準だ。こうした状況下で“新築信仰”の強い日本でも、“築浅中古”や“駅近中古”のマンション購入を視野に入れる人が急増している。その際に「見落としがちな点」があるという——。 *** 【写真を見る】たった5年で驚くほど値上がり…どんどん高くなる1平方メートルあたり「管理費・修繕積立金」の変遷 主要都市への人口集中が続く そもそもなぜ、東京都心で不動産価格の高騰が収まる気配がないのだろうか。 「立地」や「築年数」、「平米数」や「設備」に気を取られると見逃してしまう「重要ポイント」とは 「少子高齢化で住宅需要が減少し、不動産価格が値下がりしていく、という見方は日本全体で見れば当てはまるかもしれませんが、都心や主要都市ではむしろ、人口減少が住宅価格を押し上げる要因になり得ることがあるのです」 そう解説するのは、不動産コンサルティング事業を展開する「株式会社さくら事務所」の山本直彌氏だ。 「人口減少の局面で、過疎地など人の少ない地域ではだんだんと生活に必要なインフラが提供されないようになり、居住自体が難しくなるところが出てきます。すると何が起きるかと言うと、医療や教育、スーパーマーケットなど生活インフラの集約された主要都市に人口が集中していくのです」(山本氏) 中には、将来的にはAIやIoTなどの先端技術を用い、都市インフラを効率的に管理した「スマートシティ」に人口が集中し、それ以外の場所ではほとんど人が住まなくなるという未来を描く専門家もいるそうだ。 「それはまだまだ未来の話ですが、主要都市への人口集中は既に始まっています。その際たるものが東京の都心部ということです。新しい駅ができるとか、新しい路線が通るとか、そうしたことが起きない限り、立地の条件は変わりません。さらに都心への人口集中が進む中で、絶対数の限られた都市部の物件を人々が奪い合う形になるため、今後も不動産価格が維持向上する可能性が高いのです」(同) 新築マンションの供給量はますます先細り… 都内にある未開発の土地は既に皆無に等しく、新築マンションの多くは古い建物を壊しての建て替えがほとんどだ。 「用地取得費や建材費の高騰に加え、解体や建築には人件費の高騰が影響し、マンション建築費用は高くなる一方です。そのため、デベロッパーが新築マンションの販売で利益を確保するためには、販売価格を値上げするしかありません」(山本氏) その結果、最近は共用部の仕様を極力シンプルにしたり、60平米台の3LDKが増えたり、なんとか販売価格を抑えようと、デベロッパーの苦肉の策が続いている。 「仕様がすごく良いわけでもなく、専有面積も少し狭い。そんな物件を“新築”という理由だけで買う必要があるだろうか、と考える人が増えたことで最近は築10年以下の“築浅中古”の需要が急増しているのです」(同) むしろ、ひと昔まえの物件の方が、共用部の仕様がしっかりしていて、居住スペースも広々しているケースも多いという。 「今後、新築マンションの供給量はますます先細りしていくと見られています。欧米のように、日本でも住宅を購入する際に中古物件が中心になる“ストック型”のマーケットに移行していくでしょう」(同) ただ、移行期ゆえに「立地」や「築年数」、「平米数」や「設備」といった情報に隠れてしまい、重要なポイントが見落とされているという——。 マンション市場は今後「ストック型」に移行へ 「それが“管理状態”です。マンション市場がストック型のマーケットに移行していく中で、立地や築年数と合わせ、マンション管理が重要なファクターになる時代がやってきます」(山本氏) 例えば、立地や間取りが気に入って、購入を検討する物件があったとする。内見の日が決まり胸を躍らせ現地に行くと、共用部の廊下にはゴミが落ちていて、エレベーター内も見るからに古い…。そんな物件は避けるべきなのかもしれない。 「そのマンション全体がどれだけちゃんとメンテナンスされ、管理されてきたかということは、実は将来の資産価値に直結するのです。中古物件の市況が活発化するにつれ、管理状態に対する相対評価はますます重要になるでしょう」(同) ただし、不動産管理は目に見えるハード面だけでなく、ソフト面も重要なのだという。 「実は、マンション管理の本質は、見た目の美しさや設備の状態といったハード面よりも、組織運営や財政状況などのソフト面にあるのです。なぜかと言えば、管理不行き届きが結果として目に見えるのはハード面ですが、それを顕在化させるのはソフト面にあるからです」(同) ソフト面において重要な要素が「お金」だという。 「特に重要なのが修繕積立金です。仮に同じ1億円積み立てられている状態であっても、来年に大規模修繕工事を控え、なくなる予定である1億円と、売買の前年に大規模修繕工事が済んでいて、それでも1億円の残高がある状態では話が全然違ってきます。大事なのは、管理会社・管理組合として長期修繕計画をしっかり作成し、それを5年に1回の物価変動なども含めて適切に見直しを行えているかどうか。長期修繕計画上で資金不足に陥っているマンションは将来的に売却の“足枷”となる可能性があります」(同) しかし、SUUMOなどの不動産ポータルサイトを見るだけでは、長期修繕計画の内容まで確認することはできない。 「買い主が自ら“見せてほしい”と言うしかありませんが、現状では開示義務がないため、見せてくれるように粘り強く交渉する、または管理の重要性を理解している仲介業者に依頼するしかありません。例えば購入時には修繕積立金が月額1万円でも、長期修繕計画上の資金計画において購入から10年後に月額4万円になる予定がある場合、10年後の時点でその物件の流動性がガクンと下がる可能性があるのです」(同) 長期修繕計画は行政による標準となる“ひな型”があるが、実際はマンションの管理会社がそれぞれ独自に作っていて、様式もそれぞれ異なるという。また、中古マンションの販売を手掛ける仲介業者が修繕計画の内容までケアすることは難しいようだ。 「不動産の知識だけではダメで、建築や設備に関する知識も備える必要がある。不動産の仲介営業の方にそこまで求めるのは酷でしょうから、買い手が見定めるしかありません。最近は購入を検討する中古マンションの修繕計画の妥当性について、アドバイスして欲しいという相談も増えています」(同) 大事なのは“嫌われる勇気” マンションの管理方式については、最近増えている「外部管理者方式」にも注意が必要だという。マンションの管理組合が、従来の区分所有者による理事会運営に代わり、管理会社を含めた外部に管理者業務を委託する方式で、デベロッパーの関連会社が指名されるケースも多い。 「外部管理者方式は、もともとは役員の成り手不足を補ったり、住民の高齢化に対応したりするために広がった仕組みです。しかし、近ごろは都心部を中心に、現役バリバリで働いていてマンション管理にまで手の回らない住人に対する“サービス”として提供しているケースが増えていますね」(山本氏) しかし、外部管理者はあくまでも物件とは関係ないいわば他人。業務が管理者契約している範囲内に留まってしまい、100点満点の管理を求めるのは難しくなるという。 「その結果、良くて70点、悪いと50点ぐらいの管理状態になってしまうことも。必要以上に修繕計画の費用を水増しするといった利益相反が起きやすい構造も問題視されています」(同) 利益相反については、国もワーキンググループを作って対策に取り組んでいるが、今後も付きまとう課題となりそうだ。では、外部管理者方式のマンションの住人が取り得る対策は、なにかあるのだろうか。 「“監事”が管理者の業務執行や会計状況を監査する役割をしっかりと機能させることが、外部管理者方式を有効活用していく上で非常に重要になります。ただ所有者が監事になったとしても、建物の維持管理や会計などの専門的知識を持ち合わせているケースは稀ですので、外部アドバイザーの起用なども有効な手段になってきます」(同) ちなみに、区分所有者総数と議決権総数それぞれの3/4以上の承認を得れば、管理規約を変更し外部管理方式を解除することも可能だが、実際にはそれほど簡単な手続きではない。それでは、50点や70点の管理状態を改善するにはどのような方法があるのだろうか。 「私はマンション管理において非常に大事なキーワードは“嫌われる勇気”だと思っています。結局は誰かが手を挙げて問題提起しないと管理状況は改善されません。そうした声が1人、2人、3人と増えていけば、外部管理者や管理会社も対応を考えざるを得ません。“マンション管理は1日にしてならず”という言葉に代表されるように、管理状況の改善は長いスパンで見る必要があります」(同) せっかく「外部管理者方式」なのに、手間がかかってしまうのは困るという人もいそうではあるが——。 「管理状況に不満があるとしたら、今からでも取り組まないと、もし5年後に自分がマンションを売却しようとなった際に、思ったような価格で売れないという事態にもなりかねません。嫌われる勇気を持って思ったことをちゃんと意見し、草の根的に活動していくことが、マンション管理においては非常に重要なのです」 *** 〈【【“沸騰”不動産の対処術】都内で北千住・浅草が急上昇の謎…「の」の字の法則で読み解く値上がりエリアの「実名」と不動産選びの「新常識」】では、都内の不動産価格で起きている“西低東高”の傾向について、不動産業界で受け継がれる“ある定説”を元にした深読み解説をお届けする。不動産“沸騰”時代の住まい選びに欠かせない“新常識”とは——。〉 デイリー新潮編集部