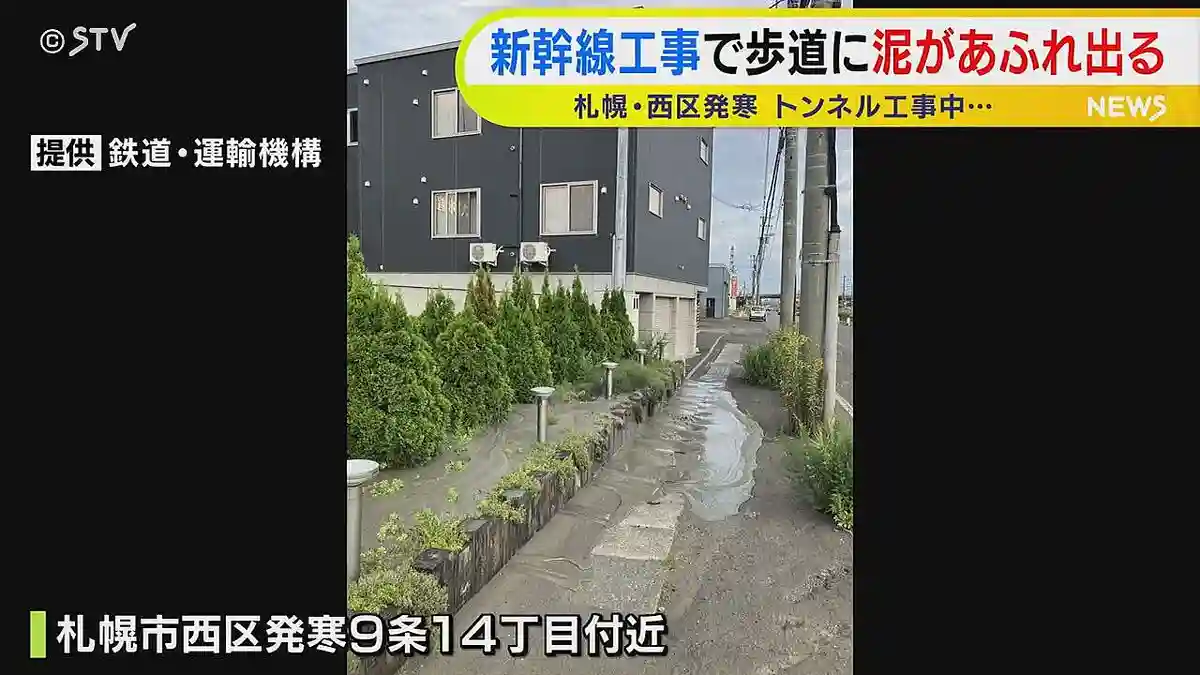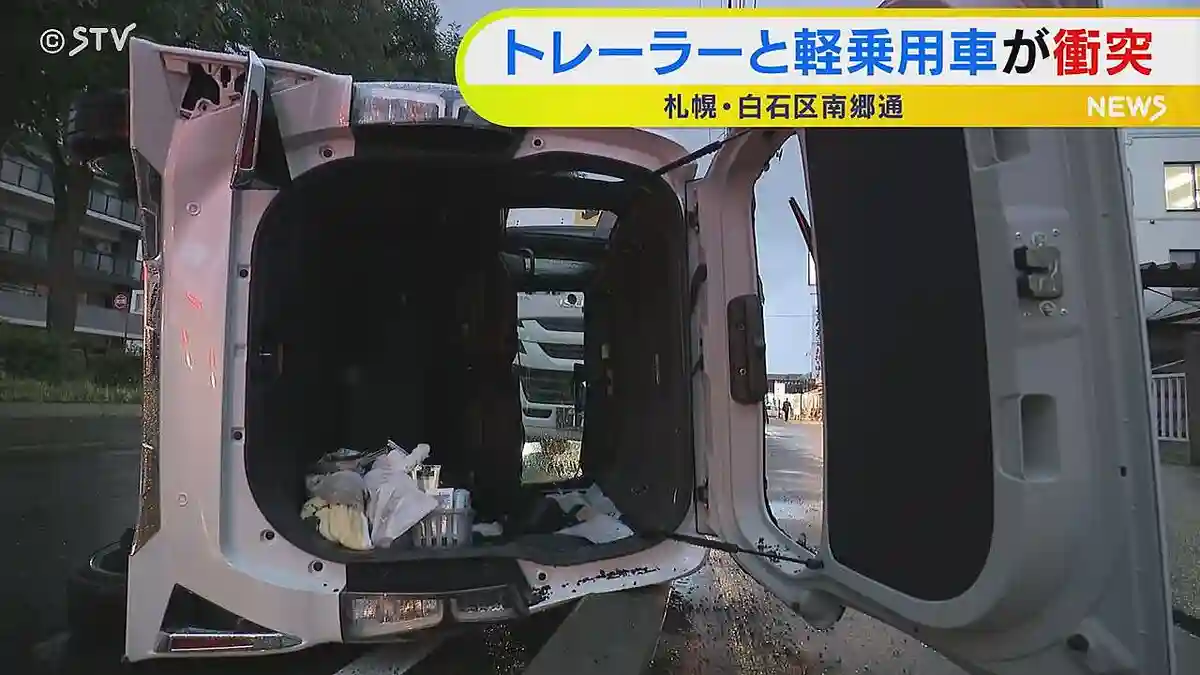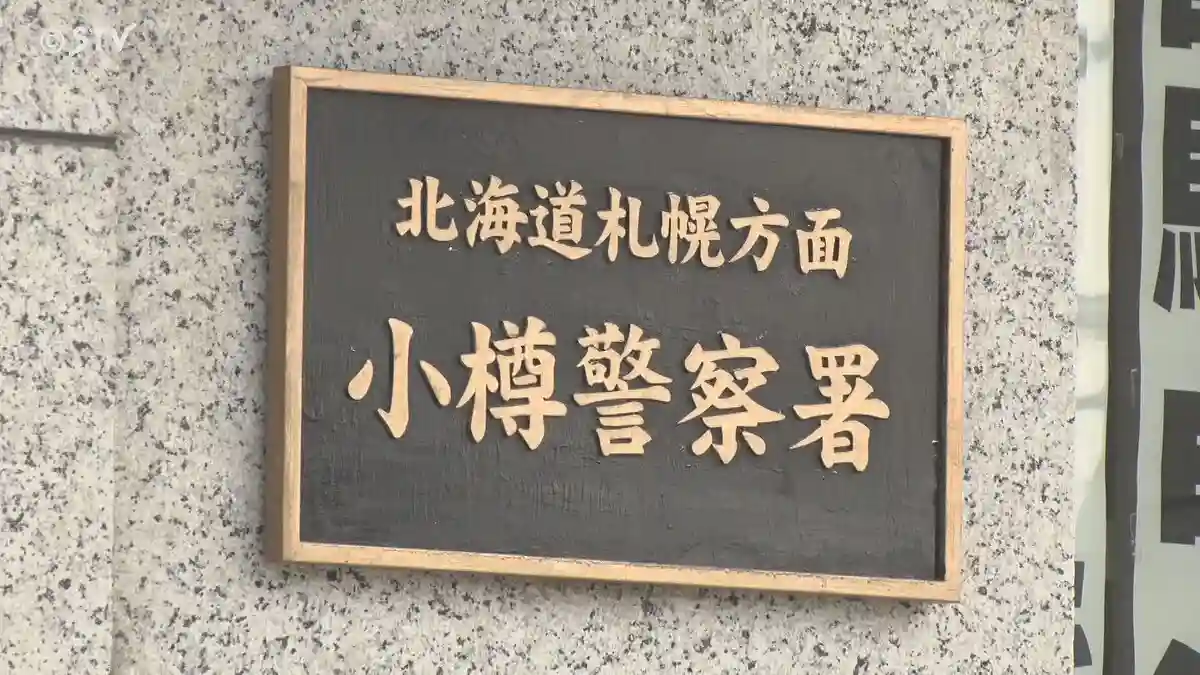未亡人というより婚礼の日の花嫁のよう… 日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。 世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。 日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。 イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。 彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。 19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。 例えば、バードは通訳の伊藤と現在の秋田県を旅している道中、六郷という町に立ち寄ります。〈イザベラ・バード40のタイトル・リンク入れます〉より引き続き、バードが日本の葬儀に出席し、感じていたことを同書より引用します(読みやすさのため、改行など編集しています)。 *** 未亡人はたいへんな美女で、遺体のそばに座っていますが、その位置は死者の両親のすぐ下座で、そのあとに子供たち、親戚、友人が青と白の翼のような衣装をつけて並んで座っています。 未亡人は顔を白塗りし、唇を朱砂で赤く染め、髪は念入りに結って彫刻を施した鼈甲のかんざしで飾っています。衣装は空色の絹の美しい着物と白い上質の縮緬の羽織、金色の刺繍を施した緋色の縮緬の帯で、未亡人というより婚礼の日の花嫁のようです。 実に衣装の美しさと青や白の絹地が多いせいで部屋は葬儀というより祭りがあるように思えます。すべての参列客が到着すると、茶菓が配られます。 香がふんだんに焚かれ、お経が唱えられ、墓場への移動がどたばたとはじまります。その間わたしはお寺の門のそばに場所を確保しました。 野辺の送りの行列には死者の両親は参加しませんが、行列に加わる会葬者はすべて親戚だとわたしは理解しています。死者の「死後の名前」を記した矩形の位牌が僧侶によりまず最初に運ばれ、そのあとにはべつの僧侶が蓮の花を運びます。 ついで10人の僧侶が経本のお経を読みながらふたりずつ並んでつづき、そのあとには台に載せ白い布をかけた棺を4人の男性がかついでつづきます。そのうしろには未亡人と他の親戚が従います。 棺はお寺に運ばれると台に安置され、香が焚かれ、お経が唱えられます。それから棺はセメントをまいた浅い墓穴に運ばれ、僧侶が読経するなか、土を地面の高さまで戻し、そのあと会葬者は散っていきます。 未亡人は華やかな衣装のままお供もなく家まで歩いて帰ります。泣き女を雇うこともなく、嘆き悲しんでいる気配はなにもありませんが、葬儀全体はこの上なく厳粛で謹厳なものでした。〔その後、主に貧しい人の葬列を何度も見ましたが、儀式の大半が省略され、式を司る僧侶はたったひとりでも、謹厳さは毎回とても目につきました。〕 僧侶への謝礼は2円から4、50円です。寺院のまわりにある墓地はきわめて美しく、杉の樹木も特別みごとです。石の墓碑でいっぱいで、日本のどこの墓地を見てもそうであるように、手入れが非常に行き届いています。墓穴が埋められると、ただちに実物大のピンクの蓮を立てます。また盆が置かれ、その上にはお茶または酒を入れた漆椀とお菓子が載っています。 *** さらに〈明治日本を旅したイギリス人女性が「宿屋」で「恐ろしいと感じた出来事」〉の記事では、日本の宿屋に泊まった時の体験について書かれています。 【つづきを読む】明治日本を旅したイギリス人女性が「宿屋」で「恐ろしいと感じた出来事」