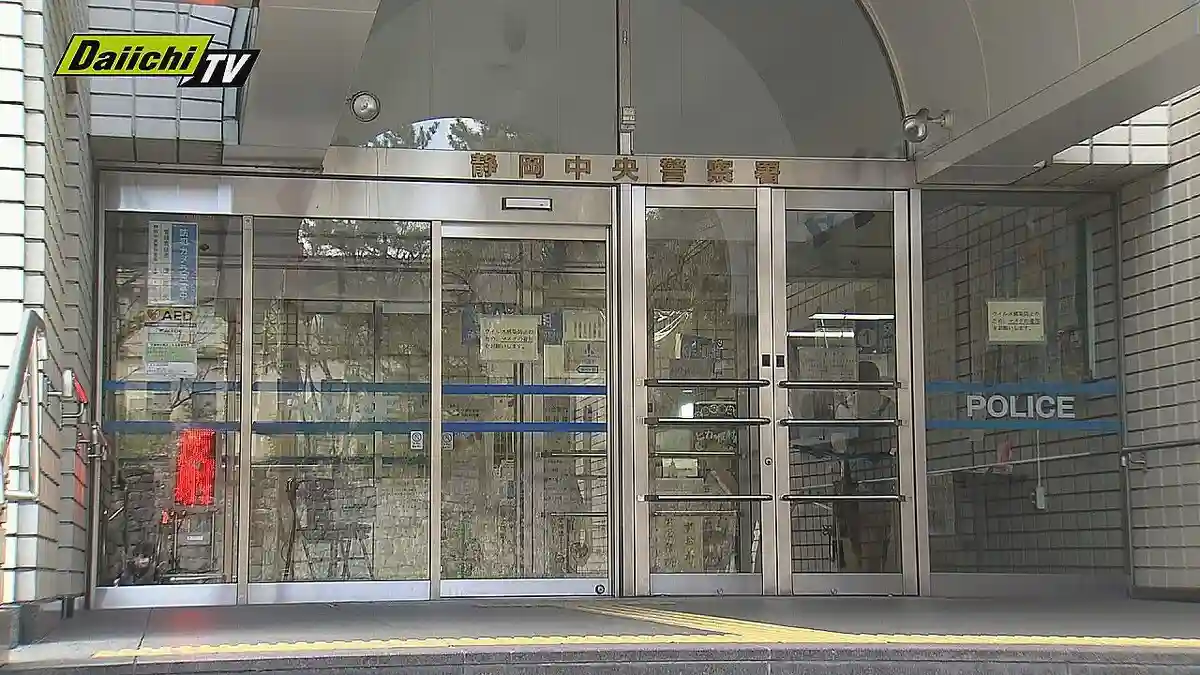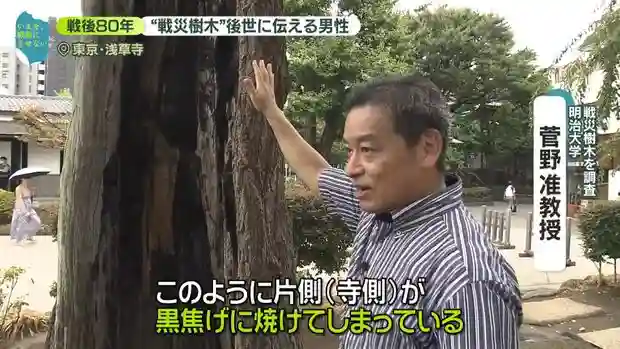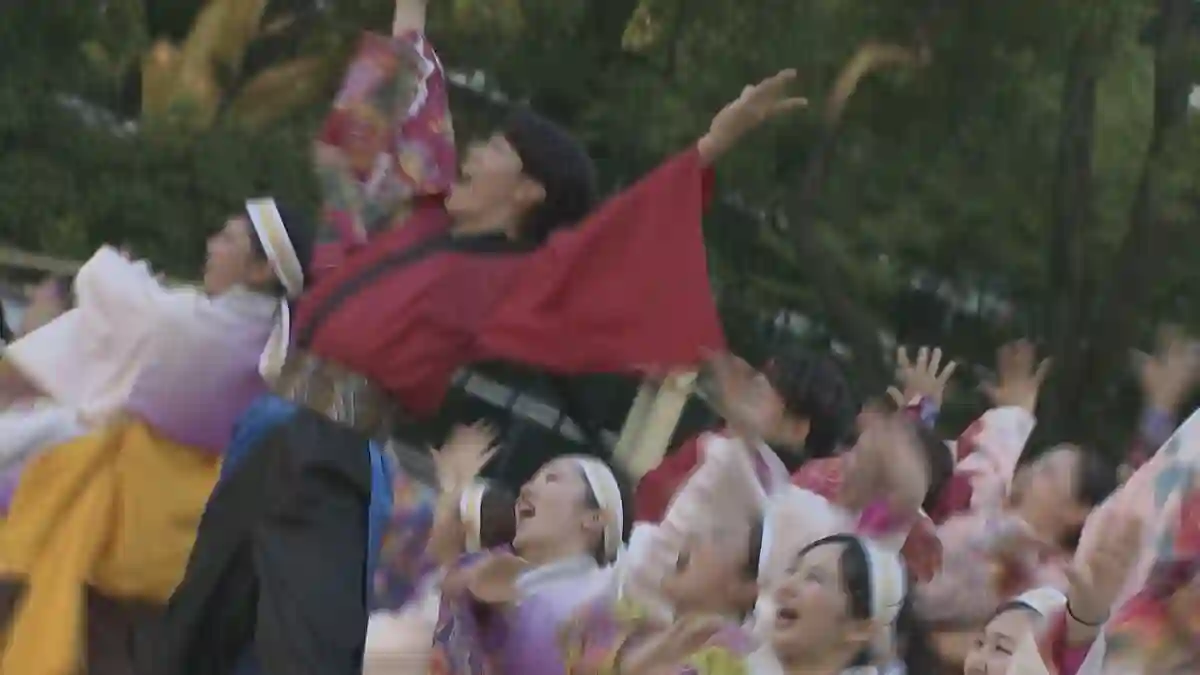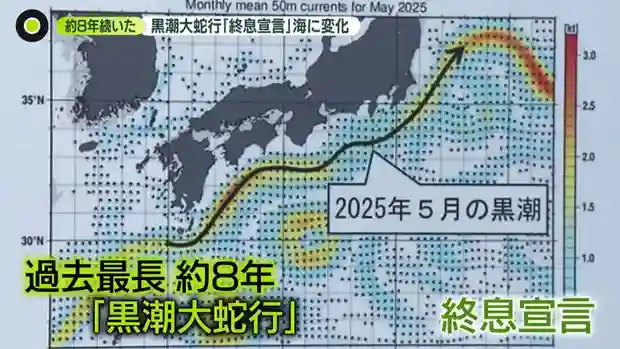8月30日は「富士山測候所」記念日です。かつて極寒の山頂で観測に挑んだ人々の物語や富士山噴火に備える最新の取り組み、意外な雑学まで富士山の空と大地の物語を見ていきましょう。(アーカイブマネジメント部 萩原喬子) 【写真を見る】東京都総務局が公開した、富士山噴火後の被害再現 富士山測候所と日本の安全を守る富士山レーダー 富士山に初めて測候所が建てられたのは1895年(明治28年)。気象学者である野中至(のなかいたる)が私財を投じて建設したのが始まりです。1932年(昭和7年)には中央気象台臨時富士山頂観測所が設立され、通年の気象観測が開始されました。富士山の観測は日本の防災にも大きく貢献してきました。特に重要な役割を果たしたのが、1964年(昭和39年)に設置された富士山レーダーです。 気象予報士 森 朗氏: 1959年の伊勢湾台風で甚大な被害を受けた日本は、接近する台風をいち早く観測する必要性を痛感し、富士山レーダーを設置しました。標高3776mの山頂に設置されたレーダーは日本の広範囲をカバーし、1999年に役目を終えるまで台風の監視にも大きな力を発揮しました。 富士山の測候所での仕事 富士山測候所で働く観測員たちの仕事はまさに命がけでした。極寒と強風に常にさらされ、物資の運搬も困難な過酷な環境に耐えながら、2か月に1度、20日間、泊まり込みで観測を行っていました。TBSには観測員に密着した映像が残っていました。観測所に行くまでが大変で物資や道具を乗せたブルドーザーと徒歩で向かっていました。ところが技術の進歩が過酷な環境での観測を一変させ、遠隔操作でデータを取得出来るようになり、2004年(平成16年)富士山測候所は無人観測施設となったのです。 気象予報士 森 朗氏: 富士山頂の最低気温は−38.0℃、最高気温は17.8℃。天候の急変で3日間行方不明になったり、下山の途中で骨折したりと常に危険と隣あわせだったそうです。 過去には秒速91.0メートルを記録したことも… みなさん「富士山の初冠雪」というニュースを聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。富士山には年中、雪があるように見えるのになぜ「初冠雪」があるのか、実は明確な定義があるのです。 気象予報士 森 朗氏: 一般的に「初冠雪は8月1日から翌年の7月31日までに山麓の気象官署から見て、山頂付近が初めて積雪などで白く見えること」と決まっています。ただ一年中いつ雪が積もってもおかしくない富士山は観測所の日平均気温の最高値が出現した日以降に初めて冠雪を観測した日となっています。去年(2024年)の初冠雪は11月7日。統計開始130年で最も遅い初冠雪となりました。 また富士山山頂は最大瞬間風速の記録を持っています。その最大瞬間風速は1966年(昭和41年)9月25日に記録した秒速91.0メートル。日本に上陸・縦断した台風26号が通過した際に風速計が捉えました。秒速91.0メートルという風を時速換算すると約328キロメートルになり、東北新幹線の時速320キロよりも速度が速いです。 さらに富士山にまつわる言い伝えで「富士山が笠をかぶれば近いうちに雨」という言葉があります。これはかなりの高確率で当たっており、実は70%くらい雨が降るそうです。 気象予報士 森 朗氏: さらに笠雲とつるし雲が同時に現れると約80〜85%にまで雨の確率が上がります。 富士山噴火、その時東京は…? 先日、東京都は富士山が噴火した場合の被害を具体的にイメージできるよう、被害を再現した動画をホームページで公開しました。富士山は最近5600年間に約180回噴火しており、単純計算で約30年間に1回の頻度です。ところが1707年の宝永噴火を最後に、300年以上噴火していません。国の富士山噴火の被害想定によると早ければ1〜2時間後くらいから火山灰が降り始め、東京23区や多摩地域では2〜10cm程度以上の火山灰が降る予測が出ています。交通インフラやライフライン、家屋や健康への影響、また備えの重要性を改めて訴えています。 気象予報士 森 朗氏: 富士山は活火山なのでいつ噴火してもおかしくない状況です。火山灰は積もると泥とは違うので洗い流せません。さらに火災など2次災害の心配もあります。どんな特性があるのか、今から調べて備えるのもいいかもしれませんね。