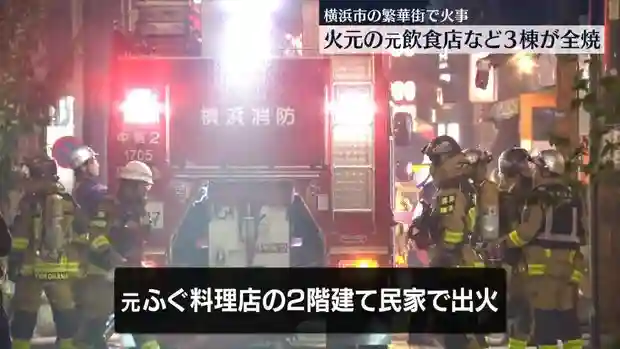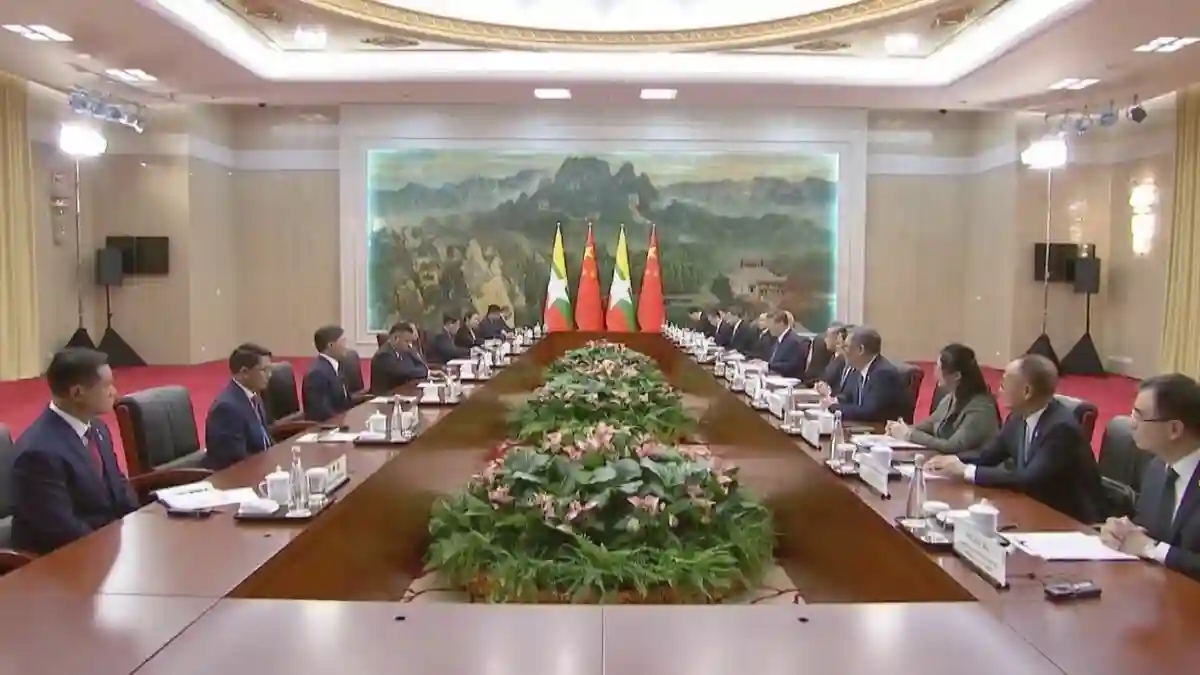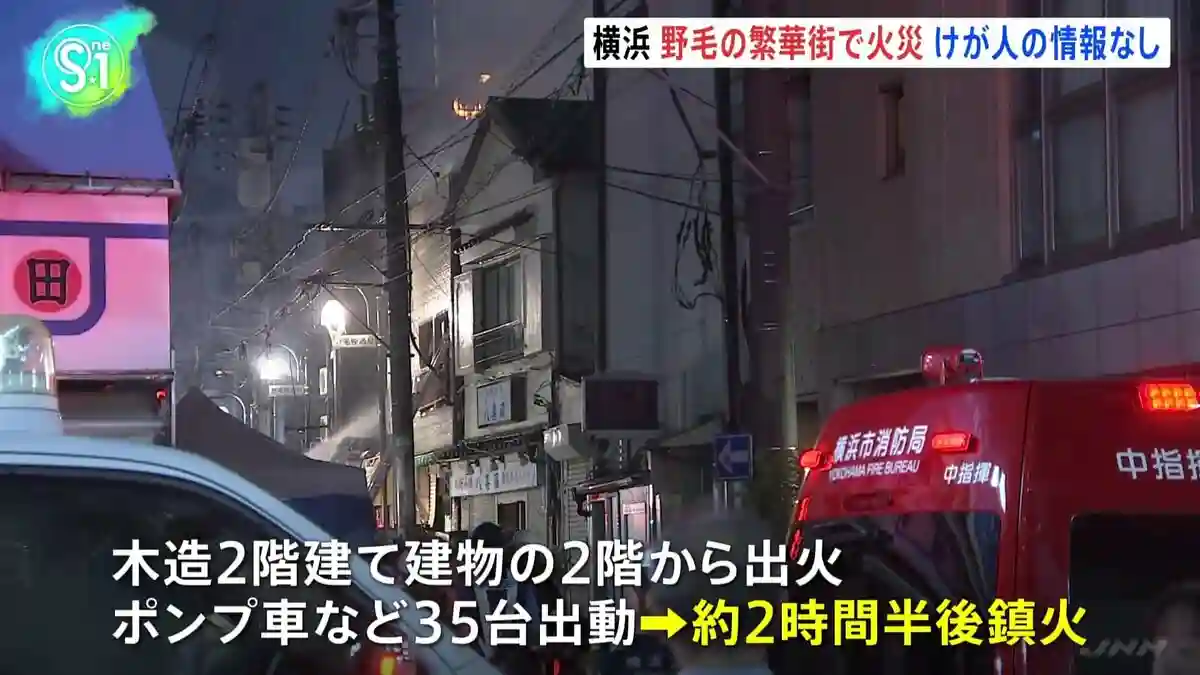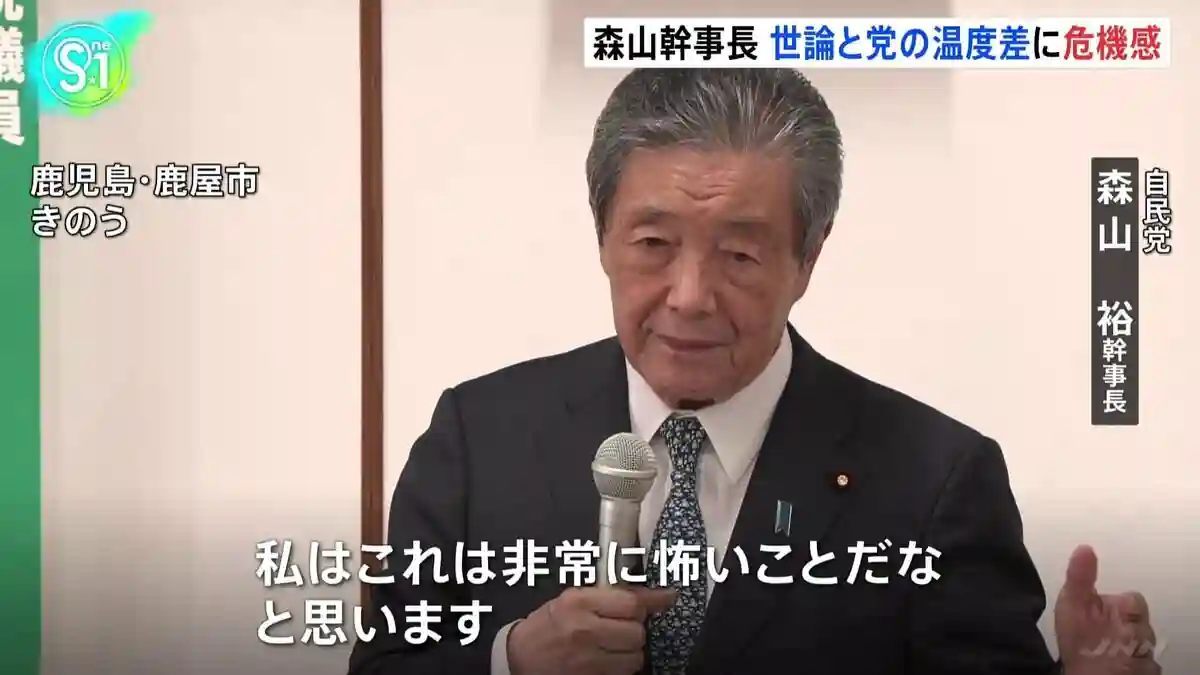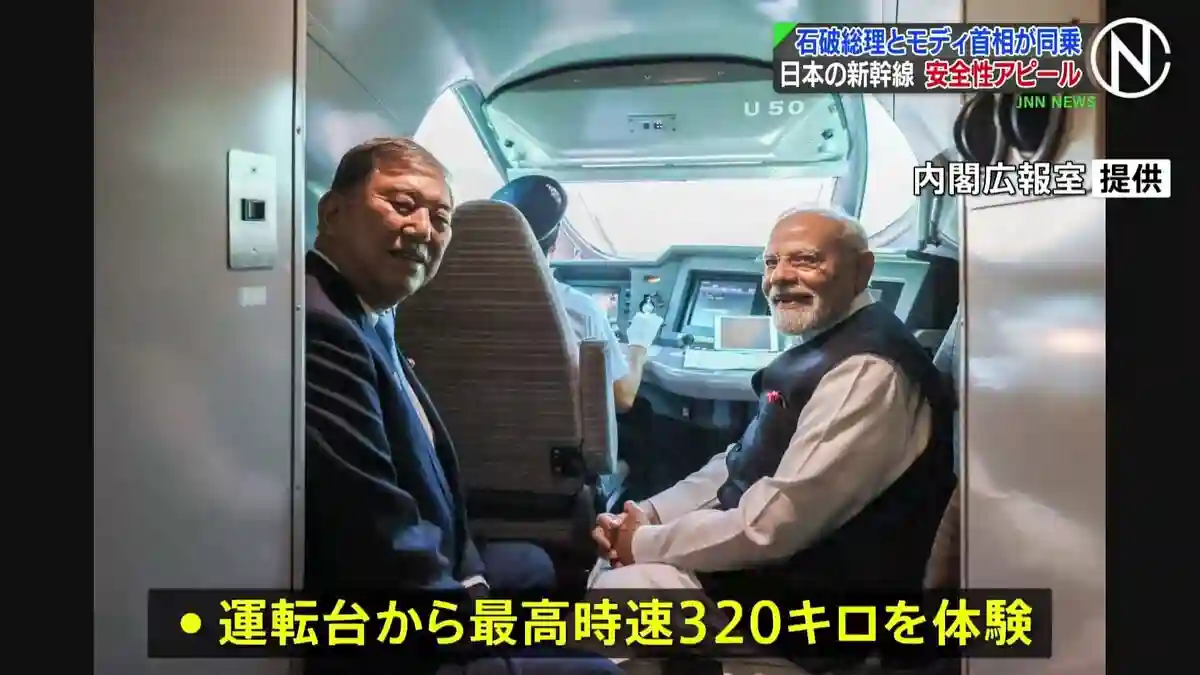野球ファンに衝撃が走った。ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の次回(2026年)大会をNetflixが独占配信することが25年8月25日、発表されたのだ——。 これまで日本代表「侍ジャパン」の試合は「国民的行事」として、地上波で中継され、時に視聴率40パーセントを超えることもあったお化け番組だった。それが有料配信サービスの独占コンテンツへと姿を変える。スポーツとメディアの関係に転機が訪れたといえそうだ。 「有料かよ」不満の一方で「テレビ持っていないから関係ない」 発表直後、ネット上には賛否が渦巻いた。「有料かよ、国民的スポーツなのに」という不満もあれば、「地上波じゃなくてもいい。画質も、視聴スタイルの自由度も高い配信のほうが快適」という肯定的な声もある。「もうテレビを持っていないから関係ない」という若年層の書き込みも目立った。 Netflix独占配信となった背景には、ひとつには放送コストの増大がある。まず放映権料の高騰。国際大会の権利料は年々値を上げ、日本代表戦となれば数十億円単位に達することも珍しくない。広告収入の伸び悩むテレビ局にとって、それを負担し続けるのは困難だ。日本シリーズの地上波中継が減り、Jリーグや大相撲の放送枠が縮小していったのも同じ構造だ。 さらに、スポーツ中継は制作費も高い。複数台のカメラ、専門スタッフ、大規模な中継車......。局の経営が厳しくなるなかで、コストの重いスポーツから手を引くのは自然な流れだろう。 もうひとつ大きいのは、視聴スタイルの変化だ。 スマートフォンやタブレットが普及し、時間や場所を選ばずに試合を見られる時代になった。DAZNやABEMAのような配信サービスは見逃し視聴やマルチアングルといった機能を備え、ファンの支持を集めている。若い世代はもはや「リアルタイムでテレビ観戦」にこだわらず、自分のライフスタイルに合わせてコンテンツを消費する。その自由度に比べると、地上波の放送枠はあまりに窮屈だ。 主催者のはずなのに...困惑にじませる読売新聞 こうした構造変化は、スポーツのありかた自体にも影響を与えている。「国民的行事」としてのスポーツは後退し、むしろ地域密着型の色合いが強まっているのだ。 Bリーグ発足以降は特にその傾向は顕著だ。地元クラブを応援する文化は着実に根づき、アリーナには熱心なファンが集う。実はそれはJリーグも同様で、地元チームの勝敗はその街のにぎわいや経済活動に直結する。スポーツの「全国的な統合イベント」という性格は薄れ、「ローカルな熱狂」が主役に躍り出ようとしている。 そんななかで今回のWBCをめぐるNetflix独占のニュースは、まさにスポーツ中継が歴史的ターニングポイントを迎えたと取るに十分なものだった。 それを象徴するのが、WBC配信をめぐる発表に関して読売新聞が——、つまりは傘下に日本テレビやジャイアンツなどを持つ、日本有数のプラットフォーマーにしてコンテンツホルダーが——、発表したプレスリリースである。リンクをたどって読んでいただければと思うのだが、ここで読売新聞は、 「当社はWBCIとともに本大会1次ラウンド東京プール(於:東京ドーム)計10試合の主催者として各試合の運営・興行を担っています」 「(前回は)地上波の番組での生中継が実現されました。しかし、本大会では、WBCIが当社を通さずに直接Netflixに対し、東京プールを含む全試合について、日本国内での放送・配信権を付与しました」 と述べている。どうしてこんなことに、という困惑と、自らも大資本でありながら、時代の流れを押しとどめられない歯がゆさのようなものがにじんでいると感じるのは、ひとり筆者だけではないだろう。 しかしここまで述べてきたように、地上波から人気スポーツが消えていくのは偶然でも一時的な現象でもない。経済的にも技術的にも、もはや不可逆の流れにあると考えるのが自然だ。 いまその役割は、グローバルな配信プラットフォームが取って代わろうとしている。