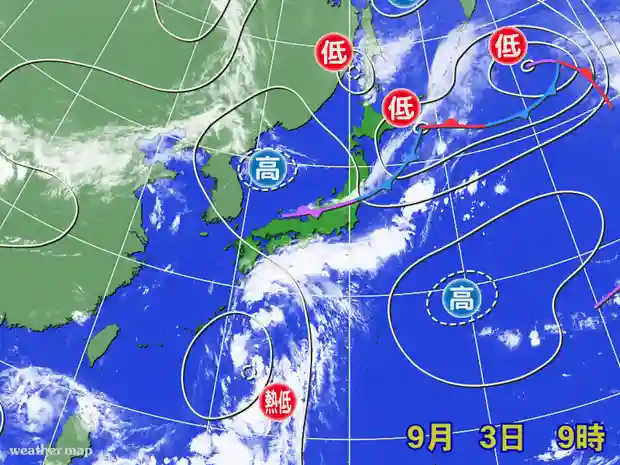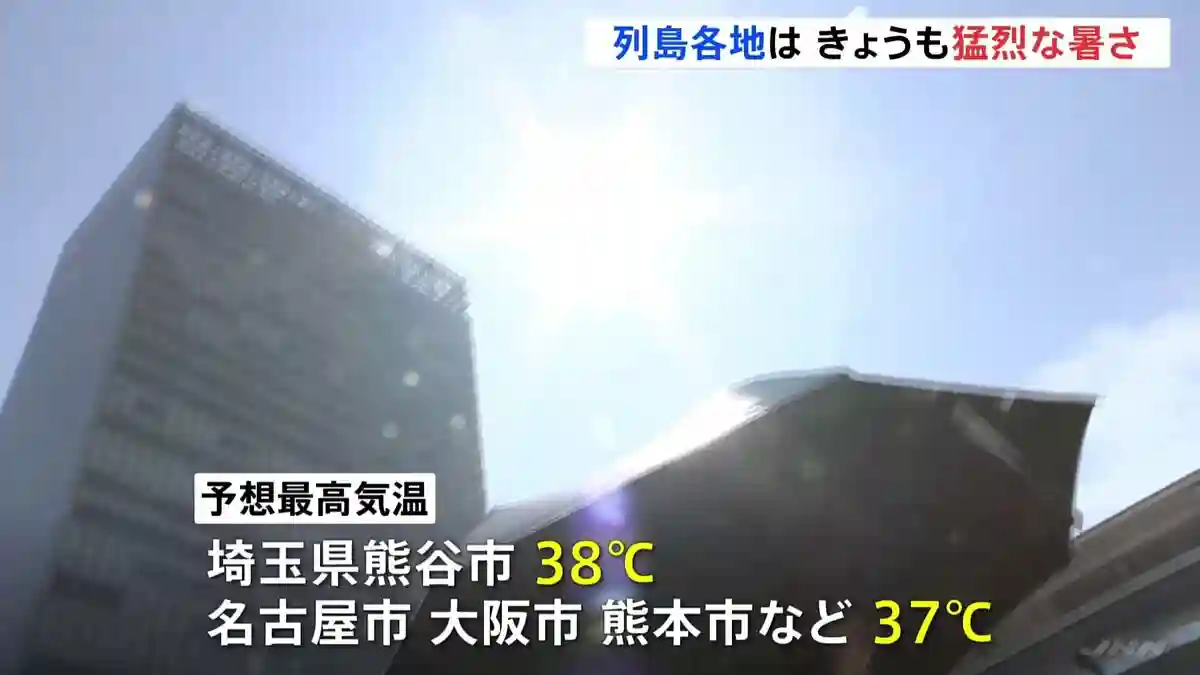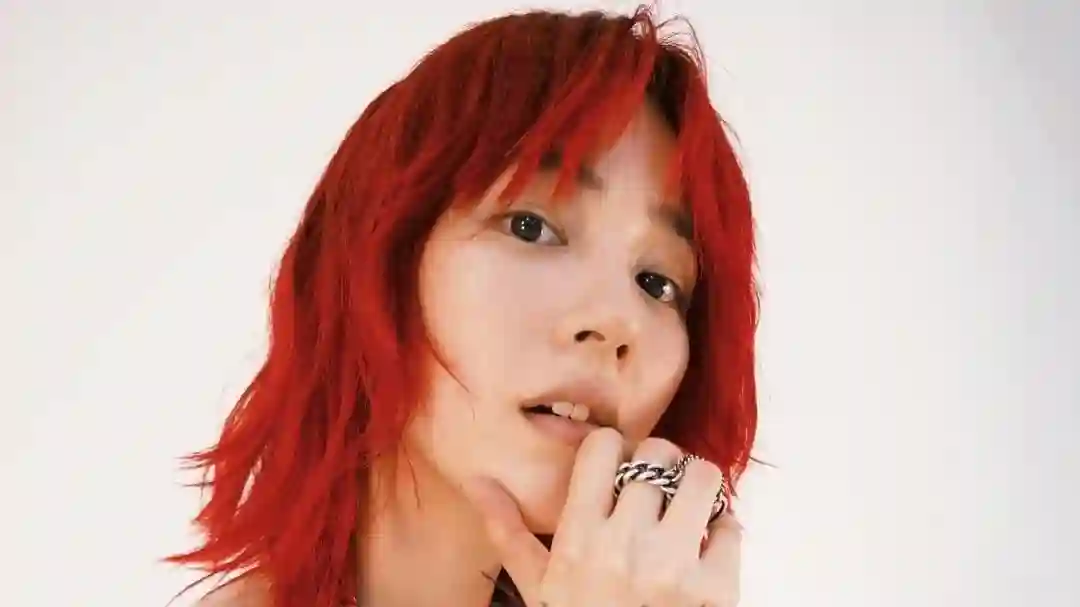GIGAスクール構想に令和の日本型学校教育──。2019年以来、文部科学省がぶち上げている教育政策では、デジタル・AIを軸にした「個別最適な学び」を推進しようという動きが主流になっている。「1人1台端末」「学習ログや行動データを蓄積し、子ども一人ひとりにぴったり合った『オーダーメイドな教育』」などが実現されるようだが、保護者からは不安の声も上がっている。「子どもがネット記事をコピペする」「計算力はAIが代替するから重要ではないと言われた」というものだ。本稿では保護者の実際の懸念の声を専門家にぶつけながら、お上が掲げる理想と教育現場が直面する課題にはどんなギャップがあるのか、検証した。取材・文=湯浅大輝(フリージャーナリスト) *** 【写真】教育現場で当たり前のように使われているタブレット端末には驚くべき「落とし穴」が 小学生が“ネット検索だけ”でレポートを書く時代 デジタル教育の弊害について危機感を持つのは、都内の公立小学校に通う男児(高学年)の保護者のAさん(40代)だ。Aさんはこう打ち明ける。 デジタル教育の意外な落とし穴とは 「うちの息子が通う小学校では、学校から配布されるデジタル端末(タブレット)を使った自主学習の課題が頻繁に出されています。自分で設定したテーマについて、書籍やインターネット検索を駆使して調べあげ、1つのレポートにしてタブレット上で提出するというものですね。実態としては、わざわざ書籍で調べる子は少数で、ほとんどがネット検索だけで提出している状況です」 「そこで息子は、大好きな『昆虫の生態』について取り上げようとしたのですが、インターネット検索の正しい方法を習っておらず、個人が書いたブログ記事もファクトチェックされた新聞記事も同じ『ネット情報』ととらえ、違いがよく分かっていません。結果として、悪い意味でいかにも『ネット情報』的な真偽不明のソースをもとにレポートをつくっていました。そもそも、以前の自由研究は子どもが実際に図書館に足を運んで行うものでしたよね。これが、その扱い方についての教育がないままネット検索に置き換わってしまっていいのだろうかと不安です」(Aさん) Aさんの不安を教育政策に詳しい愛知教育大学の子安潤名誉教授にぶつけてみた。子安氏によると、同様の課題は全国の公立学校で出されており、文科省が「モデルケース」として推進しているという。 「文科省はGIGAスクール構想の実現のために『GIGA StuDX推進チーム』を設置していて、全国の小学校・中学校・高校の現場で展開しているデジタル・AI教育の事例を紹介しています。最近増えているのが『教科書で最近学んだテーマや地域の名所をネットで検索して、自分の感想を添えてレポートにまとめましょう』というもの。Aさんのご子息の課題は決してレアケースではなく、全国的に広がっています」(子安氏) 自分でテーマを設定して、調査、レポートにまとめ上げることが目的なのであれば、何も「インターネット検索」を唯一の手段にしなくてもよいはずだ。さらにネットの膨大な情報量の中で「信頼に足る」情報を見極める技術も教わっていない中では、誤った情報を参照したり、ひとつの主張をそのままコピー&ペーストしたりするリスクも急増する。 実際Aさんは、 「今の小学生は皆中学受験で忙しく、『ネットですぐに答えが出るもの』で課題を済ませようとする子どもが多い。息子のクラスメイトは、『憲法』というテーマについて、ネットから引っ張ってきた情報で手早くレポートをまとめていたそうです」 と嘆く。 学校の課題で「タブレット端末を使って、インターネット上の情報をまとめる」ことに、どんな大義名分があるのだろうか。 子安氏は「『個別最適な学び』というコンセプトが背景にある」と分析する。 「個別最適な学び」の落とし穴 子安氏によると個別最適な学びとは、2021年に文科省の諮問機関である中央教育審議会の答申「令和の日本型学校教育」の中で示された概念で、学校教育に基盤的なデジタル・ツールを利用するなどして、子どもの特性にあった教育を行うことを指す。 子どもの学力や特性にかかわるデータを総動員し分析・活用することで、集団での授業による画一的な教育の脱却を目指す。デジタル端末やデータを駆使して、一人ひとりにピッタリはまる「オーダーメイド」な指導を行うとともに、子ども自身が個性を存分に発揮して学習を自らデザインしていこうというのが「個別最適な学び」の要旨である。 この個別最適な学びを教育現場で推進する上で重要になる教育方法が「自由進度学習」である。自由進度学習とは、子ども自身が学ぶ内容やペースを決める手法で、すでに学校に取り入れられはじめている。 自由進度学習とタブレット端末を使った課題の相性は抜群である。何しろアナログの現場で必要だった教師と生徒の双方向の細かいコミュニケーションがいらず、タブレット一つで進捗を管理できるからだ。 「タブレット端末でレポートにまとめる」という課題は、まさにこの「個別最適な学び」というアジェンダを達成するための自由進度学習の一環だったわけだ。 いくら「自由」にネット検索できるとはいえ、正しい検索方法に無知でネットの「毒」への免疫がなければ、小学生の子どもに教育目的で使わせるのは心配だ、と感じるのは親心であろう。現場の先生は、この課題に関してどのように指導しているのだろうか。子安氏は、 「まずレポートの評価で言えば、昨今は生成AIのコピペ対策を警戒するあまり『独自性のある文章か』『文体がその子どものものか』といった表現の質が最優先されます。つまり『どのように情報を調べたか』『情報の精査をしたかどうか』といったプロセスの評価は二の次になっています」 一方、子安氏は現場の先生だけを責めることは酷だとも指摘する。 「特に今の教育現場は教師の裁量が年々狭くなっていて、学習指導要領と学校が決めるカリキュラムにはとりあえず従うしかないのが実情です。自由進度学習は学校にとっても比較的新しい教育手法ですから、評価の方法もかなり画一的なものになっているのでしょう」 実際、Aさんが懸念を先生に伝えた際「仰っている意味はよくわかります」と返答があったそう。 「先生方も毎日『これで本当にいいのか』と悩みながら手探りで授業に取り組んでいるのでしょう」(Aさん) 「街の探検」もタブレットで撮影するだけ…… 子安氏は「個別最適な学び」が主にデジタル端末上で展開されることを懸念する。スウェーデンなど世界のデジタル教育先進国で「タブレット端末に依存した学習は、対人コミュニケーションの総量を減らす」という論文や関係機関の公式見解が出ていることがその理由である。 「タブレットでの検索に依存した学習の最大の問題点は、直接の社会現象に積極的に交わっていかなくなることでしょう。ある小学校の先生から聞いたのですが、小学3年生の体験学習で『街の探検』というものがあります。実際に地域の商店や食品スーパーに赴いてどんな商品が売られているのかを体験することが目的ですが、今の児童は手持ちのタブレット端末で写真と動画を撮ることに終始してしまうそうです。自分の眼で売り場や商品を見たり、店員さんにどんな商品が売れているのか聞いてみたりする児童が少なくなったのです」 「子どもにとって『体験』とは五感をフルに活用して、人とコミュニケーションを取ることではじめて心に残っていくものです。これを『とりあえずレポートに載せるために写真を撮っておこう』とするのは教育というより、やっつけ仕事というか、ただの作業に堕落しています」(子安氏) AI時代に「計算力」は身につける必要がないのか Aさんの不安は自由裁量のレポート課題にとどまらない。学校の先生が授業で発したある言葉が引っかかっているのだ。 「これからの時代、計算力などの基礎的な能力はAIが代替してくれる。だから計算力以外の力、たとえば課題解決能力を身につけよう」というようなものだ。 実はそのような考えをもつ現場の先生は少なくない。筆者がこれまで書いたデジタル教育に関する記事にも、「文明の利器を否定し、今さら馬車に乗ろうと主張するのか」と、「課題解決能力重視」の声がいくつも寄せられている。 子安氏はこの「AIが基礎的な能力を代替する論」はそもそも文科省が否定していると一刀両断する。 「教育課程企画特別部会の議論で『計算力そのものをAIで代替しよう』という報告が出たことはありません。計算力をつけるためにAIを活用しようというアイデアは存在しますが、『子どもに計算力は必要ない』と結論づけた例は少なくとも今のところまだありません」 「もちろん、これまでも中学校や高校では個別の計算で電卓を許可する例はありました。ただ、計算式を立てたり、計算式を立てた理由を答えたりする能力をAIにやらせると、それはもう子どもの回答ではないでしょう」(子安氏) 当然だが、長方形や平行四辺形など図形の面積の求め方が分からない子どもが、計算式をAIに聞いて結果をそのままコピペしただけでは「計算力」がついたことにはならない。底辺と高さを正しく見極める原理原則が頭に入っていなければ、AIなしで同様の問題を解くことはできないからだ。 「今日の心の天気」で「雷」は絶対に選ばない理由 「個別最適な学び」を支えるのは、デジタル端末を活用した学習サポートにとどまらない。子どもの学習履歴や行動記録を「データ化」し、子どもの傾向を細かく知ることも重要だとされている。 現に埼玉県戸田市はこども家庭庁から受託し、「1万2000人の児童生徒のデータを分析して、子どもが不登校になる可能性を数字で可視化」する実証実験を行なっている。 「教育履歴をビッグデータ化し、データから得られた知見を現場の指導に落とし込んでいく」という事象はすでに現場で見られると子安氏は語る。 「大阪府のある公立中学校の先生から聞きましたが、毎日一定の時間にタブレット端末を開き、アプリ上で『心の天気』を入力するという時間がすでに存在するようです。晴れ・曇り・雨・雷の4つから今の気持ちを入力するようですが、生徒によっては『雷を選択すると、後で先生に呼び出されて面倒だから絶対選ばない』という子どももいるそう」 子安氏は、教育データを現場で利活用する発想そのものは否定しない。そもそも「子どものデータ」という概念が存在する以前から先生にとって、子ども一人ひとりの性格を熟知し、それに合わせて教室を運営することは重要な能力だったというのがその理由だ。 一方、AIによる子どもの行動分析は過去のデータによる「類型化」という罠を逃れることができず、あくまで統計の範疇を出ないことを意識すべきだとも説く。 「子どもは過去に事例がない成長を遂げたり、逆に誤った道に進んだりするものです。『過去のデータによると、不登校になりかけている子どもにはAという対応が効く』とAIに教えられて、それを盲信するのは危険でしょう。同じ不登校という行動ひとつとっても、子どもが感受する経験は千差万別です。データも重要ですが、目の前の子どもとコミュニケーションを取り、具体的な心の揺れを掴んでおく方が有用だと思います」 ここまで見てきたよう、デジタル端末とデータを活用した「個別最適な学び」は、現場で正しく実践するには相当にハードルが高い。文科省が掲げる理想と先生が毎日行う授業の間には、大きな乖離が存在するからだ。 デジタルがもたらす新たな教育効果をフルに実現するためにも、このギャップをどのように埋めていくか。まずは「理想と現実には差がある」ことを確認することが第一だろう。 〈関連記事【都立校も導入「AIの教育活用」は“脳が怠けて抜け出せなくなる” MITが発表した衝撃の研究結果とは】(有料版)では、教育現場における生成AIの認知機能に対する影響について、米MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボが発表した衝撃の論文内容について解説している〉 デイリー新潮編集部