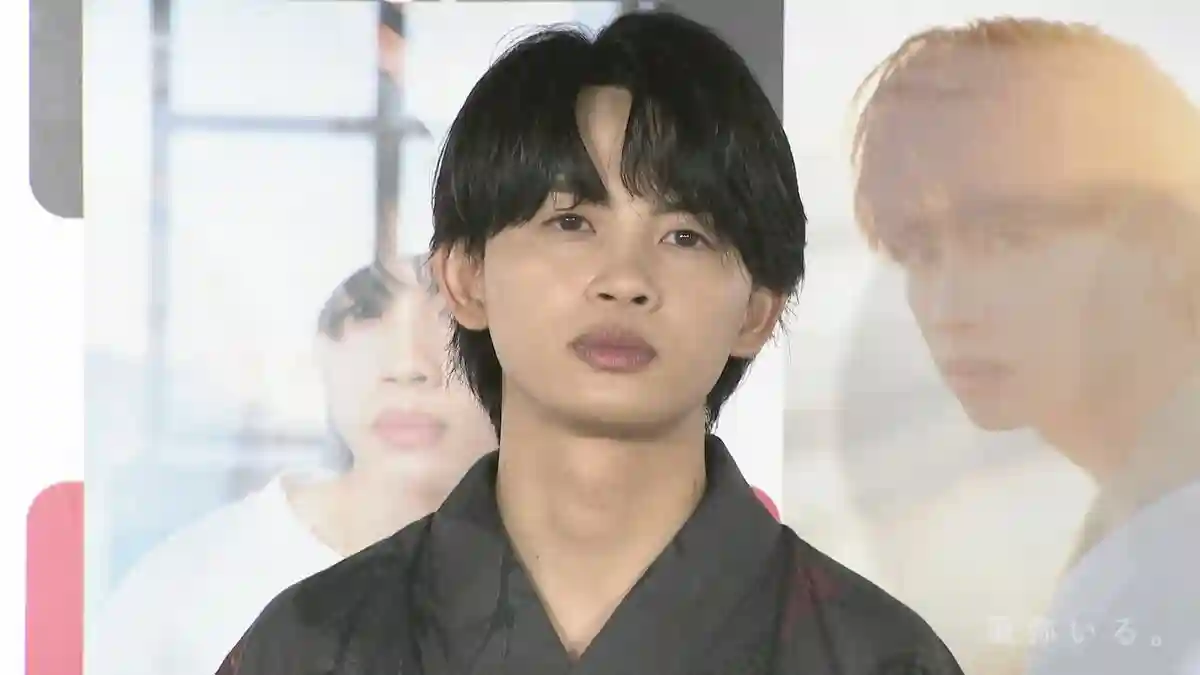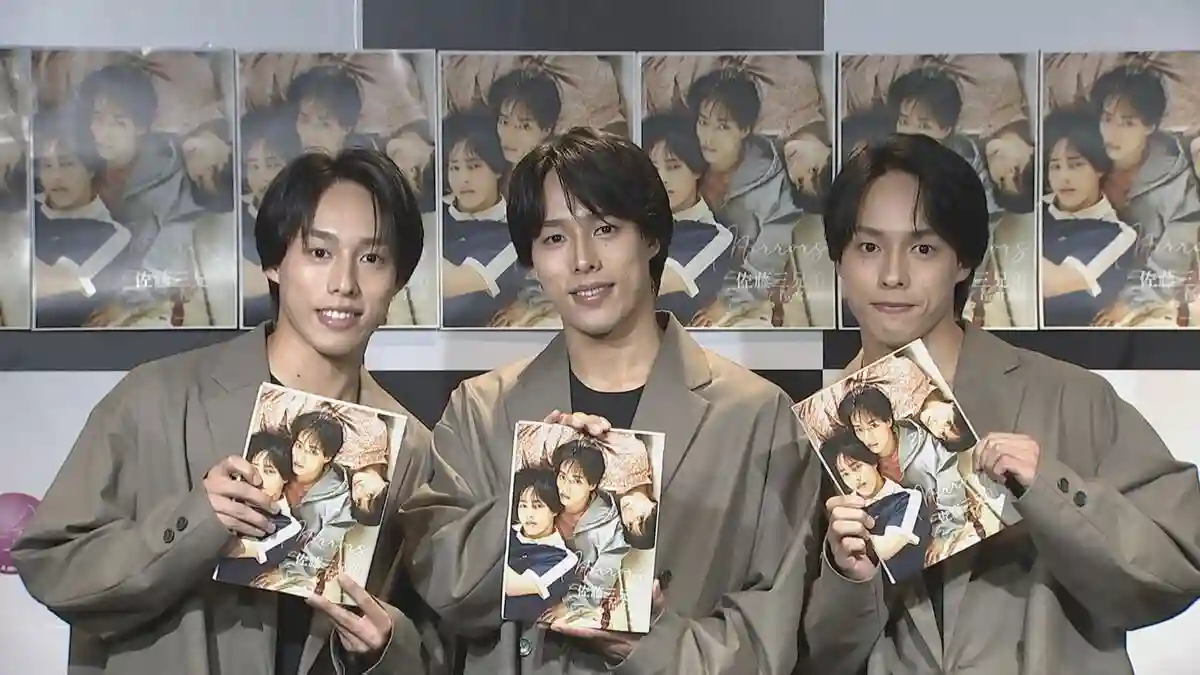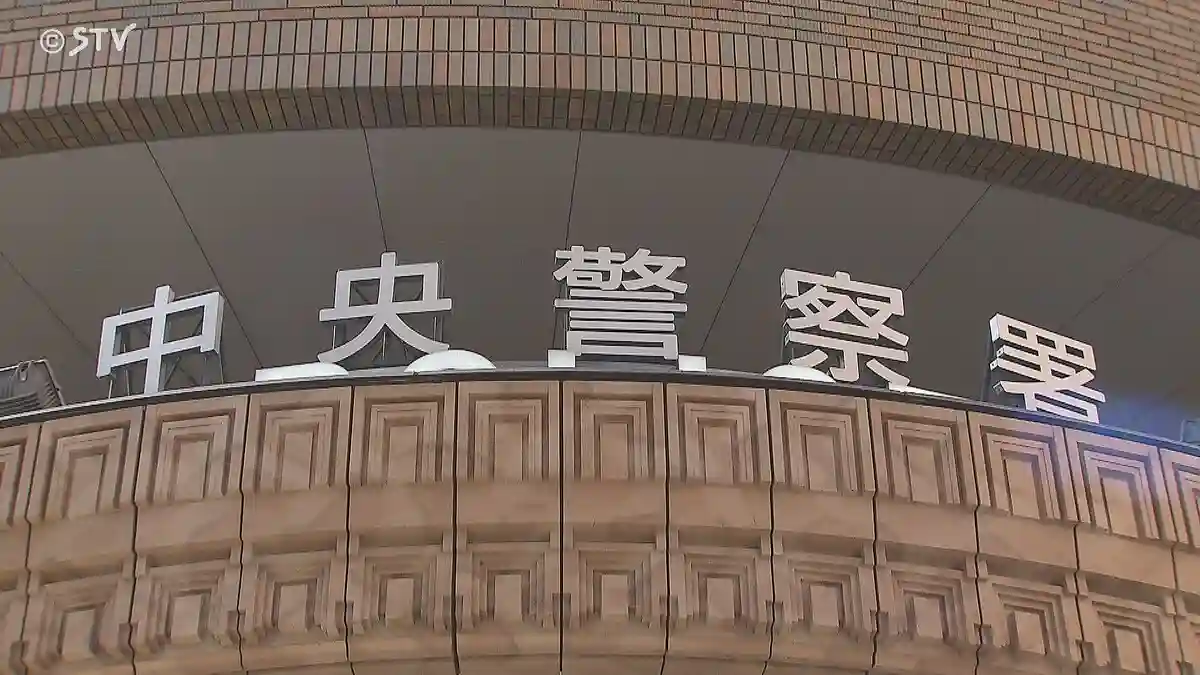「裁判官」という言葉からどんなイメージを思い浮かべるだろうか? ごく普通の市民であれば、少し冷たいけれども公正、中立、誠実で、優秀な人々を想起し、またそのような裁判官によって行われる裁判についても、信頼できると考えているのではないだろうか。 残念ながら、日本の裁判官、少なくともその多数派はそのような人々ではない。彼らの関心は、端的にいえば「事件処理」に尽きている。とにかく、早く、そつなく、事件を「処理」しさえすればそれでよい。庶民のどうでもいいような紛争などは淡々と処理するに越したことはなく、多少の冤罪事件など特に気にしない。それよりも権力や政治家、大企業等の意向に沿った秩序維持、社会防衛のほうが大切なのだ。 裁判官を33年間務め、多数の著書をもつ大学教授として法学の権威でもある瀬木氏が初めて社会に衝撃を与えた名著『絶望の裁判所』 (講談社現代新書)から、「民を愚かに保ち続け、支配し続ける」ことに固執する日本の裁判所の恐ろしい実態をお届けしていこう。 『絶望の裁判所』 連載第32回 『気に入らない裁判官の“再任拒否”は人事局の思いのまま…裁判所制度の諸改革を「悪用」する当局の実態』より続く 司法研修所は「人事局の出先機関」 司法研修所は、司法試験に合格した司法修習生(以下、単に「修習生」という)の教育と裁判官の生涯教育を担当する機関であり、セクションもこの2つに大きく分かれている。 こう書くと、誰でも、法科大学院に類するような高等教育機関というイメージを抱くであろう。しかし、実際にはそうではない。 これは、学者を含む法律家の間にさえあまり知られていないことなのだが、司法研修所は、事務総局人事局と密接に結び付いて最高裁長官や人事局長の意向の下に新任判事補を選別し、また、裁判官の「キャリアシステム教育」を行う、実質的な意味での「人事局の出先機関」なのである。 人事局と司法研修所教官、ことに修習生の教育選別を行う部門と裁判官教育を行う部門との各上席教官(後者の上席のほうが格は上)、また司法研修所事務局長(以上、いずれも東京地裁裁判長クラスの裁判官)とのパイプはきわめて緊密である。そして、彼らを通じて、人事局は司法研修所教官を動かしている。 普通に司法研修所教官といえば、修習生教育を行う教官であり、数も多い(なお、この教官には、検察官、弁護士もいるが、以下では裁判官の教官について論じる)。彼らが選ばれる基準については、昔は教える能力もそれなりに重視されていたのだが、今日では、教えることはマニュアルどおりにやればよく(自分の考えなどむしろもたないほうがよい)、事務総局のお眼鏡に適うような人物をうまく選別して任官させる能力のほうが重要といった方針で選ばれる傾向が非常に強まってきている。 その意味では、司法研修所教官は、裁判官の中でも、外部の人々がそれについて抱く幻想が最も大きい種類のポストであろう。大学教授とは全く異なった観点から教官が選ばれていることは、知っておいていただきたい。「研修所に学者なし」といわれるゆえんである。 日本を震撼させた衝撃の名著『絶望の裁判所』から10年。元エリート判事にして法学の権威として知られる瀬木比呂志氏の新作、『現代日本人の法意識』が刊行され、たちまち増刷されました。 「同性婚は認められるべきか?」「共同親権は適切か?」「冤罪を生み続ける『人質司法』はこのままでよいのか?」「死刑制度は許されるのか?」「なぜ、日本の政治と制度は、こんなにもひどいままなのか?」「なぜ、日本は、長期の停滞と混迷から抜け出せないのか?」 これら難問を解き明かす共通の「鍵」は、日本人が意識していない自らの「法意識」にあります。法と社会、理論と実務を知り尽くした瀬木氏が日本人の深層心理に迫ります。 丸暗記・丸写し教育 むしろ、司法研修所教官は、その中で「使える」ような者を選別してたとえば地方の高裁事務局長にするなど、司法官僚の2次的な選別コースになっているといわれる。2次的というのは、能力からすると、事務総局課長や最高裁判所調査官に比べればよりばらつきが大きいからである。ただし、近年は、情実人事的傾向の進展に伴い、上司の顔色をうかがうことに秀でたイエスマンの多い司法研修所教官が取り立てられる例が、以前よりも多くなっている。 そのような教官が教えるわけであるから、教育内容は、当然、千編一律のマニュアル詰め込み、丸暗記が中心であり、また、異説はきらわれる。したがって、修習生たちの考える力や分析力は伸びず、かえって、丸暗記、丸写し教育の弊害が出てくる。 また、新任判事補の選別も、客観性に乏しいものとなっていく。 弁護士人気が高まったバブル経済の時代に新任判事補の下限レヴェルの質は著しく落ちており、不況期に入ってからもそのことは変わっていない。平均的な修習生のレヴェルに達しない能力、成績の者が相当数裁判官に採用されており、ことに、司法試験合格者がかなり増加した後の新任判事補の中には、判決書起案の主文にまで書き落としや形式ミスが目立ち、注意されてもなかなかそれがなおらないといった例までが存在する。 これは、今日の優秀な修習生の多数(私がみてきたところでは7、8割程度)が弁護士になり、かつてのように裁判官に人気がなくなってきたことにもよる(なお、検察官については、近年、昔よりも人気がある)が、もう1つの理由は、教官が、能力主義の公平な評価を行っていないことにあると思う。 教官の中には、「教え子について悪いことは書けない」などと言って、能力不足の人について問題はないとの評価を行い任官を可能にする例があるのだ。しかし、そういうことを言うのであれば、自分自身がその教え子と合議体を組み、責任をもって教育すべきなのである。前記のような発言は、評価者として無責任もはなはだしい。結局、配属先でその指導に当たる裁判官のみならず、当の本人も苦労することになるからである。 「考える力」に乏しい裁判官 この点についても、テレビドラマや青年漫画誌のような感覚で、能力がなくても人のいい裁判官ならいいんじゃないか、などと考えるべきではない。裁判官の法的能力が弁護士よりも相当に低ければ、適切な訴訟指揮などできるわけがない(そのような裁判官を、ゴルフのたとえで「池ぽちゃ裁判官」と呼ぶ弁護士もいる)。また、考える力に乏しければ、まともな判断や和解案の提示もできない。一定の知的、法的能力は裁判官の最低必要条件なのである。 また、裁判官としての基本的な能力に欠けるところのある人は、伸びるといっても一定の限界があり、さらに、だらしなかったり、自己認識に欠けていたり、鼻息ばかり荒かったり(それだけならまだしも、自分の裁判長の言うことは聴かずに所長や所長代行の言うことばかり聴くなど、よりたちが悪い場合がある)で、指導がままならないという話を聞くことも多い。 自分の能力適性に関する正確な認識を欠いている場合が多いから、右のような事態を招くのであろう。 また、私の退官直前ころのことであるが、以前に比べて、裁判官任官希望者を評価する基準がさらに主観的、恣意的なものになっているのではないかという意見も複数耳にした。具体的には、組織になじむ人物であるか否かが以前よりも重視されているというのである。新任判事補選抜の際にまで、この書物に記してきたような意味での事務総局の意向に沿う人物か否かが、正面から考慮されている可能性があることになる。 これが単なる噂であればよいのだが、私自身、なぜこの人が任官できないのだろうと不思議に思った例、反対になぜこの人が任官できたのだろうと不思議に思った例を複数みているので、前記のような事柄を根拠のない噂として片付けることはできないのではないかと考えている。 『日本の裁判官の質が低下している原因は「徒弟制」にあった…若手判事補の日常教育に潜む問題点に迫る』へ続く 日本を震撼させた衝撃の名著『絶望の裁判所』から10年。元エリート判事にして法学の権威として知られる瀬木比呂志氏の新作、『現代日本人の法意識』が刊行され、たちまち増刷されました。 「同性婚は認められるべきか?」「共同親権は適切か?」「冤罪を生み続ける『人質司法』はこのままでよいのか?」「死刑制度は許されるのか?」「なぜ、日本の政治と制度は、こんなにもひどいままなのか?」「なぜ、日本は、長期の停滞と混迷から抜け出せないのか?」 これら難問を解き明かす共通の「鍵」は、日本人が意識していない自らの「法意識」にあります。法と社会、理論と実務を知り尽くした瀬木氏が日本人の深層心理に迫ります。 日本の裁判官の質が低下している原因は「徒弟制」にあった…若手判事補の日常教育に潜む問題点に迫る